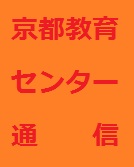
 |
●京都教育センター通信 復刊第84号 (2014.3.10発行) |
「ぐるぐるプラン」で地域再生を
京都中小業者連絡会 坪井 修
●誰が京都経済の活力を奪ったのか
府内事業所の減少は直近3年間で11.029軒。減少率はマイナス8.1%で被災地除く全国ワースト1位。
現知事は、「事業所の廃業率が高いのは事実」と認め、「廃業理由に踏み込んで、いま対策を講じている」と答弁した。(2014年2月13日府議会) しかし、現知事は、これまで「規制緩和によって強いものが勝つ、これは非常に成功した」(2008年2月7日、関西財界セミナー)、「ベンチャーは、種を育てていくということがある。そういう面からの補助と、普通に経営されている方の固定費を同列に扱うというのは無理がある」(2009年11月24日府議会)と、一部の大企業やベンチャー企業への偏った支援で、「強いものが勝って当たり前、弱いものは市場から退場せよ」という「弱肉強食」構造改革路線を貫いてきた。その結果が、まちなかでも「買い物困難者」が生まれるような全国最悪経済にまで落ち込ませたと言わなければならない。
●住民の豊かな暮らしに貢献する循環型経済へ
ある牛乳販売店では、高齢者のお客さん宅で、前日に配達した牛乳がそのままに置かれていた時には、役所に連絡して安否を確認するなど、地域の「見守り隊」の役割を果たしている。先日、「消費税増税アンケート」で訪ねた牛乳販売店主は、「消費税を上げたらお客さんはやめてしまいます。前に上がった時も大口の得意先がやめてしまった。タメ息ばかりだ。」と語っていた。知事は、増税の旗振り役をしておきながら、「消費税率の引き上げによる要配慮者への生活支援、販売力強化、落ち込み防止に取り組む」(府議会答弁)と言うが、史上最大の増税をかぶせておいて無責任極まりない。
「世を経(おさ)め、民を済(すく)う」「経世済民=経済」の担い手として、中小企業者は、自らの本業を通じて地域の住民の豊かなくらし向上にどう貢献していくか探り努力している。そうした中小企業者と府民の合意形成をめざす「地域再生ぐるぐるプラン」を掲げる尾崎望さんで必ず府政を転換させようと思う。
京都教研2013「学校づくり」分科会報告 スモール・イズ・ビッグ 小ささの教育力
こうして六年生になる!
〜サーティーンたちとともに歩む 普賢寺小学校最高学年の一年〜(前半)
京田辺市普賢寺小学校分会 府金 隆清
はじめに
よく聞かれる心配が「少人数の中ではよくても、大きな集団では埋もれてしまう。」という声です。けれども大きな小学校では、全校規模での出番があるのはごく限られた人数です。前思春期の子どもたちにとって異年齢の中での活躍というのは、大きな飛躍を与えてくれる糧となるものです。本校の児童、特に6年生はいやというほど出番があります。それも学級=学年はもちろん、異年齢のたてわり集団の中で、さらに少人数とはいえ全校児童の中で、そして保護者や地域の人たちの注視の中での出番も少なくありません。それらを通じて、「どうかな・・」と思われていたような子どももちゃんと6年生らしくなるのです。楽しみに待っている子もたくさんいますが、いやだと思っている子でも「しかたない」という覚悟はしているのです。これも地域性、環境を生かした長年の全校集団作りの成果です。そして、その観点から「全校集団作りを通じて子どもを育てる基本的な視点」として以下の3点を特活部の方針として確認しました。
①「少人数の学級、学校の中で力が発揮できても大勢の中では萎縮してしまったり、引っ込んでしまう=小さい学校の弱点」という懸念、そうなってほしくないという期待に応えられる学校づくり、集団作りのアプローチ「小さい学校だからこそ全ての子どもに、豊富な出番がつくれる。その中でこそ自信と自覚を育てられるし、大きな集団でも力が発揮できる素地を作れる。その自信と自覚の記憶は一生の財産となる」という視点
②全校集団作り、わけても6年生を前面に押したて、活躍させることを学校づくりの一つの中核にすえる。少人数学級の中での自治活動には限界があるが、全校に目を向けることで広がりができ、一人ひとりが伸び、学級づくりも進むという視点。
③子どもたち自身が“6年生ならではモノをやりたい”という意志を持っている。それが濃密な人間関係の中で、代々受け継がれてきている。その気持ちを生かし、育てるという視点。
3年間の組合専従による休職期間を経て普賢寺小学校に復帰した私は、実に7年ぶりに5年生を担任することになりました。そして今年は6年生。久しぶりに自分自身が担任する高学年で、こうした実践を着実に展開し、発展させていくことができるのか正直不安がありました。
現在1月末、ゴールまで2か月たらず。まだまだ曲折はあるかもしれませんが、この10ヶ月間の成長を見るだけでも、普賢寺小学校の持っている力はサーティーン(児童数13人の今年の6年生の子どもたちを通信等で、こう呼んでいる)たちにも機能し、徐々に6年生らしい6年生に育ってきていることは間違いありません。
この報告では、サーティ−ンとともに過ごしてきた“最高学年”としての日々を追い、実際にどんな学習や活動の中で子どもたちに自信と自覚が育っていくのかを捉え直してみようと思います。きっと、その全体像の中に「スモール イズ ビッグ」の一つの側面が浮かび上がってくるのではないかと思っています。
1.特活部方針への反映〜全校的な合意形成
(特活部方針より抜粋)
2、指導の重点
(1)さまざまな構成の集団活動において各々が役割を自覚し、協力して目的をやり遂げていく能力を育てると共に、リーダーの姿を実践的に学ばせる。
(2)児童会活動・学級活動を充実させる中で、自分達の生活の現状を正しく捉える資質や、自分達でより楽しく規律ある生活を築いていこうとする自主性を養い、解決や実現の過程を経験させることを通じて実践的能力を育てていく。
(3)教科指導、生徒指導、各行事などとの関連を図りながら多様な集団、多様な活動を展開し、学校生活を楽しい充実感のあるものとしていく。
9、異年齢集団づくり
(1)ねらい
学級集団の枠を超えて、年齢の異なる子ども達が協力して諸活動に取り組む事を通して、上級生はリーダーとしての役割を体験し、下級生はリーダー像を学び自覚を高めていく場とする。
また、少人数の学級集団では経験できない様々な規模・構成の集団での活動を保障していくことは本校においてはとりわけ重要な意味を持つので、計画にあげられている行事の場だけでなく、日常的に機会を作っていくように意識的に取り組む。
(2)活動
①あおぞらグループ
6年生をリーダーとした、全校縦割りグループ(今年度は赤3、白3の6グループ 通年)
1年生を迎える会、グループ遊び(5月、6月、10月、11月、12月)、夏祭り(準備の中でグループ給食)、運動会グループ競技、大縄大会、6年生を送る週間、6年生を送る会。
②色別グループ
運動会での応援、リレー、団体競技(1、2、3年と4、5、6年)
③学年ブロック
[1、2、3年と4、5、6年ブロック] 運動会(団体競技・表現)等
[1、2年と3、4年と5、6年] 学習発表会、遠足(春は1、2年のみ)等
[4、5年] 林間学習・送る会等
[1、2年] 生活科の諸活動等
[5、6年] パーティー給食、大豆の殻むき、味噌作り等
[1、6年] いきいきタイムの読み聞かせ、新体力テストのペア、8の字跳びの指導等
④掃除班
6年生または4、5年生を班長とした異年齢集団(2名〜6名)。3期制
⑤地域仲良し会 地域ごとの集まり(年4回)
※その他
[5年生と幼稚園児] 田植え、餅つき(5年生は入学予定児との給食交流もある)
[6年生と幼稚園児] とうもろこし・枝豆の収穫
2.それは、5年生から始まった
○5月の初めに林間学習です。南山城少年自然の家使用のトップバッターです。このところいつもこの時期だったそうです。クラス替えがあってごちゃごちゃしている他校ではとてもこの時期に林間は無理。しかしわが校ならできる。5年13人、4年17人の30人クラス替えはなし。しかもわが校の特徴である、4年・5年合同の林間学習なので、5年生が経験者として4年生をリード、準備は早い。見通しのきく子どもが決して多いとはいえないわがサーティーンながら、補い合いながら4・5年混合班の班長やまとめ役を務めた。このときには役割がはっきりしていたからだろう、その姿が際立って見え「なかなかやるな感」をもたせてくれました。
○「来年は君たちの番、6年生のやることをしっかり見ておくんだよ。」ことあるごとに5年生はそう言われ続けます。私も意識的にフォローシップ、支え役としての5年の役割を強調しました。しかしあまりパッとしません・・児童会活動の中心を担う「運営委員会」も5年生、6年生がそれぞれ3人ずつなので、すでに児童朝礼や運動会の児童会競技の司会などで、全校向けのデビューを飾っている5年生もいます。また地域によっては、5年生から通学班の班長になることもありますし、掃除班も5年生がリーダーになる場合もありますから、それなりにリーダーの仕事を受け持ってはいるのですが、サーティーンには支え役というのは難しかったようです。「5年生がふざけて困ります。」と6年生の子どもに苦情を言われたこともありました。とはいえ、やはりこの時期は見習い期間です。あまり6年生をサポートするような動きになっていなかったとしても「来年は自分たちがやらなければならなこと」という目で、一つ一つの活動にかかわっていたようです。
○やはり存在が意識を規定するものです。本格的に「最高学年」を突きつけられたのは、3学期「6年生を送る取り組み」からです。この取り組みは5年生が言い出さないとスタートしないから今年はどうする?の問いかけへの答えから話し合いました。「6年生が最高に楽しめて感動できる心に残る送る会にしよう。」(めあて)を決め、2月5日、6年生抜きのあおぞらグループ会で提案し、サーティーンの実質リーダーデビューを果たしました。そして卒業式までのいわば引継ぎ期間、バトンゾーンタイムで、「学級」の中の事でなく、全校に関わることが「学級」の課題になっていきました。この中で、サーティーンは不安や緊張、心配、怖れなどを体験しつつも、一つ一つを成功させ、(小さな失敗もしつつ)不安を安心に怖れを自信や希望に変えていきました。
(前半終了、後半は次号に掲載します。)
京都教育センター 2013年度活動の報告
学校・地域の実態から学び、探究し・発信しました
1.第44回京都教育センター研究集会
12月21日〜22日、教育文化センターで開催。集会テーマとして「子どもが育つ地域・学校への探究」を掲げ、全体会では岡田知弘氏の講演「構造改革は地域・学校に何をもたらしたかー住民・子どもが主人公の地域・学校のあり方を考えるー」、パネルトークは「地域・学校で育つ子どもたち」として少人数学級のよさや地域で子どもたちが育つ意義などについて議論された。二日目は各研究会による9つの分科会を行った。参加者は1日目64人、2日目114人。
2.公開研究会の開催
各研究会が企画開催した研究会15回開催され、次の二つはセンター全体で重点的に取り組んだ。
・「安倍政権の教育改革のゆくえ:石井拓児さん」(教育センター・教科書連絡会共催) 6/16 〈35人〉
・「発達障害と子どもたちー集団としてどう関わるか:別府哲さん」
(教育センター・障教センター・京教組障教部)10/26 〈54人〉
3.教育研究集会・民教委、民研などへの参加
第63次京都教育研究集会(1/25〜26:教文センター他)には共同研究者として二日間でのべ55人が参加。民主教育推進委員会には共同研究者・世話人として21人(8/31)、28人(11/10)、20人(1/18)が参加。8月の「全国教育のつどい(愛知)」に11人が参加。
・ 共同のとりくみとして「子どもと教科書を考える連絡会」「教育・子育てネットワーク」「教育府民会議」「学校統廃合・小中一貫教育連絡会」などに参画。
4.季刊誌「ひろば・京都の教育」の発刊
| ・174号(5/15) ①体罰について考える ②子どもの居場所としての学校のあり方 ・175号 (8/7) ①学力テスト体制について考える ②学校統廃合と地域 ・176号(11/13) ①安倍教育改革と教科書 ②乳幼児の育ち ・177号(2/19) ①人にやさしい京都府政に ②子どもが育つ文化・表現活動 |
5.「センター通信」の発行
| 73号 | 室崎生子/富田宣之(舞鶴) |
| 74号 | 野中一也/金井多恵子(市・栄) |
| 75号 | 高橋明裕/新庄久美子(福知山) |
| 76号 | 得丸浩一/上田正文(京都市小) |
| 77号 | 倉原悠一/上田正文(京都市小) |
| 78号 | 中須賀ツギ子/下田正義(乙訓) |
| 79号 | 内野 憲/大西新吾(亀岡) |
| 80号 | 中西 潔/渋谷清孝(船北) |
| 81号 | 河口饠洋/別府哲講演① |
| 82号 | 大平 勲/別府哲講演② |
| 83号 | 小笠原伸治/別府哲講演③ |
6.出版活動
今年度出版活動はできませんでした。これまで出版した「原発・放射線をどう教えるか」(教育センター編集・京教組発行)を普及することと、このテキストなどを用いての実践の広がりが今後の課題となっています。また、50周年記念誌としてセンターが刊行した「風雨強けれど光り輝く」と、一昨秋刊行した早川幸生著「京都歴史たまてばこ」(「ひろば」連載)の普及に努めます。
7.研究活動
9つの研究会があり、それぞれ独自に研究活動を展開していますが昨年度休会状況にあった「発達問題研究会」と「教科教育研:国語部会」が、研究会再開をめざしてとりくみ、第44回研究集会ではすべての研究会が分科会を開催することができました。さらに研究委員の拡大に努めます。
8.事務局・運営委員会体制
代表:野中一也 研究委員長:高橋明裕 「ひろば」編集長:西條昭男 事務局長:本田久美子
運営委員(上記含め): 高垣忠一郎 築山 崇 川地亜弥子 倉本頼一 下田正義 原田 久 中須賀ツギ子 倉原悠一 浅井定雄 中西 潔 大平 勲 相模光弘 得丸浩一 佐古田博