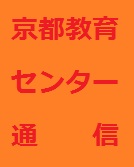
 |
�����s����Z���^�[�ʐM�@ ������V�T �@�i�Q�O�P�R�D�T�D�P�O���s�j |
�S�E�Q�W�u�匠�̓��v�̗��j�F���������Ȃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���s����Z���^�[�@�����@���T
�@�S��28���A���{��Ấu�匠�E���ێЉ�A���L�O���鎮�T�v���J�Â����B�u���a���̔����ɂ��䂪���̊��S�Ȏ匠�E���ێЉ�A60�N�̐ߖڂ��L�O�v����Ƃ����B��Q�����̑Γ��u�a���i�T���t�����V�X�R���a���j��1951�N�X���W���ɒ���A���������̂����N�S��28���ł������B���{���t�͂��̓��������āu���S�Ȏ匠�v�̓��Ƃ��ċL�O�E��j���悤�Ƃ����̂ł���B����ɑ��āA���̓��ȍ~���A�����J�̎{�������ɒu����A1972�N�ɖ{�y���A�����Ƃ͂������Ȃ��ČR��n�����������Ă��鉫�ꂩ��R�c�̐����������Ă���B
�@�|���āA����ɂƂǂ܂炸���݂̓��{���匠�̐������Ă��Ȃ��Ƃ�����ł��낤���B�S��28���ɂ͍u�a���ƂƂ��ɓ��Ĉ��S�ۏ���i�����ہj�E���čs������i���Ēn�ʋ���̑O�g�j���������Ă���B�b��̋ߊ��A�O�������w���Ēn�ʋ������x�i�n���Ёj�͕ČR��n�̎��R�g�p�A���{�S�y�̕ČR�́u���ݓI��n�v���Ƃ��������I�ȓ��e���������ނ��߂̗v���s������ł���A���̂��߂Ɉ��ۏ����A���ۏ������荞�܂��邽�߂̏��u�a���ɐ��荞�܂�Ă���i��U���j���Ƃ�����ǂ��w�E���Ă���B
�@�O�N�X���̍u�a���̌��ƒ���A�����e�ɂ��Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��傫�Ȗ�肪����B�u�a�����߂����ẮA���������Ƃ̂ݍu�a���鑁���u�a�i�P�ƍu�a�j�_�ƁA���{���푈�E�A���n�x�z�����S�Ă̍��ƍu�a����S�ʍu�a�_�Ƃ����_����Ă����ɂ�������炸�A�����̋g�c�͒P�ƍu�a�ɓ��ݐ����B���̂��ߎЉ��`�����̈ꕔ�͏����ɉ������A�܂��͒�������ۂ������A���{�̍ő�̐푈��Q�������ؐl�����a���E���ؖ����͏�����������Ȃ������B���{�̐A���n���������N�����̊؍��Ƌ��a�����ΏۂƂȂ�Ȃ������B����ɍu�a����Q���ɓ��{�̗̓y�̕�������߂�ꂽ���A���̓��{�̗̓y�ɂ��Ă̓J�C���錾�ɂ��ƂÂ����̂ƃ|�c�_���錾�ɂ���ɂ�������炸�A�瓇���\�A�Ɉ����n�������^����̓��e�����荞�܂ꂽ�B����͍����̐푈�ɂ��̓y�̊g��A�s���ȗ̓y�ύX��ے肵���吼�m���́E�A�����錾�ɔ�������̂ł���B�܂��u�a�ΏۂƂȂ�Ȃ������؍��Ɋւ��ẮA���{�����N�ɑ��ĕ�������̓y�̍��ڂ���|���i�Ɠ��j���ŏI�I�ɂ͂�����ĞB���ƂȂ������Ƃ��痛���Ӄ��C���ݒ�Ƃ������d��������A�����̒|���E�Ɠ����̉Ύ���c�����B��t�����͓쐼�����i����j�ƂƂ��ɃA�����J�̎{�������ɂ��������A1972�N�̉���̖{�y���A�ɍۂ������O���Ȃ����t�����i�ދ����j�̗̗L������������A���N�̓������𐳏퉻���ł͗̓y���ɂ��Ă͌����ɂ��I�グ�Ƃ���邱�ƂƂȂ����B�����k���̓y�A�|���A��t�����Ƃ��������{��������̓y���̉Ύ�́A���{�̐푈�ӔC�E��㏈����B���ɕt�����T���t�����V�X�R���a���̒�����e�A�P�ƍu�a�ɖ�肪�������Ƃ����ĉߌ��ł͂Ȃ��B
�@�����}�̑I������ł͎��̂Q�E11�u�����L�O�̓��v�̍��Ǝ��T���J�Â���Ƃ��Ă���B�S�E28�u�匠�v�Ƃ͓��{�̐푈�ӔC�E��㏈���𖢂��ɞB���ɂ������j�F���̌���ł���B�Q�E11�s���F�ƂƂ��ɂ��̓�����j���������Ă����^���̂��������Ƃ��Ă��������B
�Q�O�P�Q�N���s�����u���a�E���ۘA�сv���ȉ��
�������S�A�݂����̂̎����A�`���������Ɏv�����āA����̂炵�����a��a��
�|�ӂ肻�ł̏����u�݂炢����v�Q�N�ڂ̂Ƃ肭�݁|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V���@�v���q�i���O�x���w�Z�j
�P�@�͂��߂�
�@���a���炪�w�Z����Ŏ��g�ނ��Ƃ�����Ȃ�A�q�ǂ��B�͂��Ƃ��A���a������������Ă��Ȃ��搶�B�����d�ɂ��悤�ɂȂ��Ă��Ă���B�����������A���s�̖k���ɂ����āA���N�u�ӂ肻�ł̏�����������v�𒆐S�ɕ��a�����𑱂��Ă�����y�̐搶���ƈꏏ�Ɋ������邱�ƂɂȂ������́A�������炱���A�����������̍��̒n���Ȋ����̈Ӌ`�������Ă���B
�@�u�ӂ肻�ł̏������������v�����P�T���N���@�ɔ��������A���Z�����a�T�[�N���u�݂炢����v�B�Q�N�@�@�ڂɂȂ������Z���̂Ƃ肭�݂́A�������Ƃ��������肵���v���łƂ肭�ނ悤�ɂȂ��Ă��āA���Z���̒�͂������܂����B
�@����̃��|�[�g�́A���̂P�N�Ԃ̕��݂��ӂ肩�����āA���̈Ӌ`���m���߂Ă��������Ǝv���܂��B
�Q�@�P�N�Ԃ̂Ƃ肭��
�i�P�j�S�����E����n��̐푈��Ղ�T��
�@���m�R������w�Z��̂����͑�ォ��̊w���a�J�̎��ꂳ���������B�������a�̑�����ێ����悤�Ƃ��Ă���N�y�̐l�����̑z���ɂӂ��Ɗ�悵���B���w���̎Q��������A���̌�A��ɓ��芈�܂��B
�i�Q�j�T�����E�����v����l����
�@�V�������Ԃ��}���A���N�x�̊������l�����B��N�̒���s���Ŋ����������̑̌�����������y���Z���B���N���������֎~���E���i�L���j�ɎQ���������Ƃ������ƂɂȂ����B�����āA�L���ɂ����Ȃ�A������x�A���c�W����̘b�����Ƃ������ƂɂȂ����B
�i�R�j�U�����E���c�W����̔픚�̌���
�@�L�������Ŕ픚���ꂽ���m�R�s�ݏZ�̈��c�W���炻�̔픚�̌��������������B���c����͎菑���̒n�}���L���p�ӂ���Ă��āA�������g���Č�����������̗l�q�A�����ȍ~�L���̏Ė쌴��������̌������A���ɘb���ꂽ�B�픚�҂̑̌��k�́A�͂��߂Ă̐��k������^���ɕ��������Ă����B����ɂ�������炸�A��������b�����p����u�Ⴂ�l�ɓ`�������v�Ƃ����v�����Ђ��Ђ��Ɠ`������B
�i�S�j�V�����E���q����i3��j
�@�������E���ɍs�����Ƃ����߂��݂�Ȃ́A��N�̑̌������ƂɎ��������Ŏd���S���A�Ă��ς��Ƃ����߂Ă������B
�E���q�@���������̌��ӂ�A��N�x����̊����L�^��O��̒���E�������E���̊��z�Ȃǂ��̂����B
�E�J���p�̑i���̕��͂���
�E�J���p�̑i���E�E�e�c�̂̏W�܂�ɐϋɓI�ɕ��S���đi����B�ۈ牀�̉čՂ�ł͗��߂ŎQ���B
�i�T�j�W�����E�������֎~���E���Q���E���n�t�B�[���h���[�N
�@�L�����������̓��Ɨ����Ɉ��c�������ꂽ�ł��낤����������ƂɌ��߁A���O�̊w�K�Ƃ��Ă������K�₵�A�ŏI�I�ɕ����R�[�X�Ƃ��̎��ӂ̌�����������̔픚���m�F�����B
���̊w�K��ɂ͂S�̐V���Ђ���ނ����Ă��ꂽ�B
�ȉ��@�`�D�͎�ɕ������n�_�Ɠ��e�B
�@ �L���O�H���D�� �W���U���w�k�����̓�����
�W���U���ɔ픚���ꂽ�ꏊ�B�K���قƂ�Ǖ����͂��ꂸ�A�ߌ�ɋ{���̏h�ɂ֖߂���B���D���ł͐l�ԋ����̐����Ɍg���B���ɂ͓��点�Ă��炦���B
�A�]�g�̊C �W���V�����{��͌�(�]�g)�̊C�ł͎��̂�������ł����B�݂�ȐÂ��ɂȂ��Č��߂Ă����B
�B�]�g�R���̘e�� �L���̊X���p�ЂƂȂ��Ă���̂�����ꂽ�ꏊ�B���Ƃ̍ד���������B
�C�Z�g���E������ �����炭�W���V���ɓn��ꂽ�Ǝv���Ă��鋴�B���̂������s�����Ă������B
�D�L�������t�͊w�Z �����ݐЂ��Ă���ꂽ�w�Z�B
�����̃q���V�}�c�A�[�ł̓��e
�@�@�E�e�o�X�ɏ�荞��ŃJ���p�̑i��������B
�@�@�E�픚���ō��ꂽ�q�ǂ����̈ԗ�ՎQ���E�M�d�ŁA�ߎS�Ȕ픚�̌����B
�@�@�E�S�����Z�����a�W��ւ̎Q���E�����A��
(�U)�X�����E�����푈�W�E���m�R�푈�W�ł̕�
�@�q���V�}����A���āA��T�ԂŁu���c����̔픚�R�[�X��������v������͑����ɂ܂Ƃ߁A�����푈�W�A���m�R�푈�W�ŁA���Z���B�����ŕB
�E�����͐�~�L�����h���A�s�[���Ŕ���
�E�Ί��{�����e�B�A�Q���̍��Z���ɑ̌��k���B
�i�V�j10�����E�t�B�[���h���[�N
�E�����̒��E��т�����A���āA���������Ɓu�����w���猴�����l����v���c�搶�i���{�Í��Z�̐搶�j�̘b��
(�W)11�����E���ŋ��Â���A���f������
�@���c����́A�`�������v������A���̐l�ɂ��`�������Ƃ������Z�����A���悢��A���ŋ�����Ƀ`�������W�B��ʂӂ��G�̍\�����݂�Ȃňӌ����o���������B��͂�A�C���[�W������Ƃ���ȕ��ɂȂ�̂��Ɗ��S����قLjӌ�����т������B�܂��A�u�݂炢����v�̉��f���Â���́A���p���̐��k����`���A��Ɏ��ŋ����̑傫�ȗ͂ɂȂ���B
�i�X�j�P�Q�����E���ŋ�����
�@�쐬�������͂����x�������B�u�{���ɈӖ����킩�邩�A�q�ϓI�ȗ���łǂ����v�_�c���[�܂��Ă������B������Ȃ̂ŁA�������̋�ނŁA����͂�ł̉�����B��̕������グ���ς��ƁA�������������̃T�[�N���̈�̊����łĂ����B
�i10�j�P�����E�g�}�g�̌��E���ŋ�����
�@���ŋ��̏d�v�ȃ|�C���g�ɂȂ鈰�c���ӂ邳�ƂɋA���Ă����Ƃ��Ƀg�}�g���E���ꏊ�����c����Ƃ݂�Ȃŕ������B�����ɗ����Ă����킩�邱�Ƃ�����B����́A���c����̂炢�̌�����̂���A�䂪�ƂɁu�A�肽���v�v���������B���̎v�������X�g�̏�ʂɂȂ�A�`���V�ƂȂ����B
�@�X�ɁA���́E�G�̌��������ꂽ�B�u���c����̘b���āA���n������Ă����̂ɁA�����ƃ��A���ɂȂ�Ȃ����ȁ[�B����`���悤�ɂȂ�Ȃ����ȁ[�B�v��������ӌ���������A���������ꂽ�B
�i�P�P�j�Q�E�R�����E���ŋ����
�@���p���̗F�B�ɂ���`���Ă��炢�F�h��J�n�B�����̍��Ԃ��ʂ��āA���͓I�ɂƂ肭�ށB�ӂ肻�ł̏������삵���]�]�v�Ȃ����ŁA�����ۂ̊G�{����̘b�����A�v����Z�@���w�B�����B
�@�n���FM�����̔ԑg�Ƀp�[�\�i���e�B�[�Ƃ��ĎQ�����Z�������ŁA���o���B���X�Ƙb���т�����B
�R�@�܂Ƃ߂ɂ�����
�Ƃ肭�݂̂Ȃ��ŁA�����Ă������Ƃ̑���������܂����B���N�͑̌��������Ƃ����ƂɁA�͑����ɂ܂Ƃ߂Ă݂�Ƃ��A���ŋ�������Ƃ��u�`�ɂ��Ă��������v�ɂ��������Ǝ��g�ގp���݂��܂����B���̌��_�ɂ͊w���Ƃ𑼎҂ɓ`�������A��������̐l�ɒm���Ăق����肢���ӂ����ł����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�����̒��Łu�k�Ђ̃{�����e�B�A�ɂ��������v�ȂǁA��̓I�ȍs���Ɍ��т��鍂�Z�����o�Ă��܂����B���̒��Ԃ��݂āA�����Ɗw�т����Ƃ�������������A���낢��Ȋw�K��ɍL�������B�܂��A���ŋ����ł͊G�̏��Ȑl�A���͂̑g�ݗ��Ă����܂��l�A�c�Ƃ��ꂼ�꓾�ӂȕ��삪��������A�݂���F�ߍ����A�u���ȁ[�v�Ƃق߂������Ƃ�����܂����B���Z�����u�Ŏh���������A���܂��Ă��邱�Ƃ����܂����B
�@����ɁA�m���Ƃ��Ă̏��͑������̂́A�o���̏��Ȃ����Z���ɂƂ��ẮA���ۂɂ��̏�ɗ����ƂŁA���낢�돃���Ɋ����Ă���Ǝv���܂����B���ꂪ�t�B�[���h���[�N�̖��͂Ȃ̂��Ǝv���܂����B
�@�u�����ւ���ƁA�v�킸�A�������܂Ƃ����Ă��܂������B�v�u���ɂ͊w�Z�ɂ͂Ȃ��ʂ̃O���[�v�����肢���������v������ʂ��A���ԓ��m�ւ̈��S������ł���W�c�������Ă��܂��B������������A�����������Ȃ����Z�����ɂȂ��Ă��Ă��錻��̒��ŁA����ȃT�[�N�����ɃT�|�[�g���A��������̍��Z�����}�����ꂽ���Ƃ����܂��B���������Z���O�N���͎Ɍ����āA�������T���Ă����܂��B���̓_�ł́A��N���ɂ�����������Ă��Ă��炤�Ƃ肭�݂��l���Ă����Ȃ���Ɩ͍����ł��B
�@�����āA�T�|�[�g���鎄�B����ϖZ�����ł����A�݂��̗ǂ����o�������Ȃ���A���̒n��ɂ��镽�a�̍��Y�����āA�n���Ɋy������������悤����������܂��B�i2012���s�������ȉ��蔲���j�i�NjL�j3��31���ɁA�����������ŋ��̂̕ǂ����A���m�R�s�E�����s�̌㉇�āA�L���Ăт����A�J�Âł��܂����B
�Ǘ��Ƌ����̋���ɍR���āA�q�ǂ��̖L���Ȕ��B��ۏႷ�鋳����I
�\�Q�O�P�R�N�x�̋��s����Z���^�[�̊��������\
�P�D�i�P�j��{����
�@�E�V���R��`�ƕ��ÓI����ςɂ�铝���I����ɍR���āu�q�ǂ��_�v�����ɁA���ׂĂ̎q�ǂ��B�̖L���Ȕ��B��ۏႷ�鋳�犈���⋳����H�����ꋳ�E���Ƃ̘A�g�����߁A���y�ɓw�߂�B
�@�E��ÁE��������Ƃ̘A�g��T��A�n��ɂ�����w�Z�̂������ƂƂ��ɒT������B
�i�Q�j�����̏d�_
�@�E���{�̋���Đ��A�����ېV�̉�̓����ɒ������A�{���̋���̂������T�����A�L�߂�B
�\����ψ���x�A�������狳�Ș_�Ȃǁ[
�@�E�����߁E�̔��A���B��Q�Ȃǎq�ǂ��̔��B�Ɋւ���Ďq�ǂ��̐l�i�`����̉ۑ��T������B
�@�E���s�w�K�w���v�́A���ȏ��̖��_�A�w�̓e�X�g�̐��������A����I�Ȏ��H������B
�@�E�n��ł̎q��ĉ^���ƂƂ��ɍ����̊w�Z�̂������E���E���ƂƂ��ɍl���A�������L���A�ۑ��T��B�@�@�@�@�@�@�@�\���Z����A�w�Z���p���A�������A�y�j���ƂȂǁ[
�@�E�����̎�������A�������Ǝq�ǂ��̈炿�Ƌ���̂���悤��������
�E���t�̒m���I�Ɍ������{���̂������������B
�Q�D�Z���^�[�̐�
| �E��\�F�쒆���@ �E�����ψ����F�������T�@ �E�����ǒ��F�{�c�v���q�@ �E�����ǁ@���c���` �E�^�c�ψ��i��L�܂߂�18�l�j����Y�@�啽�M�@��n����q�@�q���I��@�q�{����@���͌��O�@�������j�@���_����Y�@�z�R���@���{��c�M�q�@�������@���c�v�@���ۍ_��i�דc�r�j�j �E�u�Ђ�v�ҏW�ψ��F����(�ҏW��)�A�q�{�A��n�A�{�c�A���c �EHP�Ǘ��@��� ���@�e��������ǒS�� �@�n���i�t��j�@���w�i�����j�@�w�́i�s��j�@���B�i�啽�j�@�n��i�P��j�@���Z�i���c�j�J�E���Z�����O�i���j�@����i�����j�@��Q���i����j |
���^�c�ψ���@�i��c�j��2�y�j�@�i�w�K��j��4�y�j�@��������ߑO���@�Z���^�[���ɂ�
�R�D�P��̂Ƃ肭��
����44��Z���^�[�����W��@12��21��(�y)�A22��(��)�����Z���^�[
�Z�u�Z���^�[�ʐM�v�̔��s�F����10���@������H�̏Љ��
�Z�@�G�����u�Ђ�v�̔��s�F5���A8���A11���A2���@����ǎҕ�W��
���@����Z���^�[���͕ʊ�2�K�i���E���͂P�O�F�O�O�`�P�U�F�O�O�j
����̗\��
| �w�́E����ے���������J�w�K�� �@�@6��2���i���j�P�R�F�R�O�`�@����301���� �@�@�@�@�@�@�@������H�Ɋw�ԁF�v���V�A���P�N���E���i�\��j ���s����Z���^�[���J�w�K��@�u���{�����̋�����v�̂䂭���v �@�@�@�@�@6��16���i���j13:30�`�@�@�����Z���^�[103���� �@�@�@�@�@�u�t�@�Έ�@�i���m�����w�y�����j |