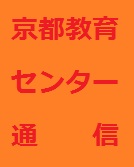 |
|
||
| |
今、再び「教え子を戦場に送るまい!」 藤原ひろ子 (名もなく貧しく心美しい年よりたちの語らいの会・元衆議院議員) |
||
私、藤原ひろ子は今、85歳。 78年前、尋常小学校一年生に入学しました。国語読本を開くと、片仮名で「サイタ サイタ サクラガ サイタ」そして、2頁にわたって満開の櫻の花が描かれていました。担任の辻茂先生は「お前たちは幸せだぞ!さくらの花は天然色だ!」と叫ばれました。 これは、文部省国定教科書が、日本で初めて色刷りになり、カラーの本を手に子どもの前に立った教師の感動の言葉です。続けて先生は「櫻の花は日本の国華だ!パッと咲いてパッと散る!散りぎわグズグズしてはならないっ!」と声をはりあげられました。 次のページは、「ススメ ススメ ヘイタイ ススメ」。その次は、「ヒノマルノハタ バンザイ バンザイ」でした。 櫻の花と兵隊とそして日の丸がセットの教育。日の丸は、忠節を意味していたのです。 この教科書で、「兵隊さんだけでなく日本国民は、天皇のために櫻の花のようにパッと咲いてパッと散る。死に際グズグズしてはならない。潔く死ぬことが美しいのだ」と骨の髄まで叩き込まれました。 修身の教科書は第1ページに、軍隊の最高統帥者である大元帥、即ち天皇が白馬にまたがる勇姿が描かれておりました。 このように、私の小学校入学(1933年)以降は、天皇を絶対とする軍国主義教育が強められていったのです。そしてこの時、日本が中国への侵略戦争を拡大していった時期と一致するのです。 教科書に、昔話や神話を載せて戦意高揚に利用した。これが当時の日本の教育方針でありました。このもとで私は、どんな子どもに育っていったのでしょうか。 「日本ヨイ国 神ノ国」「天皇陛下ハ生神様」これがお腹の底まで浸みわたり、信じてやまない人間になっておりました。 戦争が激しくなった小学四年生の時。 「今、日本は武器を造るのに鉄が足らない。家じゅう捜して鉄製品を供出しなさい」「お国のため、天皇陛下のオンタメです」と教室で先生がおっしゃいました。私は、「そうだ!内には大きな鉄瓶がある。あれで大きな大砲の弾丸ができる!」と飛んで家に帰り、胸躍らせて父に訴えました。ところがなんと父は、私のスキを狙って鉄瓶をそっと押入に隠しました。それをめざとく見つけた私は、「お父さん!非国民!」と指さし怒鳴りつけました。「非国民」とは「国民にあらず」「天皇陛下の赤子(せきし)ではない」という戦争中、他人を非難する最大級の罵りの言葉です。父は、何とも言えない悲しそうな顔で黙り込んでおりました。今、父亡き後69年目。私はあの顔を忘れることができません。喘息病みの父は、私の小学校入学一年前に台湾総督府の勤務を退職し、家族と共に日本に引き揚げてきたのです。そして、冬といわず夏といわず座敷の障子を閉め切り、大きな火鉢に鉄瓶をかけチンチンとお湯を湧かし、喉を潤し咳を押さえておりました。気分のよいときは、乾いた布で鉄瓶をピカピカに磨いておりました。これが毎日の我が家の光景でありました。父は、「お国のために」と自ら金歯を供出した人です。それなのに鉄瓶は押入に隠した……。思えば、鉄瓶は父の命を守る最後の道具だったのです。しかし、軍国主義ガリガリ亡者の娘にはそんなことは通じない。「ホシガリマセン、勝ツマデハ」を信じ込んでいる私は、病身の父の心情ばかりか、他人様の心などとても理解できない人間に育ってしまっていたのです。 これが当時、私だけでなく日本国民の中に、数限りなく重ねられながら侵略戦争は300万人という尊い犠牲をつくり出したのです。真実を正面から教えない教育が、どんなに歪んだ人間をつくり出すのか。誠に教育は恐ろしいものです。 1939年、私が女学生になると、支那事変から太平洋戦争へとますます戦争は広がりました。高等女学校三年生になると英語の授業は無し。「鬼畜米英(きちくべいえい)(鬼、畜生のアメリカ、イギリス)、こんな国の言葉を学ぶ必要はない!」というお上の教育方針で英語は廃止。そして、授業は勤労奉仕で嵐山へ草引き。果ては、山城南部の「祝園(ほうぞの)」まで動員されて、兵隊さんの下着の洗濯や繕い物など。更には、女子挺身隊が組織され軍需工場へ動員。当時の学力不足の人間は、こうしてつくられたものです。しかし、私たちは、どれを「一億一心、火の玉だ!」と思いこみ、なんの不思議も矛盾も感じない人間に仕立て上げられてしまっておりました。 こうして、日本のファシズム体制は、思想を統制し、国民を画一的に組織する支配体制をつくりあげていったのです。 女学校五年生三学期は、女学生生活最後です。しかし、私は10人だけの友人と共に臨時教員を養成する女子師範学校に通わされました。 そして、たった三ヶ月の講習で小学校教員に。京都市から「四月より翔鸞小学校助教を命ず。月俸40円」と書かれたハガキが届き、二年生50人の担任教師となりました。授業中、「ウーッ、ウーッ」と空襲警報のサイレンが鳴ると授業は直ちにストップ。子ども全員に綿入りの防空頭巾をかぶらせ、教室の後ろの床を上げて地下防空壕に50人を押し込め、薄暗い中で警報解除をじーっと待つという日々が続きました。それでも私は、子ども達の笑顔に生きがいを持つ毎日でしたが、それも束の間。 翌年の四月には、激しくなる本土空襲を避けるためにと、学童疎開付添い教員となり、京都の北端、丹後山田、石川村で暮らしました。児童は3年生から6年生までの150人。付添い教員は40歳代の男子教員が一人。あとは私と同じ20歳代の女性。私も児童30人の寮の責任者になり、山の中腹にある「だるま寺」で名高い「福寿寺」で2人の寮母さんと共に生活しました。昼間はかがとのすり減ったわら草履姿の子ども達と坂を下りて石川小学校の4年生の担任。勤務を終え、子どもと一緒にお寺に帰ると、もう勉強どころではありません。毎日の食糧確保。頭髪や衣類にとめどなく湧くシラミ退治。夜中には、蹴飛ばした布団を掛けて回る仕事。これは、お薬など一切ないのが戦争中。ですから夜の見回りは寝冷え、風邪の予防などにはなくてはならない夜の仕事なのです。子ども達は、夕飯が済みあたりが暗くなると襖の影で「家に帰りたい」とシクシク泣き出します。私も一緒に泣きたい思いでした。 ある晩、夜中の見回りの時、6年生の古川君の布団が空っぽでした。「おしっこかな?」とお便所を覗きました。古川君はおりません。お寺の本堂まで走り、仏さんの押入れもみんな開けて捜しましたがおりません。お寺中走り回りましたがおりません。「はっ!」と思って私は、提灯を手に外へ飛び出しました。ああ!やっぱり……。古川君は、山をくだり鉄道の線路に沿って歩き続けておりました。「汽車に乗ってきたのだから、この線路を反対向いて歩いて行けば、お母ちゃんに逢える!」と考えたのです。月の明るい晩でした。線路の向こうの方に黒い影が動いています。「古川くーん!」私は叫びました。「古川くーん!」2回叫ぶと、その影がこっちへ走ってきました。そして、黒い影は泣きながら「先生!」と飛びついてきました。お母ちゃんに逢いたい!の一心でひたすら歩き続けていた古川君。私は古川君を抱きしめ、古川君と同じ思いで一緒に泣きました。銀色に鈍く光るあの鉄道線路。私は今でも脳裏に焼き付いて離れない光景です。子ども達をこんな目にあわせたくありません。 当時、天皇のために死ぬこと以外の生き方を教えてもらわなかった私たちは、教育と祖国の崩壊を阻止できなかったばかりか、戦争を草の根で支える人間に仕立て上げられてしまっていたのです。 しかし、私は思います。人間は必ず変革します。 1945年、敗戦。新憲法と教育基本法で私たちは天皇制教育の呪縛から解放されました。日教組は「教え子を再び戦場に送るな」の運動をすすめ、私も京都教職員組合の一員として、平和と民主教育を守り育てる運動の中で、仲間と腕を組む大切さを学び、教育労働者として育てられました。とりわけ、京都教育センターの民主教育三原則は、今日もなお私の支えとなっています。それは、①全面発達…人間の能力、人格の全ての側面での全面発達をめざす。②科学的認識…自然・社会・人間について正しい認識をもち、労働や生産の大切さをよく身につけ、それらを人間の幸福のために役立てる力。③集団主義…「ひとりはみんあのために、みんなはひとりのために」真理・真実を貫き、問題をみんなで考え行動していく力。この三原則をもとに職場や地域で、子どもを真ん中に父母と教師が対等平等の立場で話し合い、考え合い、実践を重ねる民主教育に専念する人間に変革していきました。私は、どんな困難をも乗り越えて、教育を二度と再び「不当な支配に服することなく」発展させるために、力を寄せ合うことが重要だと考えます しかしながら今日、労働者階級が労働組合に結集してたたかいに立ち上がることを抑えつける「新自由主義」の影響が、教育の分野にも非常に大きく及んできています。低賃金、無権利のパートや派遣など、非正規雇用は、民間大企業はもとより自治体や学校の職場にも急速に広がり、人間らしい労働のあり方が壊されているのです。何ということでしょうか。これは、政府、財界、大企業が一体となって推進する労働政策です。これをどうしてもはね返さなければなりません。 今、日本は歴史の転換点に立っています。一体、どんな日本につくりかえればよいのでしょうか。私は先ず、私が体験した侵略戦争について、政治がきちんと反省し、この根っこを断ち切ることが大切だと考えています。二つ目には、日本は、政治も経済もすべてアメリカの言いなりです。ここを抜け出し、自主的で主体性を土台とした日本につくりかえなければならないと思います。三つ目には、日本は経済大国になりましたが、その成果は大企業独り占め。汗水流した労働者や国民はそっちのけで格差や貧困が広がっています。経済力の成果は、公平に還元する当たり前の日本を建設することが重要です。 「主権者は どこにいるのか 国の春」 これは、元京都府知事、蜷川虎三さんの俳句です。 今日、またまた、日本は危険な方向が伺われます。「侵略戦争などというのはヌレギヌだ!」と暴言を吐いてクビになった田母神(たもがみ)空幕長。なんとこの人が「憲法を変えよう」と全国を講演して廻り、テレビにまで出て「自衛隊をアメリカと一緒に戦争できる軍隊にしよう!」と叫んでいます。危険です。そして、民主党も自民党も、憲法改正を叫んでいます。危険です。しかし一方、新しい政治を強く大きく求める国民のたたかいが日本中で湧き起こっています。日本国民は、たたかいの中で変革し大きく成長しています。今日本は、大震災と原発事故という危機のさなかにありますが、みんなで手を繋ぎ合いこれを乗り越えれば、行く手には新しい日本をつくりあげることができると確信します。 私たちは、ここに自覚と自信をもち全体を見る広い眼(まなこ)と、高く深い志をもって、憲法九条を守り、核も基地もない日本を築こうではありませんか。 私も、もう二度と騙されない人間に成長して、生き続けてまいります。 (2011年8月記す) |
民主府政「落城」後、30余年の「京都の教育」を検証 ★京都教育センター編『風雨強けれど 光り輝く 検証!京都の民主教育1978~2010』 「風雨強けれど 光り輝く」は、民主府政「落城」の1978年以来30余年間の京都の教育の変遷をまとめたもの。厳しい攻撃が相次いでいたが、「やられっぱなしではない!」この間のたたかいをまとめました。8人の編集委員〔野中一也・大平勲・小野英喜・中西潔・磯崎三郎・高橋明裕・松尾隆司・西條昭男〕が昨年の9月以来合宿を含め14回の編集会議を重ねて刊行しました。この間のたたかいの中にみなさん方の足跡が反映されています。是非、手にとってお読み下さい。 |
季刊『ひろば』の人気連載から37編を厳選・加筆 ★早川幸生著『京都歴史たまてばこ』 「京都歴史たまてばこ」は早川幸生さんがこの間『ひろば』に連載された中から37編を加筆編纂されたものを集めたものです。調べ歩いた京都の風物詩に引き込まれること請け合いです。 |
*2011年1月から、京教組各支部書記局で求めることができます。 *また、申し込み用紙(PDF版)にご記入いただいて、ファックスでお申し込みいただくこともできます。 |
| 京都教育センターホームページにアクセスを http://www.kyoto-kyoiku.com 検索「京都教育センター」 京都教育センター事務局や公開研究会の活動をはじめ、センター通信、季刊「ひろば・京都の教育」、教育センター年報、研究集会、教育基本法に関する様々な資料など、多彩な情報を提供しています。 |
