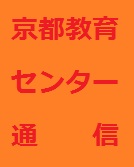 |
|
||
| |
「子どもの権利条約」と日本の子ども 本田久美子(京都教育センター) |
||
「子どもの権利条約」は、1989年11月に国連で採択され、1994年4月に日本は批准し、5月に条約が発効しています。この条約を批准した国は、批准した年から2年後に、その後は5年ごとに国連子どもの権利委員会へ子どもの状況などを報告することが義務付けられています。第3回日本政府報告書に対する審査は2010年5月27,28日に行われ、6月11日に最終所見が採択されました。 最終所見の主な特徴は、 まず第1に、前回の第2回報告書に対する勧告の大部分が実施されていないか、まったく取り組まれていないことに遺憾の念を表明し、重ねて勧告しています。 第2に、子どもに関する予算の貧困さを指摘しています。近年の経済危機のもとで貧困が増加し、子どもの幸福および発達のための補助金および手当がそれに対応して増加していないことを深く懸念しています。そして、子どもの権利の視点から中央と自治体レベルでの予算を精査することを勧告しています。2011年度政府予算は総額92兆4116億円、文部科学省予算は5兆5428億円で、政府予算全体に対して文部科学省予算はわずか6%で大変不十分です。これらのことが2011年度4月から小学校1.2年生からの35人学級を進めようとしたにもかかわらず、小学校1年生からだけの実施となったり、高校生の給付制奨学金については実現されなかったりしています。 第3に、教育制度の崩壊を指摘しています。学校および大学の入学をめぐって競争する子どもの数が減少しているにもかかわらず、過度な競争への不満が増加し続けていることを懸念しています。また高度に競争主義的な学校環境が、就学年齢にある子どもの間のいじめ、精神的障害、不登校・登校拒否、中退および自殺の原因となることの懸念も示しています。そして過度に競争主義的な環境が生み出す否定的な結果を避けることを目的として、大学を含む学校システム全体を見直すことを勧告しています。これまでの勧告より一歩踏み込んで、学校制度自体を見直すことを勧告したのは今回が初めてです。日本の教育が過度に競争的になり子どもたちが発達のゆがみをきたしていることは1998年の第1回最終所見で勧告されていることで周知のとおりです。これがさらに政府が推し進める新自由主義的教育改革により拍車をかけています。2006年12月教育基本法が改悪され、その具体化である教育関連3法の改悪、学習指導要領の改訂、全国一斉学力テストの実施により、さらに競争を激化させています。 第4に、家庭環境の崩壊を指摘しています。親子関係の崩壊が、子どもの情緒的および心理的幸福度に否定的な影響を与えるとともに、子どもの施設入居までも引き起こしていることを懸念しています。さらに親が子どもに不適切に期待をかけていることにより、子どもが家庭において暴力の危険性にさらされていることにも懸念を表明しています。児童相談所が対応した児童虐待件数は年々増加しつづけ、2009年度4万4210件で過去最高を更新しています。しつけや指導の名のもとに暴力により子どもを親や社会の価値観に従わせようとする考え方事態を転換することが大切です。 子どもの権利条約および第3回政府報告書に対する最終所見にてらして、日本の子どもの置かれている状況を見てみると大変深刻です。子どもを子どもとして尊重し、豊かな成長・発達を保障していくためには、日本の社会のあり方、経済のあり方が、まず問われます。日本政府は第3回最終所見を真摯に受け止め、子どもを社会で育てる視点での施策が何より大切です。6月11日には、子どもの権利をいかす(DCI)京都セクションが立ち上がりました。私たち自身が、子どもの権利条約をいかしたとりくみを多くの方々と進めていくことが重要です。 |
|||
| 地域と共に生きる教師!ここにあり!―「吉田武彦実践」に学ぶ |
|||
| |
◎報告内容はセンター通信次号で詳しく紹介しますが、吉田先生の足跡は次のようにまとめられました。 ○ 周山中では:サッカー部OBを集めて「京北蹴球団」を結成。地域をサッカーの町にと10年間。 ○ 和知中では:近畿青年洋上大学に参加し中国留学生を招待。同和地域加配として発達の観点で実践。 ○ 綾部中では:「ふりそでの少女像」建立運動に参画、丹波地域の戦争関連遺構探索や舞鶴朝鮮学校との生徒会交流。 ○ 東綾中では:地域の中高生の組織「楽学塾」を結成し、「口上林地域マップ」を作成し全戸配布。地域の伝統的なまつりに中高生と共に参画。舞鶴朝鮮学校と6年間相互訪問。 ※ 当時の実践をまとめた出版物 『水源の里 綾部で文化を紡ぐ』 (かもがわ出版¥1500) センターまで ○ 日新中では:管理統制の強い職場にあっても「ゴーヤの栽培」で地域朝市と交流し、冬の「鮭のとりくみ」にも発展。夏休みの社会科課題で地域聞き取りを課し「地域まるごと博物館」で発表。(地元新聞などで話題に)。押し付けの「キャリア教育」に抗した地域の著名人による「ワクワク講座」での進路学習実践。 ○ 川口中では(今春から):ナガサキ修学旅行に初めてとりくみ、校区全体から折り鶴回収。
|
||
| |
|||
| |
「つくる会」系の歴史・公民教科書を採択させるな! 予断を許さない京都市などでの動きーー教育委員に「不採択」の声を届けよう。 |
||
| 来春から中学校で使われる教科書の採択が7〜8月の教育委員会で決定されます。現場からも選定委員が選ばれ現在選定作業の最終段階かと思われますが、誰がどのような手続きで決められたかは不明です。最多の修正意見がつけられ年表資料などを他社から「盗作」した「自由社」や「育鵬社」の歴史・公民教科書が「検定合格」しています。侵略戦争を美化し天皇賛美のこれらの教科書は「まさか選ばれないだろう」というのがこれまでの常識でした。しかし、今回の採択にあたっては、新教育基本法や学習指導要領で「伝統と文化」が強調された新たな事態のもとで、「つくる会」系が京都市を横浜市などと共に採択可能な重点地域として激しく「攻勢」してきている危険な動きが際立っており予断は許しません。市議会などでも「つくる会」系の請願を採択しており、彼らの学習会に参加した自民党議員が議会で再三にわたって「採択せよ」と教委に執拗に迫っています。こうした緊急事態を受けて教組、教科書ネット、教育センターなどが参加する「連絡会」は「6・25シンポ」の成功を受け残された一ヶ月で、教育委員への「採択するな」のハガキ要請、署名、街宣・デモなどに全力挙げることを決めています。 |
民主府政「落城」後、30余年の「京都の教育」を検証 ★京都教育センター編『風雨強けれど 光り輝く 検証!京都の民主教育1978〜2010』 「風雨強けれど 光り輝く」は、民主府政「落城」の1978年以来30余年間の京都の教育の変遷をまとめたもの。厳しい攻撃が相次いでいたが、「やられっぱなしではない!」この間のたたかいをまとめました。8人の編集委員〔野中一也・大平勲・小野英喜・中西潔・磯崎三郎・高橋明裕・松尾隆司・西條昭男〕が昨年の9月以来合宿を含め14回の編集会議を重ねて刊行しました。この間のたたかいの中にみなさん方の足跡が反映されています。是非、手にとってお読み下さい。 |
季刊『ひろば』の人気連載から37編を厳選・加筆 ★早川幸生著『京都歴史たまてばこ』 「京都歴史たまてばこ」は早川幸生さんがこの間『ひろば』に連載された中から37編を加筆編纂されたものを集めたものです。調べ歩いた京都の風物詩に引き込まれること請け合いです。 |
*2011年1月から、京教組各支部書記局で求めることができます。 *また、申し込み用紙(PDF版)にご記入いただいて、ファックスでお申し込みいただくこともできます。 |
| 京都教育センターホームページにアクセスを http://www.kyoto-kyoiku.com 検索「京都教育センター」 京都教育センター事務局や公開研究会の活動をはじめ、センター通信、季刊「ひろば・京都の教育」、教育センター年報、研究集会、教育基本法に関する様々な資料など、多彩な情報を提供しています。 |
