 |
●京都教育センター通信 復刊第52号 (2011.3.10発行) |
――今、文学の力を借りたい!――
藤原義隆(京都教育センター 学力研究会)
1959年、別府で開かれた全国教育研究集会での末川博さんの記念講演はこの言葉で始まりました。「そこに教育の使命がある!」と明快で、会場は興奮の渦が広がりました。 私は「父母との連携」分科会のレポーターとして参加、私のクラスからも親が2人参加してくれました。記念講演の演題は「教育の壁」。当時の新聞連載で大きい評価を受けた石川達三「人間の壁」に因んだものです。文学が教育論の前提になって力強い内容の講演になりました。 私を送り出した御室小分会は、組合員70人余、半数以上が青年部という活溌な組織でした。47年基本法は「理想の実現は根本において教育の力にまつべきものである」と憲法との一体性を説いています。ところが憲法は発布の翌年、米副大統領が「日本に平和憲法を与えたのはまちがいであった」と嘆き、日本の民主主義は苦難の門出を余儀なくされます。旭丘中学事件もそういう中ででっち上げられました。私は動員に参加して「右翼が全国から来ているのはなぜだろう?」と疑問を持ったことが学習の原点でした。 やがて「池田・ロバートソン会談」が締結され日本は右へ右へと寄っていきました。そんな中で、まるで「エアーポケット」のように、私の水道方式の授業に300人が集まり、校長と教組委員長が揃って"水道方式礼讃のあいさつをする"という未曾有のことが起こりました。 問題はその後です。大橋俊有教育長名で「水道方式禁止通達」が出されたのです。教基法10条違反、新聞もこれまた未曾有のこととして報道、今に至るも完全には撤回されていません。燎原の火のように広がり始めていた実践は瞬時に"鎮火"、私たちはサークルの地下茎で守らざるを得ませんでした。 こういう力関係、緊張感は今も続いているし、教育内容と運動を発展させるキーポイントだと言ってよいでしょう。中学校を退職した名古屋の友人が1年ほど前、「この教育の厳しい時代に、なぜ文学が生まれないのでしょうか?」という大きい宿題を残して帰りました。私は「人間の壁」を再読し、「破戒」「田舎教師」も読みました。100時間ほどかかりました。何れも「国民の切実な期待」という点では共通していましたが、社会的視野の広いのはやはり「人間の壁」。現代にも十分通用します。幸いにも岩波現代文庫に収録されています。(上・中・下3巻、古本が安い)名古屋の友人の指摘は、「新しい教育文学が生まれてもいいじゃないか」という積極的な指摘ではないかと思います。なぜ、新しい文学作品が生まれにくいのか!?私は、親(国民)をモンスターペアレンツという感覚で見るのは正しくないのと、教育という仕事自体に自縄自縛的な要素があるのではないかと「仮説的に」思っています。 退職後20年、介護と自らの病気治療に明け暮れる毎日、同じ先生と呼ばれる医師の献身的な姿に接して、ぼんやりと浮かんだ仮説に域を出ませんが…。 蜷川府政「落城」後30余年をまとめられたセンター刊行の「風雨強けれど光り輝く」に出てくる諸課題を文学作品に"昇華"するのも大切な方法として、国民の目に真実が伝わることを願っています。 |
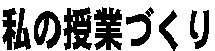
理科 6年「水溶液」の学習
--(全国教研推薦レポートより)--
山口 誠(宇治市立西小倉小学校)
理科の授業作りで大切にしていることは、自然科学の基礎的な事実、法則、概念が学習できるようにすることです。 6年生の水溶液の学習では、教科書ではいきなり酸性雨がでてきます。酸とは何かも分からないうちからの酸性雨です。 酸性は、酸物質が水に溶けてはじめて示す性質です。また、「ものをとかす」ことは、酸水溶液のとても大事な性質です。これは溶解ではなく化学変化です。 酸性雨といいますが、もともと雨水は酸性です。二酸化炭素の溶けたうすい炭酸水だからです。その雨水にさらに硫黄酸化物や窒素酸化物が溶けて酸性が強まり、金属を溶かしたり、植物や動物に悪影響を及ぼすようになったものが酸性雨です。雨水に何らかの物質が溶けて酸性を示すということをきちんと理解できる学習にしたいと考えます。 この単元のねらいを次のように考えました。
次のように指導計画を立てました。
個体の酸を溶かすことから始め、液体の酸、気体の酸と学習を進めました。次に、気体の酸が溶けた塩酸を使って酸水溶液と金属との変化を学習し、酸水溶液の別の性質のあるアルカリ水溶液について学習し、最後に酸性雨について学習しました。 課題に対して自分の考えを持ち、友達の意見を聞いて考えを深めることも大切にしました。本当は、討論できれば良いのですがなかなかそこまでできませんでした。書くことを通して考えを深められるようしました。 例えば、次のような課題では子ども達は次のように考えました。 ○酢酸(液体)は液体です。この酢酸と酢酸を水に溶かした酢酸水溶液とではどちらが働きが強いでしょうか? ア、酢酸 イ、酢酸水溶液 ウ 変わらない ア、酢酸の方が働きが強い ・18人 ・水に溶かすとうすくなる ・うすめない方が酸が強い ・こいままの方が強い ・酸が多い方が良く溶ける イ、酢酸水溶液の方が働きが強い ・6人 ・前の実験でも水に溶かした。 ・割合が多いと反応しにくい (再度予想をとるとアへ3) ウ、変わらない ・1人 ・同じ酢酸が入っているから変わらない、水は関係なさそう。 多数決では正解にたどり着けない、テストの点のよい子の答えが正しいとは限らない経験を通して根拠を持って自分の考えに自信を持ち考えを深められるようになったと思います。 子ども達のノートから、友達の意見を聞いて自分の考えを整理している様子がうかがえます。
教える側が、何を教えたいかそのためにどんな課題を設定し、どう学習計画を組み立てるかをしっかりと考える事が大切だと思っています。また、集団での学習を通して理解を確かなものにしていきたいと思います。 |
||||||||||
| (詳細は、京都教育センター通信52号をごらんください。) |
| ★京都教育センターの活動・2010年度総括 | |
1.設立50周年記念:第41回京都教育センター研究集会 設立50周年記念集会として12月25日〈ルビノ堀川〉~26日〈教文センター〉の二日間開催。 「設立50年の教育理念を今日に生かして!」をテーマにして、全体集会では、民主教育研究所前代表の堀尾輝久氏をお迎えし、野中一也氏、築山崇氏の3氏による「戦後教育を検証し、今日の教育課題と展望を語る」鼎談を開催しました。引き続くパネルトークでは現職教職員が「現代を生きる教師」としてその苦労と喜びをリアルに語りました。1日目には実質123人、2日目の8つの分科会には121人の参加があり記念集会にふさわしい規模と内容の集会になりました。 2.50周年記念祝賀会 研究集会全体会に引き続き、ルビノ堀川「平安の間」で、歴代のセンター関係者、近畿各地民研、府内教育関係組織、各支部教組などから約100名の参加で盛大に開催されました。 3.公開研究会の開催 事務局が各研究会とリンクして、情勢にマッチしたテーマで12回開催。のべ約250人が参加。 4.教育研究集会などへの参加 第59次京都教育研究集会には共同研究者としてのべ59名が参加。民主教育推進委員会には21人(5/23)、20人(9/11)、28人(11/6)が参加しました。 5.季刊誌「ひろば・京都の教育」の発刊 ・ 162号(5/19) ①子どもの生きづらさ ②健やかに育て、子どもたち-地域で育てる ・ 163号(8/4) ①若い先生の教育実践に学ぶ ②京都の高校入試・高校教育の実態と課題 ・ 164号(11/10)①困難を抱える子どもたちと向き合う教育実践 ②教科書が変わる! ・ 165号(2/14) ①気になる保育の「新システム」 ②子ども・青年の表現文化 6.出版活動 (1)8人の執筆者が1年間12回の編集会議を経て50周年記念出版「風雨強けれど光り輝く」刊行。 (2)「京都教育センター年報23号」を例年通り3月に発行。 (3)2006年5月に復刊した「センター通信」は5年目に入り、今年度も月刊ペースで発行。 (4)早川幸生著「京都歴史たまてばこ」(「ひろば」連載)を出版し、その普及に取り組んだ。 7.研究活動 8つの研究会がそれぞれ独自に研究活動を展開し、年間3回の拡大事務局会議でその報告と交流。 8.H.P.の更新と資料室の整備・活用 2004年1月に開設されたH.P.は浅井定雄氏の編纂で毎週2回更新され、現在4万件を越える閲覧が記録されています。また、関係者の尽力により資料室の整備がすすみ関係者に利用されています。 9.事務局体制 ・事務局会議は(15名構成)は3週間に一回のペースで下記の日程で18回開催され、企画検討会議(月一回)も12回開催されました。 ・代表:野中一也 研究委員長:築山 崇 「ひろば」編集長:西條昭男 事務局長:大平 勲 ――事務局メンバー―― 高垣忠一郎 市川 哲 倉本頼一 高橋明裕 中須賀ツギ子 倉原悠一 浅井定雄 中西潔 東 辰也 得丸浩一 長尾 修 |
|
民主府政「落城」後、30余年の「京都の教育」を検証 ★京都教育センター編『風雨強けれど 光り輝く 検証!京都の民主教育1978~2010』 「風雨強けれど 光り輝く」は、民主府政「落城」の1978年以来30余年間の京都の教育の変遷をまとめたもの。厳しい攻撃が相次いでいたが、「やられっぱなしではない!」この間のたたかいをまとめました。8人の編集委員〔野中一也・大平勲・小野英喜・中西潔・磯崎三郎・高橋明裕・松尾隆司・西條昭男〕が昨年の9月以来合宿を含め14回の編集会議を重ねて刊行しました。この間のたたかいの中にみなさん方の足跡が反映されています。是非、手にとってお読み下さい。 |
|
季刊『ひろば』の人気連載から37編を厳選・加筆 ★早川幸生著『京都歴史たまてばこ』 「京都歴史たまてばこ」は早川幸生さんがこの間『ひろば』に連載された中から37編を加筆編纂されたものを集めたものです。調べ歩いた京都の風物詩に引き込まれること請け合いです。 |
|
*2011年1月から、京教組各支部書記局で求めることができます。 *また、申し込み用紙(PDF版)にご記入いただいて、ファックスでお申し込みいただくこともできます。 |
|
京都教育センターホームページにアクセスを http://www.kyoto-kyoiku.com 検索「京都教育センター」 京都教育センター事務局や公開研究会の活動をはじめ、センター通信、季刊「ひろば・京都の教育」、教育センター年報、研究集会、教育基本法に関する様々な資料など、多彩な情報を提供しています。 |