 |
●京都教育センター通信 復刊第49号 (2010.11.10発行) |
北村 茂(京都退職教職員の会 事務局長)
大阪地検特捜部主任検事が、裁判資料を故意に改ざんして無実の人を罪に陥れようとした恐ろしい事件が起こった。その上、この事実を認識しながら隠ぺいした容疑で、元上司2名も逮捕された。これは、単に一検事の犯罪や大阪地検の失態・隠ぺい体質の問題では済まされない大事件であることは言うまでもない。 郵便料金不正事件の担当検事は、大阪地検評判の"エリート検事"だったということに着目したい。この検事は、想定したストーリーどおりに容疑者を徹底的に追い込めることに長けていたそうである。自白強要や証拠の改ざんをやってのける検事が"エリート"だとすると、検察に対して、国民は不信感だけでなく恐怖感さえ抱かざるを得ない。 このことから転じて、教育の世界でも、やたらと"エリート"というレッテルを貼ったりすることが多い。最近、ノーベル賞がよく話題になるが、「将来ノーベル賞を受けるような逸材を早くからエリート教育をした方がよい。」という意見をまことしやかにに語る人がいる。また、「競争意識がない少人数の学級や学校では、伸びる子も伸びない。」と学校統廃合の理由立てにされたりする。しかし、少人数の学校で、教師が創造的な教育実践や一人ひとりの子どもを大切にした取り組みをしていることに目を向けようとせず、「きれいな校舎になる」「小中一貫で教育効果が上がる」というふれこみで、地域を『納得』させて、強引に学校統廃合を推し進めようとしているのが各地の実態だ。 私が通った京都市のど真ん中の小学校は、今や5つの小学校の統廃合で豪華な校舎になり、学校名も変わっているが、今年の同窓会の席上「市内有数の進学校だと評判だ。」と手柄話のように紹介する友人がいた。私は宴席での発言でもあり、特に問題を指摘しなかったけれど、「公立の小学校までもが進学を競うのか」と苦笑せずには居られなかった。 また、門川京都市長出身の高校は、『○○の奇跡』とまで持ち上げられ、高い大学進学率を誇ることで有名になったが、一昨年、生徒が盗撮事件を起こしていた事実を学校が隠ぺいしていたことが発覚した。"エリート校"という肩書が、不祥事を公表させなったのであろう。 そもそも"エリート"という肩書が、ともすれば、無情にも人間性を損なうことが多いのではないか。成果主義による競争で、ある面で実績を上げた者に与えられ、その人格とは切り離された『称号』であるのかもしれない。 京都市教委は、かつて全教職員対象に研究図書費を支給していたことがあった。しかし、それを全部引き上げ、市教委推薦の教育功労者や学校関係者を表彰する費用に転用した。各校への研究補助金も、各学校の『研究への意欲?』によってランクをつけ、金額に相当の格差をつけて配分するなどして、つねに教師と教師、学校と学校を競わせるように仕組んできた。その中で、"エリート教師"や"エリート学校"がつくられているように思う。 山田洋次監督は、学校シリーズ第1作のパンフレットで、「最近"母校"という言葉が死語になっている。」と述べられている。学力テストで学校間格差を意識づけるような教育改革で、どの子も出身校を"母校"として誇りをもつことができるのだろうか。 子どもと学校・教師との信頼関係や、父母・地域からの温かい視線と支えがあってこそ、子どもたちは、自らの学校や友人に誇りをもつができるのではないだろうか。 |
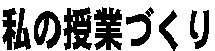
―学力実態を踏まえ、クラス集団での弁証法的展開の試み
久保 斎(京都市立金閣小学校)
●算数授業についての問題意識 その1 ・「算術から算数への原理で授業をつくる」-ゴテゴテした導入は子どもたちを算数嫌いに 子どもたちの算数の学力実態を見てみると、 こんなこともできないのかと唖然とすること があります。算数のレベルはいうに及ばず、 算術のレベルもできていない状態です。 私の授業づくりは「算術から算数へ」とい う取組を、授業のなかで子どもたちといっしょに展開しようというものです。例えば、三角形の面積の学習の場合だと、まず三角形の 面積を有無をいわさず「底辺×高さ÷2」と 教え、「どうだ、発生の術はすごいだろう。ごちやごちやいわずに、やってみろ」と提起す るのです。ここが「算術」です。そして、計算の結果と方眼で調べた結果を比べ、術のすばらしさを確かめさせるのです。そのあとで、子どもたちのなかから「なぜ?」「どうして?」 という疑問がわきあがったときに「算数」へ と転化していくわけです。 教科書のように、計算の仕方や公式はなぜそうなのかを先に学習する「算数」から入ると、教師の意図するように、しっかりと発表してくれる優れた子が何人か出てきます。教 師はその子たちに助けられて、授業を展開していくわけだが、その子たちが実際にその場で工夫し、考えて意見を発表しているのかというと、そうではないのです。シビアに見ていると、実はその子たちの多くは塾や通信教育ですでにこの公式とそれに至る過程を学習していることが判明します。 一方、事前に知識を持たない子は教師の問いかけにいとも簡単に正解を述べる友だちに圧倒され疑問を抱いたり、質問をはさむ余地もなく、導入の一、二時間で頭がぐちゃぐちやになり、学習意欲を減退させてしまいます。 知識をもっている子がいるという現実があるのに、すべての子が知識をもっていないという前提で授業を組み、知識のある子に、あたかもその場で考えたような立ち振る舞いをさせること、そんな欺瞞に満ちた授業では、 知識のある子も、知識のない子も伸びません。 第一に幾千万の人々の英知と天才の閃きによって創りあげられた公式が小学校の子ども たちに発見できるわけがない。 今の算数の教科書は導入に多くの時間を使 いすぎている。そしてその導入が子どもにあらぬ混乱をもたらしているのです。教師が一斉授業の技で先人の英知を的確に語り、すべての子に平等に知識を与え、算術として習熟させてから、「さてなぜなのか」とみんなで考え合い、算数することを楽しむ。そんな授業こそがどの子も伸ばし、輝かせていく授業な のです。 ●算数授業についての問題意識 その2 ・子どもは履修した技を習得し「学力」とするためにはおよそ1年を必要とする 私は前任校と現在の学校とで、全校挙げての計算力、文章題力、読解力、漢字習得悉皆調査の学力実態調査を続けてきました。特に計算力の実態調査は10年間続けましたので それなりのことが分かったように思います。 私の学力実態調査の特徴は、前学年の課題 の定着を調べるものではなく、1年の課題か ら前学年の課題までを調べること、年に3回 から4回調べその進捗状況をクラスごと、学年ごとのデターを公開して、学力分布の実態をその都度議論することです。 この取組の中での私なりの結論は 1、計算課題をどの子にも獲得、習熟させるにはおよそ1年間の授業内での「さかのぼり的指導」が必要である。 2、4年生の課題の習得が不十分な子は1年間かけても5年の課題の習得が十分には出来ずにそのまま中学生になります。 3、剥落しない確かな学力の獲得は、新たな課題を理解、習得しながら進む。 4、優れた教師の授業は、既習の課題の復習、新たな課題の習得ではなく、新たな課題の理解、習得と既習の概念の再構築で成り立っている。 ・文章題の理解、習熟には独自の努力が必要 4年生の子どもたちは、4月から計算力の 「さかのぼり的指導Jに取り組み、1,2, 3年生の計算課穎については9月の段階で当初の目標にほぼ達する状態になっていました。 また、4月から教科書どおりに4年生の学習 を進めてきました。そんな子どもたちに、つぎのような四則の混合した文章題を出題し、 どれくらいの力を発揮するか調べてみました。
① 27g + 39g = 66g ② 24g/本×11本 =264g ③ 5g/まい ×43まい =215g ④ 66g+264g+215g=545g ⑤ 545g÷5人=109g/人 ⑥ 答え109g ①~⑤まで式が10点、答えが10点で採点 この文章題の成績の学年分布をグラフに表すと、みごとにM型のグラフになっています。 基礎・基本調査の計算力の分布はL型になっているのにと思い、一人ひとりの子どもたちの計算力とこの文章題の成績をドットで表し相関を調べましたが、必ずしも相関があるとは言い切れない状態でした。国語の読解力との相関も調べましたが読解力との相関も明確ではありませんでした。さすがに計算力が低いのにこの文章額の成績が優れているという子はいませんでしたが、計算力は百点なのにテストが零点の子いました。国語の読解力に優れているのにこの文章題の成績が悪い子もたくさんいました。零点が17人もいたことにショックを受けました。 この調査からの教訓は「文章題の力をつけるには教科書に文章題だけでは不十分であること、文章題の習熟には独自の取組が必要である」ということでした。 紙数の都合で詳しい実践は紹介できません。 (拙著「一斉授業の復権」子どもの未来社判 参照〉 |
||
| (詳細は、京都教育センター通信47号をごらんください。) |
| 行事案内 |
第41回京都教育センター研究集会 【設立50周年記念集会】 開催日:2010年12月25日(土)~26日(日)
|
|
京都教育センターホームページにアクセスを http://www.kyoto-kyoiku.com 検索「京都教育センター」 京都教育センター事務局や公開研究会の活動をはじめ、センター通信、季刊「ひろば・京都の教育」、教育センター年報、研究集会、教育基本法に関する様々な資料など、多彩な情報を提供しています。 |