 |
●京都教育センター通信 復刊第33号 (2009.5.10発行) |
京都府立高等学校教職員組合執行委員長 原田 久
今年の四月、「あなたは現場向きやと思うけど」という妻の言葉に少し動揺しながら、私は府立高教組の専従になった。 最後の勤務校は奇しくも新任で着任した須知高校で、親も教えた生徒たちに見送られ、思い出深い学校を後にした。今回は、この須知で三年間担任した食品科学科の生徒たちとのことを書いてみたい。 食品科学科は京都府下全域から受験できるため、四十人の生徒たちは北は綾部中学校、南は山科の大宅中学校からやって来た。彼らとの三年間がどのようなものだったのかを想像してもらうために、 京都新聞に投稿した一文を紹介したい。 三月一日、教え子が巣立っていった。振り返ると濃密な三年間だった。「このクラスだ大嫌いやった。学校も辞めたいと思った。でも、今は大好き。今までは 言いたいことも言わずに、(そのため) ケンカもなかった。でも、このクラスで はケンカが毎日のように起こった。おかげで自分も変われた。」 「みんなのおかげで今の自分がある。いろんなことを乗り越えてがんばってこれた。」 (略) 「三年間で二回本気で学校辞めようと考えた。 けど、心配してくれた先生と仲間たち。感謝。辞めなくてよかったって、率直にそう思える。」「高校生活いろいろあった。本気でムカついたり、傷ついたりもした。けど、そんなこと乗り越えてきた。 いろいろあったクラスやから『いいク ラスやったなあ』って心から思える。」 「三の一のみんな、私はみんなの担任で本当に良かったよ。卒業おめで とう。 この時から早くも四年間が過ぎ去った。私は担任の時に『ほっとステーション』というクラス新聞を発行してい たが、今も卒業生版『ほっとステーシ ョン』を不定期に発行している。卒業生たちはとても楽しみにしてくれていて、しばらく出ないと、「先生、『ほっとステーション』まだか?さぼっとるんちゃうか」と叱ってくれる。記事を書くためには卒業生に電話をしたり、時には出会う。すると、驚くような卒業生たちの近況が見えてくることもある。 たとえば、就職した卒業生たちの現実である。 「先生、俺もうアカン。辞める」「先生、今から店を出て、家に帰るところや(午前○時三十分の電話)」 「もうやっとれんわ。店終ってから掃除して、それからミーティング。ミーティング終わるの、夜十一時やで」、電話の向,こうで彼らは必死に叫んでいた。 就職をした十六人の内十人が五ヶ月以内に職場を去った。その中には、離職後日雇い派遣の仕事に就いたものの、怪我をし、補償もされないまま、やがて仕事が来なくなり、引きこもり一歩手前まで追い込まれた場合もあった。 こんな話が舞い込むと、詳しく聴くために出かける。話していると、学校時代にもっとこんな力や知識を培う必要 があったと反省することも多いし、なによりも卒業生たちがどんな現実に出 くわして、苦悶しているかを進学した生徒も含め、私たち教職に関わる者がもっともっとつかむことの大切さを思い知らされる。 最近はうれしい話がよく舞い込む。 「先生、今度結婚するし、披露宴jに来てな」、「S子、もうすぐお母ちゃんになるよ」、「先生、今度沖縄に住むことになった」、こんな話がやってくると早速カメラを持って出かけていく。話を聴いていると、ついこの間まで天真爛漫な高校生だった彼らが四年の年月の中でいろんな出会いを持ち、自分の人生を選び取っていこうとしている姿に出くわす。そんな時、「ああっ、人間ってこんな風に自分の人生を歩んでいくんだなあ」と思う。そして、教育とい う営みがその中でどのような意味を持ったのかを考えさせられる。 卒業生版『ほっとステーション』は これからもどんな物語を載せながら、卒業生たちの間を行きかうのか、ちょっぴり不安でもあり、楽しみでもある。 |
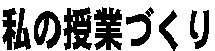
向日市立第六向陽小学校 清水 鉄郎
一、はじめに 昨年は、「源氏物語」千年紀といわれ、京都初め全国各地でその関連の行事や取組が数多く開催されました。「源氏物語」の「東屋」に「読み聞かせをする」場面があります。すでに「読み聞かせ」をすることによって、心を慰めたり、癒したりすることを 千年の昔から先人が知っていたことに驚きました。今、私たちは全国的に読書の大切さ、読み聞かせの大切さを強調していますが、「読み聞かせ」 は千年の歴史を持つ営みであるというのは大げさで しょうか。 二、全国ですすめられる「国語力向上と読書運動」を考える (一)全国に広がる朝読書のとりくみ 今日、全国的に、国語の学力低下(とりわけ読解力)、読書力の低下が指摘され、学校現場では、朝読書運動が広がっています。読書の習慣づけとしては効果的ですが、本来の読書の意図とかけ離れた管理と結びつく「朝読書」運動が広がっているのも現実です。 県あげての一〇〇〇万冊読書運動や学校ごと目標を設定させ、読んだ冊数を競わせ、教育行政が評価するという実態も起こっています。 一方で、学力テストの結果、読解力向上のために、国語の力をさらに向上させるため、「読書」をことさ ら強調している傾向が見られます。これは、私の学校の地域の現状だけではなく、全国的にも起こってきており、こうした読書のゆがんだ形が、学校教育に競争と格差を生み出す一面にもなっていないでしょうか。 本来、読書は強制的ではなく、自主的であくまで楽しみに結びつくものと考えます。「読解力」などの力は、結果としてつくものであり、結果を目的化すべきでないと考えます。 私の学校でもこうした見解を持っていますが、行政からは冊数を競わせる指導があります。 三、私の学校(前任校)でのとりくみから (一)日常的な「読み聞かせ」がなかったクラスを 担任して 読み聞かせとの出会いを大切にし、本を読んだり、 読んでもらったりする体験の心地よさを子どもたちにと、毎朝できるかぎり読み聞かせを実施しました。 読みながら、驚いたり、笑ったりしながら、読む先生も楽しいことをいっしょに感じたい、共感しあうことを大切にしました。 (二)何よりも「読み聞かせ」の楽しいひとときを子どもたちと一緒に 「読み聞かせ」本は短冊カードにして、すべて教室に張り出しました。イラストは係りの子どもたちが交代で描きます。だんだん増えるにしたがって、子どもたちの自慢になりました。さらに、本や作者に注目し、よく本を覚え、関連した本もよく読むようになりました。また、子どもたちの作文カードの中から、「読み聞かせ」のおも しろさを書く子どもたちもふえてきました。「みんな と一緒に聞くことが楽しい」と感じる子どもたちが出てきました。 (三)お母さんの「読み聞かせ」 ~本をかかえて教室にやってくるお母さん~ 学級のお母さんの自主的な取組として、「お母さんの読み聞かせ」がスタートしました。学級懇談会で出たもので、定期的に朝の十五分、お母さんが クラスのみんなに読み聞かせをします。子ども達は、その日のうちに感想を手紙にして届けます。するとお母さんから返事が届けられます。学級の子どもたちとお母さん方をつなぐものになり、懇談会でも話題になりました。 このお母さん方は、「読み聞かせノート」をつくり、次の人にまわしていました。今日読んだ本、子どもの反応や感想、読み手の反省、さらには、ク ラスのその日の雰囲気まで書いてありました。お母さん同士の交換日記みたいになりました。 四、「読み聞かせ」で育つもの 国語では、ブックトークの取組を学年で取り入れ、成果を上げてきたが、こうした取組で次のような力が育ってきたと考えます。 (一)「読み聞かせ」によって言葉に反応しながら イメージを膨らませること、表象力が育っていく。 (二)子どもたちの語彙を増やし、日本語の持っている美しさ、たのしさに気づき、日常の生活の中で発展的に広がつていく。 (三)作品の中から、社会や自然に対する認識を新たにすると同時に、具体的な形で人間の生き方や考え方の認識を作り上げていく。 (四)「読み聞かせ」によって、読み手と聞き手の心をつなぎ、作品を通して共通体験をする。 ということがいえるのではないでしょうか。 |
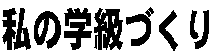
~もっと楽しいホームルームを求めて~
京都市立塔南高等学校 木下 淳史
TDLやUSlに行ったときのあの感覚を、HR教室で味わえないか、それがこの実践の出発点。HR教室がテーマパークなら、毎日楽しくてたまら ないだろうな、そのためにとにかく自分が楽しむためにいろんなことをやっ てみようというのが私の担任のやり方。もっと楽しいHRを求めてこの3年間も突っ走ってきましたが、その3年間の学級集団づくりのうち、一年四組の一年間を振り返ってみます。 クラス開きは十分な準備を! 入学式までに私がやっておくことはたくさんありますが、重要なことは学級通信の作成です。 私は一年の通信タイトルは「翼をください」と決めていて、週刊でLHRの日に発行することを原則としています。内容は前回のLHRで決定した事例の報告や本日のLHRでの実施内容などです。また学級日誌の準備も私のHRでは 重要で、日直は一日二人制、HR教室に学級日誌箱を設置して、生徒たちが自由に学級日誌を 閲覧できるようにしています。 入学式当日には、ビデオ撮影付き名簿の確認 をしましたが生徒たちはとても驚いていたようです。また入学式の次の日には、担任とのツー ショット写真付き自己紹介カードの作成もおこないました。これは作成後すぐに教室後方に掲示して、一年間の学級集団づくりの基本単位とする班づくりに利用します。そして、「班づくりに挑戦!!」です。私は班を掃除、座席、行事 そしてHR役員の基本グループと位置づけ、H R役員も一つの委員に一つの班を割り当て協力させる形式をとります。こうしたことを四月当初におこない、少しでも早く生徒たちにとってHR教室が居心地のよい場所になるように心がけます。 前期は学校行事が目白押し! 前期の九月までは、学校行事が目白押しです。 どの行事もさらに楽しむために工夫を凝らします。クラス遠足では、「BISTRO KINOPPI」 と名付けた野外炊飯の班別対抗コンテストと、「勝負服コンテスト」と名付けた遠足のときのみ許可される私服で競い合うコンテストを企画し、前日には遠足下見ビデオも上映します。終了後は、それぞれの表彰パーティーと遠足のビデオ上映で楽しみます。 球技大会や体育祭では、「めざそう!優勝!」 を合言葉に、一週間前から昼休み練習を開始します。そして終了後は、必ず優勝祝賀パーティーを実施します。残念パーティーになる時もあるわけですが、それでも終了後に見るビデオ上映ではみんな笑顔になれます。 文化祭では各自が楽しいと思う活動をするということを重視して、いくつもの企画に取り組みます。結局、展示で女子中心の「ちぎり絵セサミストリート」を製作し、男子中心で「カジノ風ゲームセンター」を実施しました。 後期はクラス独自の行事でエ夫を! 十月からの後期に入ると、学校行事は少なくなりますが、クラス独自の行事を多く企画し楽 しみます。前期にも五月のこどもの日パーティ ー、七月の七夕パーティーを実施しましたが、 後期には十二月のクリスマスパーティー、一月 の班対抗百人一首大会、二月の節分パーティー、 バレンタインパーティー、三月のひなパーティーを実施しました。そして後期最大のイベントが一年四組独自秋の遠足で、十一月の極力クラブの練習の少ない土曜日にみんなでUSJへ行 きました。 一年間の学級活動のまとめが、三月のサヨナラ特別企画「ありがとう!!一年四組」と名付けたイベントです。これは「クラスMVP投票」、 「クラス寄せ書き」、「最終クラス写真」の三本柱からなる企画で、特に「クラスMVP投票」 は、一年間にクラスで最も活躍したメンバーを投票で選び、表彰しました。 後期終業式に実施した、この「一年四組MV P」表彰式兼サヨナラパーティーでは、「一年 四組MVP」の表彰と賞品 (「寄せ書き」の原本と一年間に獲得した賞状)授与の後、一人づつ進級記念品(「寄せ書き」カラーコピーと「担任とのツーショット写真付き自己紹介カード」、 「DVD二〇〇六年度一年四組全記録」)を渡 して、握手でサヨナラしました。 最後に~三月二日の卒業式を迎えて~ 二〇〇九年三月二日、私とともに一年間歩んだ旧一年四組の生徒たちが卒業式を迎えました。卒業式の後、一年の時のHR教室に生徒たちを集合させ、卒業祝賀パーティーを開きました。入学式のときのビデオ映像を見てみんなで 笑いあいながら、一年四組の一年間の 「翼をください」をまとめた小冊子を配布し、私は感動 のひとときを味わいました。 (この実践の詳細は季刊誌「ひろば」五月号に 掲載されています) |
|
||
[09第1回公開研] 高校における学力保障と学習指導要領の改訂 今回の改訂では小中と同様に学習内容の増加と全教科での道徳教育の強化や「言語活動の充実」を打ち出し、これまでの「ゆとり教育」の転換を図りました。そして、総則で強調している「義務教育段階の学習内容の定着」では、すべての高校生への確かな学力を保障する観点での教育課程の編成を各高校で検討することが求められます。講演とともに中学校や高校での実践報告を聴くだけでなく、教育課程検討の一助になればと願って企画しました。 |
||
[公開研究会予定]現在、企画中のもの Ⅰ. 5月31日(日)13:00 教文202 「高校での学力保障と新指導要領」 (学力問題研) Ⅱ. 7月19日(日) 9:30 教文204 「エンカウンターグループ」 (カウンセリング研) Ⅲ. 9月 6日(日)13:00 教文203 「内容未定」 (発達研OR地域研) Ⅳ.10月12日(月)13:00 教文203 「内容未定」 (発達研OR地域研) Ⅴ.11月29日(日)13:00 教文203 「子どもの発達と集団づくり(仮)」 (生活指導研) ◎ 第40回研究集会: 2010年1月23日(土)~24日(日) 教文センター全館 |
||
[定期刊行物] ・季刊誌「ひろば」158号~161号の4回発行 ・「センター通信」毎月発行 ※ 京教組の取り組みに共同します ・ 民主教育推進委員会への参加:5/9 9/12 11/1 ・京都教研への共同:11/14~15 |
||
京都教育センターホームページにアクセスを http://www.kyoto-kyoiku.com 検索「京都教育センター」 京都教育センター事務局や公開研究会の活動をはじめ、センター通信、季刊「ひろば・京都の教育」、教育センター年報、研究集会、教育基本法に関する様々な資料など、多彩な情報を提供しています。 |