 |
●京都教育センター通信 復刊第25号 (2008.7.10発行) |
国民融合・全国会議事務局長 大同 啓五
このほど文部科学省から「人権教育の指導方法等の在り方についてー第三次とりまとめ」が、公けにされたということです。(〇八年二月) 今後「人権教育」の推進が、ことさらに強調されることと思われます。そこで日ごろ思っていることを若干述べてみることにします。 ①「人権学習」の内容が、実際には差別意識解消のための学習になっていないだろうか。 九六年の地対協「意見具申」も、つぎのように述べています。「今後、差別意識の解消を図るに当たっては、これまでの同和教育・啓発の中で積み上げられてきた成果とこれまでの手法への評価を踏まえ、〝人権教育・啓発として発展的に再構築すべき〟〝同和問題を人権問題の重要な柱として捉え〟」と。つまり、「人権教育」の課題を差別意識解消の問題としてとらえ、これまでの同和教育・啓発を無批判に「人権学習」の手本のように扱っています。 しかし人権にかかわる問題をとりあげるにあたっては、基本的人権がすべての等しく保障されなくてはならないことを明確におさえるとともに、個々の問題をとりあげる場合、単に差別・被差別の関係としてとらえるのではなく、それぞれの問題の本質、問題解決に向けての現到達段階、解決に当たっての当面の課題などが明確にされなくてはなりません。 ②この折り、人権について学ぶ子どもたちがそれぞれに、自分の考えを自由に述べ、友達との意見交換を通じて、自らの人権についての認識、自覚がつちかわれていくように配慮され、「人権」の詰め込み教育にならないよう留意されなくてはならないと思います。 実際に「人権教育」がひとごとの「人権学習」に終わつていて、それぞれの子どもを人権の主体として尊重する観点、教育実践が弱くはないだろうか。人権についての理解、認識を育てていくことと、子どもを人権の主体として尊重していくこととが統一して追求されなくてはならないと思います。 ③さらに、子どもの学習と発達する権利を保障していくこと自体が、人権の保障であるという認識が弱くはないだろうか。 今日の学校教育が、能力主義と管理主義の強化という政府の教育政策によって、本来の基礎学力をつちかい、民主的な人格を育てる場からかけはなれ、詰め込みと過度の競争の場、子どもの人格を認めようとしない管理の場に変質させられてきています。人権尊重というならこういう教育政策は直ちに改められねばなりません。 そのうえ、子どもの人権保障にとって不可欠な基盤や条件が貧しいままに放置されていないだろうか。子どもを絶えず激しい受験競争のなかに追い込み、貧しいままの教育条件と教師の多忙化を放置し、「管理」のみを強めるもとでの人権教育の推進は、本来ありえません。 |
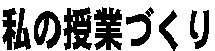
ー新聞の切り抜きの発表と感想の取組について
京都府与謝野町立加悦中学校 浦島 清一
1 新聞の切り抜き・発表はこうして始まった。 今、地球や世界が大きな課題を持っている時、子どもたちは、その社会とどのようにつながり、またその社会や世界を認識しているのだろうか。 生徒に聞いてみると「新聞は読んでない」「新聞を読んでもテレビ欄ばかり」「世の中のこと知らなくても生きていけるし」との答えばかり、そこで、毎年やっていた「新聞の切り抜きと発表」に加えて、みんなで感想を書き、その感想を発表者に返し、それを読んだ上でレポートをさせた。方法としては、① 気に入った記事を選び、それについての意見を回覧ノートに書く。② 切り抜いた記事を始業前に届けさせ、印刷し、授業前にそれを配る。③ 発表者は発表をし、他の生徒は発表後自分の感想を書く。④ すべてが発表後、他の子どもたちの感想文を渡し、その後レポートさせる。 2 記事選択から分かること 子どもたちが取り上げた記事を整理するとこんな事が分かった。① 「命」に関わることを多く取り上げている。これは今の子どもたちが、「命」や「生きること」についてしっかりと考えたいという思いの表れでは。② 「子どもに関わる事件」や「教育」に関わる記事についても興味を持っている。③ 地球規模の課題である「戦争」「環境」などについてもしっかりと考えなければいけないという課題意識を持っている。 3 取り組んでみて (1) 新聞を読む中で、記事を解説したり、自分の感想を書くことにとどまらずに、何でそうなのかを考える生徒も多く出てきた。また、次第に社会全体に目を向け、自分の生き方に迫る生徒も出てきている。 (2) 今回はみんなの感想文を発表者に返し、その感想を読んでさらに自分の考えを深めることを課題にした。自分の考えたことをみんなはどう思っているのか、今子どもたちのつながりの薄さを考えたとき、「言いっぱなしで終わる」のではなく、子ども同士をつないでいく取組の重要性感じている。 (3) 人の意見を聞く中で、「同じ問題でも、こんな考え方がある」という評価と、一人一人は違うことに改めて気がついている。また、「人間の考えは変わるんだ。」と書き、人との意見の交流の中で、自分の考えが深まったり、変わることがあることに気がついている。 (4)この取り組みは生徒の支持を得たが、それは新聞を読み、考える。それが次第に社会や日本そして世界につながるという読みをしたときに、「知ることはすばらしい」と感じる「学び」ができることになる。 また、「一人の学びからみんなの学び」につながる喜びなのではないかと考えられる。自分が取り上げた記事をみんなが一緒に考え、感想を書くその中で「共感」「発見」があり、さらに「知りたい」、そして「本当のことが知りたい」という願いとなってくるのではないかと考えられる。 |
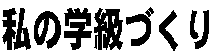
八幡市立八幡第二小学校 森田 紀恵
一、「班づくり」で前進する学級を この数年間は、高学年を担任することが多くなりました。二十数年前のようにガンガンと「学級集団づくり」を進めるわけにもいかず、時に多くを妥協しては、なんとか自分も、自分の主義?もつぶされないように、毎日の学級づくりをしています。 私がずっと続けてきているのは、ごくごくあたりまえのことなのですが、「班づくり」をすすめながら、学級も前進させていくということです。どこの学級でもやられていることでしょうが、四月から年七、八回の班替えを繰り返しながら、話し合える・協力し合える班を目指します。チャイム席や集中二十秒など、いたって真面目な目標に取り組んでいきます。がんばりシールを貼っていくのが、いつものやり方です。 二、「おもんない。俺やらへん」 「そんなんやったって、しゃあないやん。」「おもんない。俺やらへん」と、言い出したA君。もちろんA君のいる班のシールはちっとも増えません。声を掛け合い、どんどんシールを増やしていく他の班との差は開くばかり。こんなとき、「そこは、ダメ班!」「がんばりが足りない!」と言ってしまったらオシマイです。班づくりや取り組みは、ダメな子や足を引っ張る子にレッテルを貼って『いい子だけでがんばる学級』をつくることが目的ではないからです。目標に向かう時のハードルを明らかにしつつ、それを乗り越えていける力──それは例えば、A君に協力を求め、励まし、いっしょに行動していける力だと思うのですが──をつけていくことこそ目的にすべきでしょう。でも、実際A君の班のシールが目標に届かなければ、他の班のやる気も失せてしまいます。ここで奥の手?を使います。「うーん、A君の班はなかなか苦労しているねえ。でも先週よりは班の中での声掛けは増えているよ。進歩、進歩。」とごくごく小さな変化をほめます。そして、「そうやな、シール五十枚!」なんて、サービスします。A君も「俺ががんばったからやぞー。」とへんに自慢したりして、その後も努力を続けるようになります。A君がいる班のシールは百枚以上。しんどい子がいる班こそ優秀班にすることは、とても大事なことだと思っています。 三、楽しみながらの試行錯誤 みんなが足並みをそろえるということが、実はとても難しいことなんだとわかってきたころから、こんなふうにちょっとズルイ?甘い?方法を取り入れています。もちろん、一歩の歩幅は、一人一人違うということ、それでも前に進んでいる方向は同じであること、それをみんなで確かめ合いながら、さまざまな取り組みをしていくことが私流の学級づくりです。思い通りに子どもたちは動いてくれません。自分たちの意志で動くようになるために、どんな言葉かけをすればいいのか、どんな大人として彼等の前に立てばいいのか、試行錯誤の繰り返しです。それを楽しむつもりで長ーく働きたいです。 |
――今夏は全国レベルの研究会(IN京都)が目白押し―― 民間研と全国教研でおおいに学ぼう! 今年の八月、京都では全国規模の研究集会ラッシュです 何もなかった昨夏と比べて今年は7つもあり、前代未聞の ことです。お盆前の民間研は日程が重複しているので選ば なくてはなりませんが、最低ひとつには参加したいもので す。盆明けの「全国教研集会」は1990年の第1回開催 以来18年ぶりの京都開催です。今から日程調整して何を 置いても参加しようではありませんか。
今、学校現場は、戦前の治安維持法下の教員生活を描いた三浦綾子の「銃口」の時代背景に近づいていると指摘する研究者もいるぐらいです。学習指導要領や観点別評価、週指導案などの「呪縛」にあって、子どもの成長とは無縁の報告が求められています。新学習指導要領の今後の十年で、教育基本法に次いで憲法さえその改悪を強行するシフトを着々と敷いてきています。 私たちはこの路線に歯止めをかける重要なカギを握る立場にあります。そのためにはふたつの方策が必須です。一つは「力」です。父母と共同して子どもの立場での民主教育をすすめる教職員の勢力を大きくすることです。もう一つは「技」です。すべての子どもがかしこく豊かに人間として発達していく道筋を解明し、自前の授業づくりや教育課程づくりを志向することです。とりわけ、この20年ほどに採用された方は、子どもの実状や発達観を踏まえないマニュアルチックな指導方法を行政研修や官制研のトップダウンで学ぶことを強いられてきています。今の教育を管理と統制の下にあると認識し得ない方々もいます。そこでは、表面的に流れている日々の教育活動にあっても子どもとの豊かなふれあいは「乖離」しています。 若い先生もベテランも、今の自分の実践に確信を深めると同時に、学び直すチャンスが今夏です。 苦労して積み上げられた全国の仲間の実践を近くで学ぶ機会はあまりありません。休養をとりつつも、思い切って足を運んでみませんか。自前の授業と学校づくりをめざすあなたの今後に大きなインパクトを与えることは請け合いです。職場の同僚を誘っての積極的な参加を訴えるものです。 2008年7月1日 京都教育センター |
|||
[センター公開研究会のご案内] どなたでも気軽に参加できます。
|
|||
京都教育センターホームページにアクセスを http://www.kyoto-kyoiku.com 検索「京都教育センター」 京都教育センター事務局や公開研究会の活動をはじめ、センター通信、季刊「ひろば・京都の教育」、教育センター年報、研究集会、教育基本法に関する様々な資料など、多彩な情報を提供しています。 |
|||
 |
「季刊ひろば」・・・・・ご存知ですか? --京都で唯一の教育専門誌です-- 154号(5月刊)が刊行しました。 特集1 新学習指導要領と学校教育-「生きる力」「基礎・基本」を問う 2 今日の不登校・ひきこもり問題-教育・福祉の連携と自立支援 ◎見本誌(無料)希望の方は 氏名・学校名・住所・電話番号を記入してFAX(075-752-1081)にお送り下さい。 ◎定期購読者も募っています 〔年4回刊 年会費2960円(送料共・年1回の振込)〕上記と同様に申し込んでください。 |