 |
●京都教育センター通信 復刊第 5号 (2006.10.10発行) |
倉原 悠一(京都教育センター)
もう二十五年ほど前の出来事になるだろうか。当時三十代の私にとって忘れられない一コマがある。その当時、担任をしていた高校での朝会で、いっこうに指導にのってこないある男子生徒に業を煮やして、「○○。今日こそ君に引導を渡すからな!」と怒鳴った。その場はそれで済んだのだが、放課後、職員室にその彼がやってきて、「先生。来ました」と言うのである。私は彼を呼んだ覚えがないのできょとんとしてると、彼は「先生。今朝何かを渡すと言うたやんか」と説明する。私は最初何を言っているのかわからなかったが、やがて「引導を渡す」と怒鳴ったことを思い出して、改めて彼に何も意味が伝わっていなかったことを思い知ったのである。その時以来、授業でも、生活指導の場面でも、生徒に概念を伝えるときは、言葉に気をつけ、出来る限り丁寧にしなければならないと肝に銘じた。
授業での場面
私は化学を教えているのだが、授業では「具象から抽象へ」という理解の法則を大事にすることに心がけている。そのためまず小学校や中学での学習の確認をし、新しい概念の感性的な理解を深めさせる。その上に少しずつ概念を発展させた発問を重ね、抽象的な概念へと誘う。その時、授業が一定の緊張感のあるものであることが大事。こちらの発問に対して具象から抽象へと思考を発展させて、新しい世界を知る「そうか!」と言う喜びを実感して欲しいと願っている。
ところが、今年になって悪戦していることがある。それは、高校一年生のかなりの層が、小学校二、三年生での算数分野でのつまずきを抱えていることである。分数の簡単な計算が出来ない。以前から「b/a=d/cのときcを分数で表せ」という問題が出来なくなって久しいが、いまは、例えば(2/10)の値がすぐ出てこない。多くの生徒が(1/5)としてから、筆算を始める。また、分数が「分子割る分母」なのか「分母割る分子」なのかがあやしい。だから(8/40)の値が(0・5)になってしまう。最初なぜこの値が出てくるのかつかめなかった。また、「分母、分子の移項」が扱えないことも計算を遅くしている。高校の授業では理解に一定の早さが求められる。算数分野でつまずいていた場合、授業中にここまで戻って教え直すには限界があり、見切り発車をせざるを得ない。でも高校化学の計算の大半は比例計算である。放っておくわけにも行かず、「あー。これも三割削減、ゆとり授業の現実か」とため息をついている。この現実に悩んでいる教科は理科だけではなく、家庭科や社会科でも直面している。こうなると高校でも早い時期に「百マス計算」的な計算の基礎トレーニングが必要になっているのかもしれない。
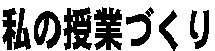
京丹後市立網野南小学校 和田 誠
三年生の終わりに、クラスみんなで「モチモチの木」の勉強をしました。豆太の勇気や、やさしさをみんなで読み味わいました。それでもおくびょうが治らない豆太に、心を寄せて読むことができました。
そして、「モチモチの木」の勉強の最後に暗唱をしてもらうことにしました。何回も何回も家や学校で読む練習をしていたので、多くの子どもたちが手を挙げました。その中から、H君に読んでもらうことにしました。H君は、みんなの前に出て、堂々と暗唱しました。それを、ジーっと静かに聞いていたA君。H君が読み終わって、みんなの拍手が終わったあと、 「首が痛いのも忘れて、うっとりと聞いていた!」 と、自分の席でうつ伏せになりながらつぶやいたのです。H君に、 「A君のことば、どう思って聞いた?」 と尋ねてみると、H君は、「うれしかった!」 と言いました。そして、それでは言葉が足らなかったと思ったようで、 「すごく、うれしかった!」 と言い直しました。
A君は、一時もじっとしていられない多動な子どもです。自分の好きなことは頑張るけれども、嫌なこと・気に入らないことはちっともしようとはしません。毎日、「いらん」「しちゃにゃあ」という言葉の連続です。習熟度別学習がもてはやされている今日、クラスのみんなで勉強するということが、こんなに素敵な場面を作り出してくれました。
A君の書いた詩です。こんなにスケールが大きくて、ロマンのある詩に初めて出会いました。
しょうらいのゆめ 三年 A
ぼくは、大きくなったら、
うちゅうひこうしになりたい。
ぼくのゆめは、
太ようけいをこえること。
太ようけいをこえたら、
となりの ぎんがにいってみたいな。
となりのぎんが、
アンドロメダ大せいうんに
いってみたいな。
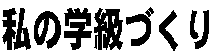
与謝野町立市場小学校 瀬戸 亭明
教師歴二十数年、何年たっても、満足できる実践がなかなかできず、日々悪戦苦闘の毎日が続いているのですが、自分の実践にいつも貫いていることがあるので紹介したいと思います。いわば、自分の経験から得た実践上の指針のようなものですが、常に意識することで、自分の実践がずいぶんと安定したものになってきたし、学級づくりにも役立っているので参考にしていただければと思います。
子どもをつかむこと、子どもとの関係づくりに徹する
一つは、子どもをつかむことに徹し、指導が入る関係づくりに全力を注ぐことです。そのために、まずは、子どもの中に入っていくことをとても大切にしています。何気ない子どもの会話に加わり、友達のように対話するのです。こういう時は、決して指導的立場で入らないようにしています。とにかく子ども達と対話を楽しむつもりで接することが大切です。気楽な関係の中で無ければ、子ども達は本音をなかなか語ってくれません。こうした対話の中で友達や家族、家での暮らしの様子など、以後の指導に大いに役立つ様々なこともつかむことができますし、意外な子どもの優しさや特技がわかったり、また、新たな課題を発見できたりもするものです。
また、子ども達が活躍している地域の活動。たとえば少年野球クラブ、少女バレーボールクラブ、ミニバスケットクラブ、地域の公民館行事、町主催のボランティア活動などにも可能な限り顔を出し、子ども達の様子を伺ったり、時間があれば、ともに活動に参加することも心がけています。特に、こういったところで見せる子ども達の様子は、学校とはかなり違うことが多く、改めて子どもを見直すこともしばしばあるものです。学校というのは、子ども達にとって、教師の管理下にあり、指導を受ける所と思っているせいか、必ずしも、本音をだして生活しているとは限りません。学校という場を離れた時に見せる様子に、子ども達の本音が現れている場合が多いように思います。こうした場面での子ども達の活躍を知っていると、学校では気付かなかった子ども達のよさや頑張りもたくさん発見でき、「叱る」ことばかりになりがちな指導から、「評価したり誉める」指導が多くなり、子どもとの関係も良くなっていきます。もちろん、叱るべき時には厳しく叱るのは当然ですが、一方的にしかるばかりでは、子どもとの関係は決してよくなりません。しかってもその倍、子どもの活躍や頑張りを評価したり誉める指導が子どもたちのやる気を引き出していくことは言うまでもないことです。このように子どもの中に入ることや学校以外の子どもの活躍を知ることで、子どもをしっかりと捉えていけるし、何よりも、子ども達と教師との関係が深まり、こちらにずいぶんと心を寄せてくるようになってきます。共感関係の成立です。こうなればこちらの指導をきちんと受け止めたり、少々困難な要求にも応えていこうと努力する子ども達が増えてきます。子ども達にとって自分のことを本気になって考えてくれたり、気にしていてくれる教師に対しては、実に素直にこちらの願いに応えようとしてくれます。
 (写真は9・23討論集会) |
20氏呼びかけへの賛同続々! 10日間で有権者300人超える「許さじ」の声 鯵坂真氏ら20氏による「教育基本法改正案の廃案を求める」緊急アピールは9月18日に公式発表しました。その日から、教育関係者、学者・大学人、文化人、宗教者、法曹界、民主団体、元学校長など1000人を超える有識者に賛同を求めるアピールを郵送しました。京都教育センターや科学者会議京都支部がその実務遂行に尽力しました。 9月末のこれへの賛同者数は別表のように約300人を数え、開始10日間ですでに5年前のとりくみの最終到達点を上回っています。今後、10月20日の締め切り日まで更に、廃案を求める有識者の賛同が寄せられるものと期待されます。 こうした背景には、安倍新政権が超タカ派的スタンスから、今臨時国会では「教育基本法の改正を何としても」と強行する姿勢を露骨にしている事への危機感と運動の高揚の反映を伺うことができます。また、9月21日に出された「君が代強制は憲法・教育基本法違反」と裁断した東京地裁の難波判決も私たちに大きな確信と勇気を与えるものでした。ひきつづきみなさん方のまわりで11月3日の円山集会を大きな結節点とした大運動への尽力をお願いします。 |
|
 |
148号 予告 (2006年11月1日発売予定) 特集テーマ 1 性と生を考える−−現代の社会・文化といのちの教育 総論で小学校の現場からの実践報告があり、それを踏まえて、各論で今日の性教育にかけられている攻撃の特徴や、京都での性教育の取り組みを紹介する予定です。 2 中学校・高校生の進路選択・進路指導−−社会他の出会い方 |
・購読希望者には見本誌を送付します ・定期購読者は年間会費2960円(4冊分)を年一回郵便振替で
・T&F075−752−1081かEmail:kyoto-kyoiku@asahi-net.email.ne.jp へ申し込んで下さい
[氏名・学校名・自宅住所・電話を]
| 11月4日(土)午後1時〜 会場:京都市・町屋「古武」(上京区大宮通五辻上ル)
京都教育センター06公開研究会第3回「国語教育の危機、どうする!」集会 〔同日 京教組民主教育推進委員会(午後1時〜教文センター)も開催されます。〕 |
|
| 11月11日(土)・12日(日) 会場:京都教育大学 第56回京都教育研究集会 | |
| 2007年1月27日(土)・28日(日) 会場:京都教育文化センター第37回京都教育センター研究集会 |
| 京都教育センター ホームページは http://www.kyoto-kyoiku.com
・京都教育センター事務局や公開研究会の活動をはじめ、「季刊 ひろば・京都の教育」、教育センター年報、冬季研究集会、教育基本法に関する様々な資料など、多彩な情報を提供しています。 |