 |
●京都教育センター通信 復刊第 2号 (2006.6.10発行) |
教育基本法改「正」法案、国民投票法案とその先の憲法改「正」、共謀罪法案など、日本社会の構造、歴史の方向を大きく変える法案が集中している今国会。この文章を書いている時点では、会期延長がなく、これらの法案は継続審議となり、秋の臨時国会にゆだねられる可能性が高くなっているが、予断は許さない。ここで緊張を緩めることなく、この間の国民的な関心と運動の高まりを、さらに大きく確かなものにしていくことが求められている。
それにしても、今、日本社会はどのような構造変動の大きな流れの中におかれているのだろうか?「官から民へ」の掛け声のもとで進む「構造改革」によって、公営事業や公立施設の民間委託(指定管理者制度という「丸投げ」も含めて)が大規模に進められている。しかし、そのことによって、人々の生活を支える諸制度・サービスが全体としてどのようなかたちになるのか、広がる「民」をコントロールしていく「新たな公」は見てこない。行政(公)が最終的に担うべきは「戦略本部」の役割で、具体的な施策・事業はことごとくアウトソーシング(外注、つまり民間事業者にゆだねる)という自治体イメージが狙われていると、神戸大学教授の二宮厚美氏は描いてみせた(日本社会教育学会6月集会での報告)が、これは、いわゆる「三位一体」改革によって、国(政府・中央省庁)の役割を、外交、防衛などに絞り込んで「小さな政府」をつくるというイメージと重なる。
一連の「悪法阻止」の取り組みを、このような「構造改革」の大きな狙いの中においてみることで、「阻止」「反対」の運動を、「構想」「創造」の取り組みとして発展させていく道筋を展望していきたい。この思いは、平和憲法、教育基本法の理念にもとづくとともに、NPOの急速な増加や、暮らしのさまざまなニーズに住民の協同の力で応え、新しいかたちを創造していく活動の展開、その先に展望される新たな社会像のイメージを豊かにしていくことへの期待といってもいい。
人類は、進歩と反動、抑圧と解放を行きつ戻りつしながら、より多くの人々が平和と民主主義のもとに暮らす社会を広げてきた歴史をもっている。 新たに生み出された社会的諸関係を、さらに作り変えていくという「否定」を契機として含んだ弁証法的な歩みを重ねながら。
コスト削減を至上命題とする激しい合理化は、不安定就労の拡大を生み、若者から、社会への信頼と将来への希望を奪っている。医療費負担の増大は、高齢者とその家族に不安をひろげている。全体社会の変革放棄宣言とでもいえる「格差社会」という時代のネーミングは、より多くの人々から希望を奪い、人間不信を強める力を働かせている。
そんな困難と新たな社会創造の胎動という時代状況の中で、分析や解明にとどまることなく、創造の力となる、研究・実践に力を注いでいきたい。 (初夏の美しい田園風景を新幹線の車窓から臨みつつ、この社会の平和と信頼に裏づけられた明日の姿への思いをこめて)
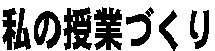
この春、四年間の組合専従の仕事を終えて、現場に復帰しました。復帰と同時に転勤となり、亀岡の北西部の広大な水田地域に位置する高田中学校に転勤しました。
四年間のブランクと新しい教育課程初体験に心配しつつ、一クラス二十三〜二十七人の規模で、少人数学級の有り難さをしみじみと感じながら、忙しいながらも授業づくりを楽しんでいます。
久しぶりの授業は①何よりも、子どもたちはもちろん、自分自身が楽しいと感じられる授業にしたい。②授業の中で、生徒との対話や生徒間の関係性を大切にしたい。③楽しく、本質的な実験や観察をできるだけ行いたいとの思いでやっています。
今年は、一年と二年担当しています。
一.楽しい授業は本質を追究する授業
楽しい授業は、わかりやすい授業のことであり、内容の本質に迫る授業だと思っています。最近、教研の理科分科会に中学校レポートがあまり出てきません。現場の忙しさと共に、高校受験という上からの圧力、学年複数担任制が多様な実践の自由度を奪っているように思います。それでも、限られた授業時数の中で、同じ内容を扱っても、教材に対する本質的な深まりは追求できます。そのとき授業者としての教師の力量を積んでいくことが求められます。
教材に対する研究と新しい発見が必要であり、それが理科教師の楽しみです。その成果を持って、いそいそと授業に行くことが理科教師としてのささやかな喜びです。
私自身、力量ある教師とは全然思っていません。話術もへただし、いつも自信なく悩んでいます。それでも全国の理科大好きの先生が集う科学教育研究協議会の大会でいっぱい学び、いろんな実践やネタを仕入れ、「まねる」ことで、理科教師としての喜びを感じさせてもらっています。
二.子どもをリアルに見つめながら
これまでプリントを主体に授業を組み立ててきましたが、今年は、ノートに書くことを大切にして、子どもたちとの対話、集団の優位性を意識して授業をしています。
授業では、子どもたちの発言、表情、ノートを見ながら、少し変化を加えています。
先日、二年のS子さんが、私の横で「理科おもしろくないわ。授業もわからへんし。あっ、先生聞こえてた。ごめん。」と独り言(?)のように言いました。私は「そうかあ。」と笑顔で答えながら、内心おだやかではありませんでした。そこで担当クラス全員に「理科授業アンケート」を無記名で取ってみました。「理科の授業はおもしろいですか」「授業分かりますか」などの内容で。
すると少なからずの数で「おもしろくない」「授業が分からない」の回答が出てきました。現場に戻り、「何とか授業づくり順調かな」と密かにあった自信はもろくも崩れました。しかし「現実は難しい。現実をリアルに見つめ、そこから進むしかない。現実を前に一喜一憂してもしかたがない」と思っています。
多様な考えを持つ子どもたちを前に、今年は、子どもたちの声に耳を傾けながら、ちょとでもましな授業を目指していきたいと考えています。
また集団の力に依拠した授業も大切だと思っています。実験はもちろん、授業場面での教え合い・班での討論や問題の出し合いの設定を意図的に組み入れています。
三.まとめにかえて
教師生活が終わるその日まで、教壇に立って授業をしているでしょう。またそうしたいと思っています。満足のいく授業がどれだけできるかわかりませんが、最後まで学び続けていきたいと思っています。
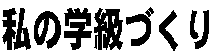
十三年ぶりの三年生の担任です。活動的で元気いっぱいの子ども達ですから、毎日のようにもめごと、喧嘩などが起こります。私は、暴力は許しませんが、子ども同士のもめごとや喧嘩は、指導のチャンスと捉えています。もめごとを起こしている当事者だけで解決できるささいな問題もありますが、できるだけ当事者だけの問題にせず、クラスの子ども達にも考えさせ、解決の方向を探っていくようにしています。その意味で毎日の「終わりの会」を大切にしています。
中間休みが終わって、一男が泣いて帰ってきました。授業が始まっても一男はうつむいたままで、教科書も出しません。理由を聞いても答えません。一男が泣いている理由をクラスの子に聞いても、誰もわからないということでした。
四時間目が終わり、給食の時間になりました。一男はこの教室では食べたくない、学年ルームで一人で食べたいと言いました。一男が一人で食べるのはかわいそうだということで同じ班の子二人が一緒に食べました。そんな中で一男も落ち着きを取り戻して、何故、泣いたのかを班の子と私に話しました。
中間休みに、男子数人で「中あて」をしていて、入れてと頼んだところ、「お前は関係ない。」と断られたということでした。
「終わりの会」で、そのことを話し、その時の悲しかった自分の気持ちをみんなに話すように、班の子も、私も一男に言いました。「もう、ええねん。」と一男は乗り気ではありませんでしたが、説得し「終わりの会」で発言することになりました。
一男の発言をもとに事実確認後、子ども達からいろんな意見が出ました。「遊びに入れてあげなかったのはあかんことや。」「一男も泣かんとはっきり気持ちを言えたらいいのにな。」「一緒に給食を食べてあげた班の人は優しいと思う。」「人数が合わなかったのだから入れない時もある。」「関係ないという言い方はひどいな。」等々。
自分の気持ちをみんなに伝え、真剣に聞いてもらい一男の表情は明るくなりました。誰が良くて、誰が悪いと暴くのではなく、どういう行為、行動が正義なのかをみんなで確認していきました。
私は、学級開きで「学校は失敗や間違いをしてもいいところ。その失敗や間違いから勉強していったらいい。安心して失敗していいよ。」と言っています。毎日の終わりの会は、その勉強の場です。自分達の生活を振り返り、何が正義で、どういう行為は許されないのかを明らかにする「価値討論の場」であると思います。三年生の子ども達ですから、教師の力を借りなければ十分に討論することは出来ませんが、毎日の積み重ねが、高学年になった時に自分達で問題を解決していく自治の力の基礎になると思っています。
| ○終わりの会プログラム ①嬉しかったこと、良かったこと ②いやな思いをしたり悲しかったこと ③係からの連絡 ④当番(日直)から ⑤先生の話 ⑥さよならコール |
 |
教育基本法「改悪待った!」緊急集会に学者・青年など63人 京都教育センターはこの数年間教育基本法の「見直し」が出てくるたびに、現場教職員を含む教育関係者による幅広い共同のとりくみをすすめてきました。2001年4月には鰺坂二夫氏(故人)、広原盛明氏ら16氏による「拙速な改正でなく深い教育論議を」の呼びかけを発表し259名の賛同を得ました。翌年には再びアピールを発信し、その後運動へのカンパを訴え集まった60万円を基金として「教育基本法」を出版(05年3月)しました。この本には04年度に開催した12回の基本法連続学習会(条文毎)のすべてが載せられ好評を博しました。 そして、今回の「改正」案が国会議論になっている最中の5月27日(土)、中央での10万に集会に呼応して「改悪待った!」の緊急集会を教育文化センターで開催しました。代表の野中一也氏による「改悪法案を廃案にしよう」との問題提起があり、深沢教文部長や成宮まり子日本共産党国政委員長からの情勢報告がありました。また、「負け組を余儀なくされた青年は就職先として自衛隊(軍隊)を望んでいる」(総評青年部)、「現行の教育基本法の下で教師になりたい」(大学院生)などの青年トークが共感を呼びました。会場からの数名の発言もあり、63名の参加者一同による緊急アピールを採択し関係機関に送付しました。 なお、この集会に向け宗川吉汪氏・望田幸男氏など48人の学者・文化人などからのメッセージが寄せられ冊子にまとめられ当日配布されました。 |
| センター通信の再発行に期待します】・・・・・・藤原義隆(元市内小学校) 18年ぶりに再刊されたことを知り、当時この「通信」を教室実践のよりどころとしていたのでとても喜んでいます。私は16年前に退職しましたが、当時から京都市教委は「算数での水道方式は禁止」など現場に圧力をかけてきましたが、子どもと父母のことを第一義的に考え日刊の学級通信や、週刊の学年通信を出すなど実践を通しての「抵抗」をねばり強くやりました。そうした実践の理論的支えになったのが「通信」を含めた教育センターの存在でした。今の現場は、もっと大変だと聞いていますが、原則的な理論装備と柔軟な視点での実践がこの閉塞を突破する“武器”だと思います。この「通信」や京都で唯一の教育専門誌「ひろば」が現場の人に読まれ、ささやかでも励ましになることを願いおおいに期待しています。 |
|
| 京都教育センター ホームページは http://www.kyoto-kyoiku.com
・京都教育センター事務局や公開研究会の活動をはじめ、「季刊 ひろば・京都の教育」、教育センター年報、冬季研究集会、教育基本法に関する様々な資料など、多彩な情報を提供しています。 |