 |
●京都教育センター通信 復刊第 1号 (2006.5.1発行) |
一九八八年以来休刊状態になっていた「センター通信」が復活発行されることになりました。教育センターの活動が現場に見えにくかったり、疎遠になっている側面があったりします。それではいけないのは当然です。疎遠にならないように少しでも努力していきましょうという趣旨でセンター「通信」を再発行することにいたしました。
京都教育センターは1960年に「平和と民主主義の教育」の確立を目指して設立されました。その後40数年、民主運動に理論的問題をふくめて前進させようと努力を続けてきました。
現在の日本社会に目を向けてみましょう。新自由主義の政策が厳しく進行しています。競争が熾烈になり、「個」のみの自己責任が問われ孤立化させられています。「集団性」が生まれにくくなっています。「維持不可能」の社会になってきて展望が見えにくくなっています。それは、例えば出生率の低下などを含む人口問題にもみられます。
社会不安、「安全の不安」などが強化されて監視の網が張られています。「安心のファシズム」といわれるような社会にもなりつつあります。自由が制限されて24時間監視下に置かれているといえるでしょう。意見も言わず、周りに同調するような風潮が蔓延しつつあります。ニヒリズムの進行といえるでしょう。「生きたまま死んでいく」空しい生き方を強要されているといってもよいでしょう。
しかし、どんなに苦しくてもその中で人間らしさを求めて多くの人びとの努力が営々と続けられています。その底流に人類の良心が息づいています。苦悩の中で実践している仲間たちの実践を出しあい交流を深めて、教訓を共有しあいましょう。きらりと光る宝を見いだし、元気を出して頑張りましょう。
今日の学校現場は、「やらされる」多忙化で「創り出す」楽しみ感は希薄です。教育センターはみなさん方の実践的、財政的支えで活動をしています。昨秋事務局長に就任以来、閉塞した現場に何で「お役に立てるか」を考え続け、今年度は「公開研究会」(4面参照)とこの「通信」の復刊(月一回)を企画しました。
現場で苦労されているみなさんの参加と投稿[毎回「私の授業」・「私のクラス」を連載]をお願いします。
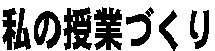
私は、日本の教育は世界に誇る二つの宝を持っていると思っています。一つは、江戸時代に寺子屋でつくりあげられた「読み・書き・計算」の技であり、もう一つは日本の教師が明治以来百余年間、営々と築き伝えあってきた一斉授業の技です。これらは庶民の中に「均質で広範な学力」を形成し、明治維新の文明開化や戦後の復興の力となりました。これらの力を保障してきたのが、学校教育における一斉授業の技なのです。私は、「生きる力・新しい学力観」を打ち出したこの十年間は「授業崩壊の十年」であったと考えています。そのもとで、子どもたちがばらばらにされた「がさつな授業」を打ち砕き、「凛々しい個別化」と「豊かな交流」が保障される一斉授業を復権、再生しなければなりません。そのためには、二つの視点が大切です。一つは、学習評価を授業の中に位置づけることです。これは到達度評価で授業を変えるという視点で研究を深めたいと思います。もう一つは、ヴィツキーの「発達の最近接領域」の考えで模倣と共同の観点から一斉授業を吟味し、班活動の意味や豊かな交流の教育的意義を検証します。
教師は自分のクラスを分析し、学びの共同がクラスに実現しているのか、学力による差別の荒野なのかを見てとる力が必要です。子どもが荒れるのは教室が差別の荒野になっている時で、いきがっていても明らかに弱者である荒れ、傷ついた子になおも塩をなすりつけるような授業をしていないか。本来、子どもにとっては授業ほど心地よいものはない。なぜなら学習行為は褒められることに満々いる。子どもは授業以外ではほとんど褒められることがなく、いつも親の小言、教師の小言・注意ばかりの生活を強いられている。 私の授業づくりプランをまとめると次のようになります。
1.教師の教え:教師の語りと模倣の準備
2.頼りになるのは「お隣さん」:共同と多様な模倣(子ども語による模倣)
3.凛々しい個別化:形成評価で学習の通過点を個々に把握
4.豊かな交流:学力の社会性に気づかせ、集団思考により深い認識へ
5.「今日学んだこと」:学習したことを文章化し発表する。友だちのまとめと教師の評価を聞き、自分のまとめを比較し深める。
私は、「板書、発問、ノート指導」を一斉授業の「三種の神器」と位置づけています。その技を子どもたちに一生の宝として身につけさせるとともに、それを通して「読み・書き・話す・聞く・考える」の学習能力を活性化させ、学習規律を高める授業をめざしています。
前任校の新林小学校での6年間の実践から学んだことを、次の三冊の本にまとめさせていただきましたのでご参照下さい。
(子どもの未来社発行) ・『学力づくりで学校を変える』 ・『学力づくりで子どもが変わる』 ・『一斉授業の復権』
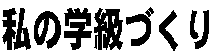
伸治は、毎日のようにけんかをしました。私は、とにかくわけを聞いて、みんなに報告しました。勉強が分からないとおもしろくない。友だちに認めてほしいのに否定されているように感じると暴れる。暴力はもちろん悪いことだけれども、伸治の否定的な行動の裏にある願いはみんなと同じであることを伝えていきました。 6年の陸上競技会や駅伝大会などの競争が伸治の心を再び荒れさせました。勉強よりも運動を生きがいにしてきた伸治が代表になれなかったのです。問題行動について私と話したとき、はじめは、つっぱっていましたが、「オレなんか何をしてもあかん。死にたい。」と大泣きしてきました。
| 自分をみつめる ぼくは、このごろ悪すぎる。ぼくは正直言うと悪いことをしている。運動会のころからなんかイヤなことがいっぱいあって、つい悪いことをしてしまう。 ぼくは、陸上競技会のリレーに出たかった。でも、ぼくのクラスでは速い人がいっぱいいるし、ぼくは出られなかった。ぼくは、しかたがないとしか思えなかった。ぼくはガマンした。でも、めっちゃくちゃくやしかった。 だから、なんかいやな気分で、すぐ悪いことをしています。「やったらアカン」と思っても、自分を止められない。 でも、友だちと遊ぶのは楽しい。中間、昼休みは、みんなとサッカーをして、めっちゃ楽しい。 ぼくは、友だちがいてよかったと思う。ぼくは、もし友だちがいなかったら何もできないと思う。 |
しばらくして、暴力事件を起こして学校を飛び出した伸治に、数人の男子が校門まで走って行って、声をかけていました。心配して友だちと家まで行った女子もいました。みんながすすんで手紙を書いてくれました。
| 伸治へ 伸治、おまえ勉強わからんかったらきいてくれよ。できるだけのことはするから。このままわからんかったら、学校なんてメッチャおもんなくなるで。 オレだって、何回かわからんときがあったけど、いろんな人にきいてわかるようになって、それで今、学校が楽しいねん。勉強なんて、ちょっとがんばればすぐできるで。 あと、中間休みとかにドッチに来いよ。おまえがいいひんかったら、オレはなんかおもしろくないやんけ。 でも、来てもあんまりケンカとかすんなよ。おまえをとめるのが一番ムズカシイんやって。 まあ、がまんできんときは、柱でもけっとけ。 |
5年のはじめ、けんかを見ても我関せず!だった良吉は、リーダーとして大きく成長しました。みんなの重いが伸治に通じて、暴力はなくなりました。
| 教育基本法改悪「待った!」緊急集会 5月27日(土) 13:30 教文センター302号 問題提起:野中一也 / 京教組・国会議員・青年の報告 |
| 【教育センター資料室だより】 教育センター[教育会館別館2F]には付属した資料室があります。以下の資料の他に戦後の教育関係出版物や資料、教職員組合運動資料などが整理して収蔵されています。 ・センター「会報」「通信」(1960~88) ・「教育を国民の手で」(77~87) ・「センター年報」(89~06年分) ・教育誌「教育運動」(創刊~100号) ・教育誌「ひろば」(101~146号) だれでもご利用できますが、事前にご連絡下さい。(月・水が原則) 資料室担当 淵田 悌二 |
|
 1960年に設立された京都教育センターは、その名称を単なる「**教育研究所」とされていません。教育活動・教育実践・教育研究は教育運動と共に発展することから、この名称にされました。発足当時から、京都教育研究集会に参加し共同して研究を進めていくことを目指してきました。また、「季刊・教育運動誌」を100号まで発行し、続いてより幅広い人々と共にとの願いから名称のみならず内容も変えて「京都の教育・季刊・ひろば」として、続けています。「ひろば」は、「人々との語り合い」の素材としてとの願いも込めて、年間会費制度¥2960(含郵送代)をとっています。憲法・教育基本法を「改訂」されかねない状況の今日、ぜひ知人友人と共に、読者を広めながら、ご購読していただきますようにお願い致します。 京都教育センター 1960年に設立された京都教育センターは、その名称を単なる「**教育研究所」とされていません。教育活動・教育実践・教育研究は教育運動と共に発展することから、この名称にされました。発足当時から、京都教育研究集会に参加し共同して研究を進めていくことを目指してきました。また、「季刊・教育運動誌」を100号まで発行し、続いてより幅広い人々と共にとの願いから名称のみならず内容も変えて「京都の教育・季刊・ひろば」として、続けています。「ひろば」は、「人々との語り合い」の素材としてとの願いも込めて、年間会費制度¥2960(含郵送代)をとっています。憲法・教育基本法を「改訂」されかねない状況の今日、ぜひ知人友人と共に、読者を広めながら、ご購読していただきますようにお願い致します。 京都教育センター
 146号発売中(2006年5月1日発行) 146号発売中(2006年5月1日発行)○特集1・・・・ニート・フリーター問題と格差社会--働くこと・生きること ○特集2・・・・教育を受ける権利と教育改革のゆくえ ○発 行・・・・春(5月)、夏(8月)、秋(11月)、冬(2月)の年4回です。 ○年間会費・・・・「ひろば・京都の教育」は年間会費制です。年間会費は2,960円です。年間会費の支払いは年に一回の郵便自動払込振替も可能です。 ○申し込み・・・・京都教育センターまで電話またはファックス、メールなどでお申し込み下さい。 |
| 京都教育センター ホームページは http://www.kyoto-kyoiku.com
・京都教育センター事務局や公開研究会の活動をはじめ、「季刊 ひろば・京都の教育」、教育センター年報、冬季研究集会、教育基本法に関する様々な資料など、多彩な情報を提供しています。 |