| 事務局 | 2014年度年報目次 |
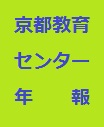 |
第2部 教育センターと各研究会の年間活動 発達問題研究会 2014年度活動のまとめ 大平 勲(発達問題研究会事務局) |
|
[経過報告] 本研究会は、センター設立時より発達問題にかかわる系統的な研究活動の実績をもつが、2011年度、2013年度の2年間は研究会代表や事務局長が他の任務に忙殺されたこともあり、実質的に休会を余儀なくされた。しかし、この伝統ある研究会の灯を消してはならないとの思いから代表や事務局担当の代行者を配置し、昨年度から新たなメンバーも迎えて活動を再開した。再開2年目の今年度は、久しぶりに公開研究会を開催することができたが、体制の不十分さから恒常的な活動を展開することができないままに推移した。 事務局会議は2回開催した。 (1) 4月12日:公開研究会にむけての企画、準備 (2)10月11日:センター研分科会の企画についての協議 Ⅰ.公開研究会(5月17日):生指研との共催 教文センター101号室 45人参加 ・あいさつ:高垣忠一郎(京都教育センター代表) [講演]「青少年の立ち直り支援に関わって」 藤木祥史(全生研全国委員) 藤木氏は乙訓の各中学校現場で退職までの38年間、その学校で最も課題を持つ生徒の担任として奮闘されてきた。退職後は京都府府民生活部青少年課ユースアシスト支援コーディネーターとして、非行少年などの立ち直り、就労支援などの活動に従事し、乙訓や山城、口丹などの地域で少年・少女自立支援の会の組織化に尽力されている。 ~講演要旨~ ・「ユースアシスト」はなぜ立ち上げられたのか?私が関わるに至ったのはなぜか。 ・世間一般には「非行」=取締り(警察の仕事)という認識だが、行政や議員等は必ずしもそうではない ・非行の両価値性:「親からの行動的自立」「親からの精神的自立」 ・支援ケースの特徴:①立ち直りの意思はあるが、既存の機関では対応できない ②立ち直りの意思がない。関係の構築から支援が始まる。 ③関係機関にかかっていない少年、出会いから関係構築へ いずれの場合も、立ち直る困難さに負けて努力を放棄する、立ち直りの意思さえ否定する少年たち。 ・支援の進行において重視すること ① あきらめずに支援を継続すること ② 具体的援助によって応答関係を築くこと ③ 非行の要因になったことを的確に分析すること ④ 要因となった関係性の改善に一緒に取り組むこと ・具体的な事例から総合的な報告 ① 一般的個別事例として母子家庭における女子について ② チームポリシーに沿った事例 ・「非行問題」を抱えながら「悩まない学校」が増えている:ゼロトレランスと形式指導 「非行問題」はあってはならないが、なくて普通なのか? [報告1]「高校の現状と課題―特別支援教育から高校中退問題を考える」 谷口藤雄(府立高校特別支援・進路支援教員、福知山高校三和分校) ~報告要旨~ ・高校生をとりまく状況:「競争と選別」が進行するもとで危機的な状況、よい中学生の青田狩り、休・退学生徒の拡大、勉強時間の二分化(勉強しない生徒の割合は京都がトップ) ・高校に進学してくる生徒で「特別な教育的ニーズ」を要する生徒の増大(LD、ADHD、アスペルガー、自閉症、非行、不登校、学力不振、難病、貧困など)。障害時教育の経験をもたない高校教員にとってこうした生徒への対応は困難を極める。高校には特別支援学級がない。支援コーディネーターとしての私の役割。 ・中退問題:京都の公立高校のこの5年間の退学率は5.9%(全日制)、15%(定時制)。定時制では入学生徒の約半数が退学していく。退学の原因として、「高1ギャップ」(学業不適応、進路変更、家庭事情、欠席時数問題)、経済的理由は無償化で激減。 ・中学校支援学級卒業生の進路:高校進学率は府全体で45.9%(北部69.4%、南部32.4%) 何の手立てもないままに社会に放り出されてどうなるのか(支援が必要)。 ・中高連携と関係機関との繋ぎ:退学率の高い高1での支援が重要であるが、府教委の「特色化路線」制度により進学先の多様化、広域化が支援を困難に。 ・高校での取り組み:①特別支援教育の制度化(義務制で2007年から)を受けて ②先進的な取り組み事例を組織的取り組みに。北部での私の関わり。 ・社会的不適応生徒の事例から:自己評価(自己肯定感)と価値観の歪みが非行問題などの引き金に。この問題や歪みをまず是正するかが課題。 ・価値感の歪み:家庭の養育過程で抜け落ちたもの。主観的、被害者的、白黒思考、言語問題 ・今、学校現場に求められること(中退をなくすために) 「高1ショック」を和らげる中高の連携強化を、関係機関との連携、など [報告2]「中学生逮捕問題から『学警連携』を考える」 大平 勲(立命館・京都橘大学非常勤講師) ~報告要旨~ 1.「中学生逮捕事件(2014.1)」経過 生徒・卒業生はすべて男子 〈事件概要〉①校舎内自転車の4人が注意した6人の教師に暴行、頸椎捻挫・打撲。(11/5) ②校外で4人の中学生と2人の卒業生が高1生徒をゴルフクラブで暴行。(11/15) ③ 給食中に1人が教師に小黒板を投げつける。(11/19) ④給食中に外で買った「たこやき」を食べ、注意した教師3人に暴行。(11/22) ※学校側が警察に「被害届」提出、受理(教師3人の診断書添えて) 〈警察対応〉・3年A(12/5:逮捕・補導)・2年B(12/12:逮捕・補導)・3年C、2年D(12/18:逮捕・補導)・3年E(1/7:補導)校外事件に関与なしで不逮捕・卒業生2人:18歳土木作業員Fと高3生徒G(1/8:逮捕・補導) 逮捕された6人は田辺署で期限まで拘留、取り調べ後「鑑別所」へ、約一ヶ月後に「少年審判」により「保護観察」処分 2.I中学校:・京都南部の町(人口約1万人)唯一の公立中学校:各学年3クラス ・もともと素直な生徒の多い牧歌的な学校→30年ほど前から宅地造成の転校生増で荒れ出す ・私(大平)の母校、新採校(6年勤務→組合専従に):生まれ育ち今も住む ・N教育長(元I中校長)、O校長(元I中生指主任) ・良心的な教師もいるが多くは30~40代:ゼロトレランスの傾向で問題生徒への挑発的な対応も「殴れるものなら殴ってみろ」 3.マスコミ報道と住民の関心 (1)事件概要が報道(1/9)「京都」「洛南タイムス」は学校名も出る (2)保護者・住民の関心:「教育長対応への不満」(1/16:保護者説明会) :「“苦汁の決断”支持」(住民の多数、遅すぎた?)〈投書〉 (3)洛南タイムス投書相次ぐ:賛否両論(全て匿名)→実名投書(大平) 4.卒業生Fへの支援対応 ・当初、弁護士(国選)も「少年院送致」を示唆 ・母親より大平に相談あり(1/27) ・藤木氏他の「立ち直り支援メンバー」に相談・協議(1/27) ・「ユースアシスト」訪問、支援要請(母親、大平→藤木氏:受諾) ・鑑別所への面会(藤木氏数回)、家裁調査官との面談(藤木氏、大平) ・「保護観察処分」で自宅へ(藤木氏、大平面談激励) ・就労支援(藤木氏) 5.課題 ・「少年法改正」の動向 ・「立ち直り支援」の重要性 (藤木講演) ・「学警連携」問題 [討論] ・学警連携の状況は進んでおり深刻だ。アシストのとりくみは学校でこそなされるべきである。アシスト組織と警察余の関係は?(研究者) ・非行少年の立ち直り支援を行っている。彼が言うには中学時代に声をかけた先生に「お~元気にしとるぞ-」と返事した時、その言い方は何だと言われ、相談室に呼ばれた。(退職教員) ・逮捕された中学生に小学生のころ関わったが、発達障害的な課題もあり、管理的な指導に慎重であるべきだと実感していた。(小学校教員) ・若い先生は課題生徒の見方を学ぶ機会が少ない。ベテランは経験した実践を継承すべき。(中学校教員) [感想文から] ・今年度採用になりましたが、昨年までの2年間講師として中学2,3年を担任していました。先輩の先生から、さまざまな考え方や指導法を教えていただいたお蔭で生徒と接し、私自身の成長にも繋がりました。管制の研修よりも先輩先生の話を聞く方が参考になり、自分の知識として取り入れていきたいと思っています。今日は貴重なお話をお聞きしてありがとうございます。 ・藤木先生のお話で学校が関係機関に「丸投げ」している現状もあると話されましたが、私は将来小学校の先生をめざしているので、学校の中でどうやって支援の機構を豊かにしていくのか考えたいと思いました。その子の最も近くにいる教師が一番の支援者になっても守り続けることが大事だと感じました。 ・いい研究会でした。またやってください。我々のあきらめない努力がまだ足りないことを教えられました。私は、大学で教えてきたことを生かして社会教育の立場から「ひきこもり」研究の勉強会を作りつつあります。ご支援願えればありがたいです。 ・ソーシャルワーカーとして教育現場に身を置いていますが、この種の学習会ではいつも門外漢で勉強になることが多いです。子どもと直接に関わる教員が働きやすく、子どもたちが学びやすい社や家庭環境を調整していくのがSSWの役割ですので現場教職員とは違って少し引いた立場から眺める場面が多くなりますが、これからもよろしく願いします。高校でもSSWの導入が必要との谷口先生のお話がありましたが、小中学校でも一部ではなくすべての学校に必要な仕事だと思います。 Ⅱ.今後の活動指針 (1)従前から研究会として確認してきた基本点 ① 発達理論に基づいているか ② 社会的、教育的情勢を反映しているか ③ 子どもたちの実態に基づいているか ④ 教育現場での課題につながっているか ⑤ 研究の成果を活用する展望があるか (2)基本点に基づく活動 ① 発達理論についての学習を深める ② 社会・教育情勢についての議論を深める ③ 子どもたちをめぐる情勢や子どもの実態についての理解を深める ④ 学校現場との交流を重視するために実践レポートを掘り起こす ⑤ 研究の成果を記録化して冊子作成やその普及に努める (3)研究体制の確立 ① 運営委員会議の定例化 ② 公開研究会の開催(2回)、案内、成果の発信 ③ 研究会員、事務局メンバーの補強を図る (4)研究会組織体制 ・代表:築山崇(代行 浅井定雄) ・事務局長:西浦秀通(代行 大平勲) ・運営委員:北村彰 谷進太郎 谷口藤雄 中山善行 和気徹 |
||
|