| 事務局 | 2014年度年報目次 |
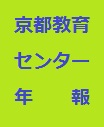 |
第2部 教育センターと各研究会の年間活動 地方教育行政研究会・2014年度の活動のまとめ 我妻秀範(地方教育行政研究会事務局) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 はじめに この間、安倍内閣のもとで集団的自衛権の行使容認の閣議決定(2014年7月1日)、特定秘密保護法の施行(2014年12月10日)、「武器輸出三原則」の緩和(2014年4月1日)など、日本国憲法と戦後日本が堅持してきた平和主義を根本から否定する動きが加速している。 これと一体に新自由主義と新国家主義に基づく「教育改革」が急テンポで推進されている。この動きはグローバル化した世界で活躍する企業戦士と戦争する国家をになう人づくりを目指したものである。 私たちには、こうした政策動向をふまえ、憲法を守り発展させる運動、民主的な教育行政と教育内容、子どもたちの学習権保障の取り組みを、今まで以上に旺盛に展開していく必要がある。しかし、後述するように本研究会の体制上の弱点から情勢と課題に見合う研究活動を展開することができなかった。以下、今年度の取り組みを総括しながら課題を明らかにしたい。 2 2014年度の主な取り組み〜概要と課題 (1)第1回京教組・地教行研合同学習会 ア)概要 ・2014年5月18日(土)、京都市職員会館「かもがわ」にて開催 ・「安倍『教育再生』とは何か〜政権存続の突破口としての教育改革」と題して中田康彦氏(一橋大学)が講演。30数名が参加した。 ・その後報告①として、我妻(研究会事務局)が「今日の教科書問題と私たちの課題」と題して、この間の教科書問題をめぐる動き、文科省「教科書改革実行プラン」の概要とその具体化、沖縄県竹富町での教科書採択問題、大阪府教委などの実教出版「日本史A」教科書の採択妨害問題について報告した。 ・さらに報告②として、葉狩(研究会事務局)が「『道徳の教科化』問題に向き合う」として、自身の「道徳教育観」をふり返りつつ、「今後の道徳教育の改善・充実方策について(報告)」(道徳教育の充実に関する懇談会 平成25年12月26日)の問題点を批判的に検討した。 イ)中田講演の概要(以下は当日の講演レジュメの項目)
(2)京都教育センター研究集会 ・2014年12月21日(日)に開催。17名が参加。テーマは「小中一貫校問題と学校統廃合」 報告者は以下の通り。なお報告・討論の概要は本誌に掲載したので参考にされたい。 (1)基調報告 松岡寛(京教組) (2)京都市内の状況 榎本知子(京都市教組) (3)東山区泉小中学校の状況 人見吉春(退職教員。元京都市教組) (4)発達の視点から見た小中一貫校 藤本文朗(滋賀大学名誉教授) (5)南丹市における学校統廃合 塩貝直樹・小寺功彦(船井北桑田教組) (3)活動総括 ・教育センター事務局が主催する連続学習会との重複を避けるために同学習会終了後に京教組・地教行研合同学習会を設定しようとしたが、事務局体制の不十分さもあって開催できず、結局5月に1 回開催しただけに終わった。 ・事務局会議も数回の開催に終わり、継続的な研究活動を行うことができなかった。特にこれまで事務局を実質的に支えてきた新谷剛氏(元京教組執行委員)が死去されたことは、本研究会にとって大きな痛手であった。また、事務局長交代に伴って、引き継ぎがスムーズに行かなかったなどの弱点を反省して、新年度の活動を作り直していくことを意識的にすすめたい。 3 2015年度の活動方針 (1)教育行政をめぐる経過 以下は2013年末から2014年末までの「教育をめぐる動き」を整理した。ここから教育行政の全国的な展開と課題を探りたい。
以上が2013年末からの教育をめぐる状況である。これらは①教育行政改革、②教育財政改革(学級規模、学校統廃合)、③学制改革(小中一貫校など)、④教員養成・教員免許制度の改革、⑤教科書制度改革、⑥道徳の教科化などにおいて具体化されている。 その一方、学校現場では、深刻な長時間労働(OECD)、精神疾患で退職や休職を余儀なくされる教員の増加(文科省調査)、先進国で最低の教育費支出割合(OECD)による劣悪な教育条件などの問題が放置されている。急テンポで進められる安上がりの「教育改革」が教職員や子どもに深刻な矛盾を引き起こしていると言わなければならない。また、京都府内では高校入試制度の改変、公立の中高一貫校の設置、学校統廃合と小中一貫校の導入などが急テンポで進められている。 (2)基本的な考え方 以上をふまえ、本研究会は次のような立場で研究を進める。 ・2015年度は「反動的な教育改革とどうたたかうか」を研究テーマに掲げ、研究の一層の発展をめざす。 ・現在進められている「教育改革」のねらいと問題点を明らかにしてする。 ・教育行政や教育条件に関わって地域や学校現場で起きている問題を明らかにする。 ・すべての子どもの人間らしい成長・発達を保障する教育を願う立場から、「子どもたち、父母、教職員の願いをふまえた教育条件」を整備する計画の策定を強く求めていく。 ・京都教職員組合との「合同学習会」を重視する。 (3)研究会の組織確立 ・教職員組合としての課題意識と、行政研事務局員の課題(研究テーマ)を出し合いながら学習会を開催する。 ・学習会の案内ビラを作成して、組合員や各団体等に配布する。その際、各分野の研究者や教育運動を進めている方々、青年教職員の参加を重視する。 ・研究会会員(登録者)へのメール配信や各支部教組への働きかけをできるだけ早く(1か月以上前)行ない、参加組織・集約を強める。 ・学習会の内容等を整理して「発信」する取り組みを重視する。 ・教育学にとどまらず法律学・政治学・経済学などを専門とする研究者に協力を依頼する。あわせて事務局員の増員をはかる。 ・事務局会議を定期的に開催して情勢と問題意識の共有化をはかる。 (4)おもな研究課題 ア)教育行政と学校 ・安倍「教育改革」の批判・検討 ・教育振興基本計画の批判・検討 ・教育委員会制度、父母・住民の参加と共同 ・学校の自主性・自立性確保と教育課程行政 イ)学制に関わって ・小中一貫教育や公立の小中一貫校について ウ)教育財政・教育条件をめぐって ・教職員定数・配置と学級定数 ・教育予算・父母の教育費負担 ・学校統廃合問題 エ)教員制度をめぐって ・教員養成・採用・研修をめぐる問題。とくに教員免許更新制について ・教員評価制度、新たな職(主幹教諭、指導教諭など)や賃金制度 オ)子どもの学習権保障 ・子どもの貧困、生活保護・就学援助制度 ・土曜活用問題 (5)事務局体制 代表:市川哲(明治国際医療大学名誉教授) 事務局長:我妻秀範 事務局員 大西真樹男、奥村久美子、田中正浩、葉狩宅也、本田久美子 会員 東 辰也、新井秀明、石井拓児、磯村篤範、井上英之、射場 隆、植田健男、大前哲彦、大和田弘、梶川 憲、佐野正彦、末富 芳、竹山幸夫、野中一也、藤本敦夫、山本重雄、吉岡真佐樹、淀川雅也 *なお、長年、本研究会の会員としてお世話になった柳ヶ瀬孝三先生(立命館大学名誉教授)が2015年1月15日に死去されました。心からご冥福をお祈りいたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|