| 事務局 | 2011年度年報もくじ |
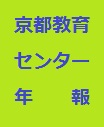 |
地域子育て・教育ネットワーク京都 《2011年度活動のまとめ》 細田俊史(京都市教組) |
|
2011年度の活動報告 |
||
■毎月の交流会を開催 |
||
毎月一回、京都教育文化センターで交流会を開催してきた。交流会は、参加団体からの報告を交流することを中心にし、またテーマを決めて学習をしたり、集会の企画について協議してきた。交流会には多い時には20名を超える参加者がありましたが、参加が少ない時もあった。 地域の各団体からの様々な取り組みをお互いに学び合い、刺激し合うことがねらいなので、「参加して良かった。」と思えるような交流会にしていくことが必要である。 ◇学習や協議したテーマ◇ 4月 東日本大震災支援・国語教科書はどう変わったのか 5月 小中一貫校「東山開睛館」 6月 小中一貫校「東山開睛館」・中学校歴史教科書の採択 7月 <東山開睛館見学会を実施> 8月 東山開睛館見学会報告・教育シンポジウム 9月 <教育シンポジウムに参加> 10月 ネットワーク主催の教育集会について 11月 ネットワーク主催の教育集会について 12月 子どもの貧困問題を考えるつどいの企画について 1月 子どもの貧困問題を考えるつどいの企画について |
||
■小中一貫校『東山開睛館』の施設見学会 |
||
交流会で話題になった『東山開睛館』を参加団体のメンバーで訪問し、学校長・教頭に校舎案内をしていただき説明を受けた。 美しい外観・幅の広い廊下・普通の学校には無い中学校までの自校給食の施設・給食運搬用エレベーター・広いランチルーム・充実した図書館(メディアルーム)・横幅が50cm広い教室や、問題の指摘されてきた地下2階の体育館などを見学しました。中庭の小学校用の遊具が少ないこと、学校敷地内に草木がほとんどないこと、地下からの避難経路には不安があることなど問題点も見えてきた見学会となった。『東山開睛館』は、施設面と教員配置で手厚く条件を整えている面と、狭い敷地に建設しているため条件整備が不十分な面があることが明らかになった(詳しくは「通信no10」をご覧ください。) |
||
■『子どもと学校教育を考えるシンポジウム』の開催 |
||
9月17日(土)に本能寺会館において、「地域子育て・教育ネットワーク京都」と京都市教職員組合が主催して行われた。パネラーは市内小学校保護者・市内小学校教員・市内中学校教員・左京子育てネットワークの4名で、京都教育センターの本田さんにコーディネーターをお願いした。市内の小中学校の教職員や父母・市民団体の方々を入れて56名の方が参加があった。 シンポジウムの前に京都市教組が、「告発!京都市の格差教育」として京都市教委が「モデル校」としている豪華主義校舎の統合校と、放置されたままになっている「普通」の学校のスライドショーを行った。スライドに映された学校間「格差」に参加者一同が目を見張り、驚きの声が上がった。(後日、京都市教組はスライドの内容を充実させてDVDを作成した。)シンポジウムのパネラーの発言だけでなく、会場の参加者からは京都市の教育に対する疑問や怒りの声が次々とあがった。 こんな「格差教育」は許せない、子どもたちの教育を良くするために父母・市民と教職員が手を携えて運動を進めていこうという思いがあふれた集会となった。 |
||
■教育集会の企画 |
||
現代の子どもに関わる諸問題についての教育集会を企画しようと、交流会で協議を重ねて、子どもの貧困問題をメインテーマとすることになりました。 格差と貧困の広がりで経済的な貧困が広がり、その影響が子どもたちに及んでいます。さらに、子どもたちが子ども時代に経験すべき遊びなどの文化的な体験がなくなってきていることから、子どもの発達に問題が生じていることが懸念されています。こうしたことを学んでいこうという企画です。 3月25日(日)午後に、スクールソーシャルワーカーの仙田富一さん(元児童相談所所員)の講演と子どもの貧困問題についての交流会を開催することが決まっています。 |
||
■通信の発行 |
||
交流会議の内容や、各地域・団体の活動案内を掲載してきた「通信」を作成し、参加している各団体に送っています。(通信の配布を希望される方は、京都市教組までご連絡ください。【075-771-9171】 |
||
|
| 事務局 | 2011年度年報もくじ |