| 事務局 | 2011年度年報もくじ |
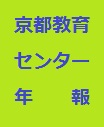 |
教科教育研究会・国語部会 《2011年度活動のまとめ》 浅尾紘也(教科教育研究会・国語部会) |
|
1.活動の概要 |
||
今年度の活動として、以下の具体的な活動を進めた。 ① 「国語部通信」の発行 今年度の「国語部通信」は、 4 月 第50号 第2回連続学習会まとめ 「説明文教育」研究会のまとめ *説明文教育についてこれまでのつみあげと今後論議すべき課題について 5 月 第51号 第3回連続学習会まとめ 「文学教育」研究会のまとめ *文学教育についてこれまでのつみあげと今後論議すべき課題について 6 月 第52号 第4回連続学習会まとめ 「作文教育」研究会のまとめ *作文教育についてこれまでのつみあげと今後論議すべき課題について 1 月 第53号 2011センター研国語分科会まとめ 国語教育の危機、課題をどうとらえ、私たちの実践をどう創造していくのか 〜国語分科会で、何が提起され、何が論議となったか〜 *国語分科会での提起と討議の内容と論議のまとめ。 3 月 第54号 2010国語部会活動のまとめ *今年度の国語部会の活動のまとめ。今後の課題も提起。 を発行してきた。 今年の国語部会の活動のテーマは、これまでの京都教研国語分科会そして京都教育センター国語部会が積み上げてきた実践的理論的成果をどうまとめて現代的課題をふまえて再構築し、現場での国語教育の空洞化・崩壊ともいうべき状況をどう乗り越えていくのかという点であり、そのとりくみを広く提起していく通信活動であった。 ②国語教育連続学習会の開催 これまでの活動の中で、課題として明らかになった、国語教育の理論と実践の再構築をめざすとりくみについての論議を深め、混とんとしている国語科指導の現状をのりこえ、 だれにでもできる豊かでたしかな国語教育の理論と実践を創造していくためと、全国教研(教育のつどい)国語分科会から提起されている、「国語分科会・20年のまとめ」の提起についての論議要請に応えて、国語教育の各分野で、これまで何が、どのように論議され、何が課題として残っているかを深めることをめざしての「国語教育連続学習会」を昨年度から今年度の活動として続けていった。 日程としては、 2010年度 2月 言語の学習 3月 説明文教育 2011年度 5月 文学教育 6月 作文教育 としてとりくみを進めた。 論議としては、全国教研・国語分科会の提起と論議のまとめについて深めたのだが、その論議は、京都の教研活動の集大成としての「国語教育・三分野説」を再検討していくためとしても意味を持つものであったと言える。そして、さらにそれがセンター研究集会の国語分科会でも深めることとした。 さらにその討議が、今後の京都での国語教育研究・実践の指針として機能していくことをめざしたい。 ③センター研/国語教育分科会の開催 1月のセンター研究集会では、今年も国語部会が中心となる分科会(国語分科会)を開催し、提起と討議を深めた。 昨年から提起してきたように、今年の最大の課題と問題点は、改定学習指導要領・国語科の本格実施が始まり、具体的なものとなる「国語教育の危機」に対して、私たちの最大の課題は、実践をどのように進めていくのか、それを理論的にも実践的にも明確にしていくことである。 この課題に応える分科会としていくために、昨年度の児童言語研究会の委員長である森慎氏を招いての「国語教育、その課題と私たちの課題〜児言研の研究成果をふまえて〜」と題しての国語教育の全体についての講演・提起、さらに「認識と論理を育てる 説明文教育の授業」と題しての説明文教育の授業をふまえた実践の提起につづいて、とりくんできた国語教育連続学習会のまとめ討議、さらに「言語の学習」と「文学教育」についての討議を深めるものとした。 今年度の参加は、10名の参加であったが、論議が深めた。 *詳細については、センター研・分科会報告を参照 今後の国語部会としての活動課題は、さらに、今年度の活動をさらに深め、各分野の内容についての論議をすすめ、国語教育の危機を乗り越える理論と実践を創造していくことである。 |
||
2.国語部会が提起しづけてきたことと今後の課題 |
||
京都教育センター国語部会は、京都の国語教育研究運動のひとつの集約点として、京都教研国語分科会での提起と討議、そして国語部会としてのとりくみをすすめて、これまでの実践的理論的な成果を明らかにし、それをふまえて京都の国語教育研究運動についての提起をし、国語教育の空洞化・崩壊の状況を乗り越えていくことである。 そのためには、そのことをしっかりと意識した活動にとりくんでいくことが大切である。 それをめざしての今後のとりくみをすすめていきたい。 |
||
|
| 事務局 | 2011年度年報もくじ |