| 事務局 | 2011年度年報もくじ |
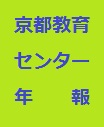 |
発達問題研究会 《2011年度活動のまとめ》 浅井定雄(発達問題研究会事務局) |
|
Ⅰ、2011年の活動経過 |
||
発達問題研究会は、再建後、下記のような経過で研究活動に取り組んできた。 ①2003年度 インターネットや情報機器・道具の普及などと併せて「コンピュータ社会に生きる子どもたちを取り巻く環境」をテーマに検討を深めることができた。 ②2004年度 「インターネット時代と子どもたちの認識・発達」をテーマに取り組んだ。 ③2005年度 「ケータイ文化と子どもたちの発達環境」をテーマに、ケータイをめぐる子ども達の実態について検討した。 ④2006年度 「子どもたちの発達課題と地域環境」をテーマに、地域の中で育つ子どもの姿に焦点をあてて取り組みを進めた。 ⑤2007年度 「子どもの発達と自然との関わり」をテーマに、引き続き地域の自然の中で育つ子どもの姿についての検討を深めた。 ⑦2008年度 「人間と自然との相互性」をテーマに理論的な検討に取り組んだ。 ⑧2009年度 「人の発達と進化」をテーマに議論を継続した。 ⑨2010年度 「子ども観を深める」をテーマに設定し、地域・集団・自然をキーワードに「自然の生き物としてのヒトと子ども」などの検討課題も含めて討論を行い、その後も、認識の発達も含めての「子どもの発達と科学的認識」に関する研究・討議の必要性などから、議論を継続した。 ~2011年度~ 「人間発達の土壌としての学校・地域」をテーマに、学校・地域で子育てに関わる取り組みについての実践報告をもとに検討を進めた。 2011度の活動の記録は、以下の通りである。 1月29日(土):運営委員会(2010年度の取り組みのまとめについて) 3月 5日(土):運営委員会(2011年度の取り組みについて) 6月 4日(土):運営委員会(6月公開研究会に向けて) 6月25日(土):発達問題研究会公開研究会(「学校が地域をつくり、地域が学校をつくる」吉田武彦先生報告:12人参加) ※報告要旨は「センター通信」56号に掲載 11月20日(日):京都教育研究集会参加 12月25日(日):京都教育センター研究会第2分科会(生活指導分科会と合同) * なお、2011年度から発達問題研究会の事務局体制の確立が不十分になったため、6月公開研究会以後の独自活動がほとんど行えなかったことをおわび致します。 |
||
Ⅱ.2012年度の活動方針 |
||
2012年度の活動方針は昨年に不十分に終わった課題について、引き続き取り組むことが中心となる。 ①「思春期の子ども」研究を継続させていく。 ②「人間発達の土壌としての学校・地域」「学校や地域は子どもに何ができるか」ついて研究を深める。 ③「インターネット時代と子どもたちの認識・発達」「ケータイ文化と子どもたち」などの情報社会の中での子ども達の発達の姿を明らかにする。 ④昨年度の反省をふまえ、発達問題研究会の事務局体制の確立と強化、会員への連絡体制の強化などについても基本的な問題として取り組んでいきたい。 |
||
Ⅲ.研究会組織体制と構成員 |
||
・代表者 宮嶋邦明、築山崇 ・事務局 西浦秀通、浅井定雄 ・運営委員 伊藤晴美、北村彰、久保田あや子、中山善行、和気徹 ・会 員 荒木巌、池上淳、梅木智恵、大平勲、春日井敏之、神谷栄司、川口伸、黒田学、清水民子、高垣忠一郎、高橋繁子、中村純子、西川由紀子、野中一也、葉狩宅也、人見江利子、堀川学、八木英二、吉田志朗、横山悦生、横内廣夫、湧井幸子 |
||
|
| 事務局 | 2011年度年報もくじ |