| 事務局 | 2011年度年報もくじ |
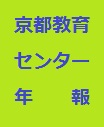 |
京都教育センター 第42回研究集会 第8分科会 卒業後の生活を見渡し、学校教育で大切にしたいこと ―キャリア教育などの動向も踏まえ 西城信幸(京都障害児教育センター) 共同研究及び助言 丸山啓史氏(京都教育大学) (*この報告は、京都教育センター事務局の責任で編集し、見出しは編集者がつけました。 |
|
基調報告 「キャリア教育をどう考えるか」 京都府立八幡支援学校 西城信幸 キャリア教育は、1980年代以降新自由主義の全世界的な進行の中で表れた、経済、雇用、暮らし等の大きな変化の中、ニートや雇用のミスマッチという言葉で表わされる若年層の雇用状況の変化に対し、国を挙げての対策として進められたものです。障害児教育の分野でも、キャリア教育を教育課程の中でどう位置づけるのかなど論議の俎上に上がってきました。その一方で、キャリア教育のとらえ方は様々であり、明確ではありません。そのため、「100%(企業)就労を目指す」、「小学部からの作業学習」という形での批判、あるいは、その本源的なレベルからの批判をすることで「キャリア教育」を全否定するのか、それとも、学校現場で「キャリア教育」をとらえなおしていき、別の方向性を出していくの論議が必要であり、今回は、京都府教育委員会や国立特別支援教育総合研究所の報告などからキャリア教育をどのようにとらえることができるのか検討した。 (1)菊池講演を受けて「キャリア教育」を定義するならキャリア教育:「働く」ということに視点をおき、学校卒業後に社会生活を送っていくうえで必要な力を育てること。 (2)「働く」ということの定義 「働く」ということは、各自それぞれにおいて多様であることを押さえていかねばならない。「働くこと」は、社会参加の一つの形で、利益を得るだけのものではない。企業への就労や福祉施設への就労と様々な場所、形態、内容があり、家庭や地域での生活の中にもある。一番大切なところは、自分ができる何かをすることによって認められたり、人に役立つことをすることが、「働く」と言うこと。 (3)「キャリア教育」を実践するうえで押さえるべき点 実践の場では、児童生徒の「願い」を大切に、「やりたい」「わかる」「できる」「やった」という思いを引き出し、主体的な活動・参加を保障していくことが大切である。 教育全般における「キャリア教育」の動向 丸山啓史 そもそも「キャリア教育」は子どもたちからスタートしたものではなく、大企業や政治の分野から発信されたものである。社会保障には金を使わないという状況のなかで、障害者にとっての働く場も個人の責任が追究されてきた。 勤労観や職業観を育てるとされる「キャリア教育」も定義が変化していく中で、「キャリア教育」には、専門的知識・技能を育てる職業教育の観点が抜けているのではないかという意見もある。 現在各校で行われている、作業学習は職業教育なのか、どのように位置づけられているのかも検討がいる。 報告1 「自分のペースで自信を積み上げ、主体的な自分づくりを」 〜仲間の中で認めあえる生活から、社会に出て生活する力に〜 京都府立向日が丘支援学校 高等部 射場 隆 竹下 誠 障害を持つ子どもたちの青年期教育には、何を大切にしていったら良いのか。そのことを子どもたちの姿から考えていく必要があります。レポートの中では、向日が丘支援学校高等部の軽度知的障害の生徒の職業等の授業で何をねらっているのか、具体的にはどんな授業をしているのか等報告された。 重要な点として、授業の中で一人一人の活動の見通しがあり、主体的活動が保障されることで、誇らしい自分が感じることができる。実践を作るときの視点は、自分作りの視点、自己解放の視点、集団の大切さの視点があげられた。 次に向日が丘での職場実習・進路学習・進路相談などの進路に向けての取り組みの実態が報告された。そして、卒業生へのアンケートや卒業生の発言などから、責任感を持つこと、目標を持ってやりきる力、自分をコントロールする力、生徒会等を通して、みんなの前で話ができる力を培うことの大切さが語られた。 高等部卒業後の自立訓練事業 丸山啓史 自立訓練事業として来春から取り組まれる「プエルタ」の取り組みが紹介された。職業訓練だけでない、青年期の取り組みを作り出していく必要があることが、報告された。 質問の中で、発達障害の方の進路として、高等学校に在学されている方等にとっても必要な取り組みではないかと言われていた。 交流・論議 府内の特別支援学校では、「キャリア教育」について提起がされてきたところで、とらえ方はまちまちであるが、ある学校では、ふれあい心のステーションに、中学部の取り組みで地域の農地を借りて栽培された野菜が出され販売されたが、その取り組みの教育課程上の位置づけはどうなのか、論議が必要であることが出されていた。 京都市では、総合支援学校の白河や鳴滝は選別があるので、中学校3年生の7月段階で、企業就労する意思があるのかないのかが問われ、「キャリア教育」の「4つの能力領域」で評価されており、総合支援学校の高等部での取り組みが、中学校段階にも大きな影響を与えていることが報告された。また、「生き方探求館」での取り組みも紹介された。 丸山先生より、「キャリア教育」のとらえ方は様々であり、各校の状況をつかんでいく必要があること、授業の作り方なども大きく変化していること、そのことが「キャリア教育」とどのように結びついているのか、そして卒業後の姿を丁寧に調査していく必要があることが指摘された。 課題 各校の取り組みの実態や実際の授業の中で、何を課題とし、どのような教材を用いるのかなど、具体的な実践の交流、論議を通して、卒業後の生活を見通して、大切にしていかねばならない教育内容は何なのかをまとめていき、共通理解を図っていく必要がある。 |
||
|
| 事務局 | 2011年度年報もくじ |