| 事務局 | 2011年度年報もくじ |
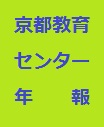 |
京都教育センター 第42回研究集会 第7分科会 「国語教育の現状から課題をとらえ、 だれにでもできる国語教育実践の創造を」 浅尾 紘也(教科教育研究会・国語部会) (*この報告は、京都教育センター事務局の責任で編集し、見出しは編集者がつけました。 |
|
<午前> 提起1 国語教育連続学習会でなにが提起、討議されたか 九野里信夫(国語部会事務局) <午後> 提起2 だれにでもできる言語の学習実践 鶴尾和広(亀岡・本梅小) 提起3 だれにでもできる文学教育実践 浅尾紘也(京都国語教育実践研究所) 【教科教育研究会・国語部会】 【運営担当】 西條昭男・荻野幸則・九野里信夫・相模光弘・浅尾紘也 |
||
「国語教育の現状から課題をとらえ、 だれにでもできる国語教育実践の創造を」 ~国語教育分科会で、何が提起され、何が論議となったか~ |
||
上記のテーマのもと、まず西條代表のあいさつに続き、国語部会事務局・浅尾からの基調提案があった。 教育基本法改悪、改定指導要領の本格実施、新国語教科書での、言語技術教育・言語情報処理能力訓練の具体化という、国語教育の危機的状況が具体的に進められていく中、府下の状況・その問題点はなかなかとらえにくい状況にあり、問題点が意図的に隠され、国語教育の変質がその中で進められようとしている今、それをどのようにとらえて、どう対していくか、それが問われている。 それには、これまでの京都の国語教育研究と運動が創りだしてきた成果をふまえて、それを現状に合わせて再構築していき、「だれにでもできる国語教育」の提起をしていくことが大切であること、国語分科会であることの共通認識から、学習・討議は出発した。参加者は、10名であった。 |
||
提起1 国語教育連続学習会で何が提起、討議されたか(九野里信夫) 国語部会の昨年度からの四回にわたる取り組みである国語教育連続学習会で、何が提起され、どう討議されたかが詳細にわたってまとめられ、提起された。 <提起> この連続学習会は、全国教研国語分科会より、教研開催20年の節目に当たって、それまでの提起と討議をまとめ、その成果と積み上げ、課題を明らかにしつつ国語教育の理論と実践についての共通認識・共通理解をすすめていくことをめざして編集された「国語分科会20年のあゆみ」を検討していくとりくみを、京都の国語教育研究運動の成果と課題という視点をもちつつすすめていこうとして企画されたものであった。 第一回「課題提起・言語の学習」(10/2月)第二回「説明文教育」(10/3月)第三回「文学教育」(11/5月)第四回「作文教育」(11/6月)にとりくまれた学習会では、この「国語部会20年のあゆみ」の編集に携わった共同研究者が提起し、それを討議するかたちで進められた。 *各回のまとめについては、「国語部会通信」49・50・51・52号に掲載されているものを参照。 この討議によって、現在かかえている京都の国語教育研究運動の弱さや問題点も浮き彫りになってきている。 現場を覆う言語技術主義・技能主義から活動主義へ、さらに言語処理の力偏重の国語の指導は、わたしたちが、子どもたちの人間的成長を「ことばの力」をのばすことですすめ、「人格の形成をめざし」「真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび」、「自主的精神に充ちた」人間の創造という教育の目標にふさわしい教育活動としての国語教育実践をめざす、京都の「国語教育三分野説」をも空洞化し、崩壊させるものとなっている。 言語の学習は、「学ばない言語の学習」という状況となり、何を・どこまで・どう学ぶかという大きな整理のし直しが課題となる。また説明文教育が「読まない説明文教育」となっている中、そこでの論理的文章の読みが、言語の学習を基礎としてそれが活きた力として子どもたちにつけていくことをめざす実践のあり方、その実践方法はもっと多くの実践が集約されて深められていかねばならない状況となっている。 さらに文学教育が、いまや「読まない文学教育」といわねばならない状況であることをどのように読むのかも論議しながら、「文学を文学として読む」ことが歪められ、「ためにする指導」に堕し、読み手の主体が軽んじられていき、「読ませる指導」ばかりが強調されることで、文学の教育力が狭められ、矮小化されることを乗り越える理論と実践の提起が今、求められている。 そのために、京都教研国語分科会やセンター国語部会の活動では、これまでの理論的実践的成果をどのようにふまえるのか、現状をどうとらえ、何を提起していかねばならないかを視点としてもっての討議が大切だと考える。 *さらに詳細には、「国語教育連続学習会で何が提起、討議されたか」(九野里提案)を参照。 <討議> 討議の時間は、限られていたが、地域での違いがある現場の状況も交流され、提起されたことの必要性も確認された。 また、これをさらに具体的に考えていくために、昨年度の国語分科会での児言研・森慎氏の「説明文教育」についての講演・提起、さらには午後の「言語の学習」と「文学教育」についての提起を、この視点から深めていくことの大切さも確認した。 提起2 だれにでもできる言語の学習実践(鶴尾和広) 「だれにでもできる言語の学習実践~三年生でのとりくみ~」は、これまで京都教研国語分科会、センター研でも提起されることがなかった、「言語の学習」実践をどのように体系立てて実践するか、それを具体的に提起したものであった。 提起は、「言語の学習」が国語教育の基礎・基本であり、とりわけ「説明文教育」に、言語の学習の「文法教育」「語い教育」が直接つながるものであるという問題意識をもったものであり、現場で「ことばの力をつける」という名目のもと、多くの市販のプリントやドリルが用意されている現状で、それが読解の訓練・加キルでしかないことから、より体系的系統的な指導のために、どうすればいいかということからスタートしたものであった。 そして、まず国語教科書の言語教材を分析し、それをもとにして、より体系的な教材に差し替えること(修飾語・対義語)、つけ加える教材(文末表現・同音異義語・常体と敬体・名詞動詞形容詞)をどう配列するかを計画してとりくみ、それが説明文教育にどういかされていったかを検証したものであった。 この差し替え、つけ加えの言語教材としては、京都国語教育実践研究所が編集した「言語教材プリント(文法品詞・文法構文・語い)」であった。 *さらに詳細については、「だれにでもできる言語の学習実践~三年生でのとりくみ~(鶴尾提起)を参照。 <討議> 討議では、国語教科書の言語教材のまずしさ、現場におろされている「言語事項重視」の名のもとのドリルや訓練、作業プリントの実態などがこうりょうされた。しかし、「言語の学習」としての内容はどうあるべきなのか、どのように説明文教育につなげていくのかなどの本質的な論議はできず、指導方法についての疑問などが出されたにすぎなかった。 このように年間計画を見通して、何がどのように実践できるかにとりくんだ提起は、多くを学ぶ必要のあるものであろう。そして「論理」を読む力として小学校でどう実践され、中学・高校の実践につなげていく視点が明らかにされていくことが大きな課題である。 提起3 だれにでもできる文学教育実践 (浅尾紘也) 三つ目の提起は、議論が多く、わたしたちがたしかめてきた文学教育の理論と実践のつみあげが、狭められ歪められている文学指導の横行の中で、豊かな文学教育実践にとりくめない状況の中、その本質的な論議のために、また特別な方法ではなくだれにでもできる文学教育実践として、何が大切にされねばならないのかを問題意識として、「だれにでもできる文学教育実践~京都の国語教育研究をふまえて~」の提起であった。 文学教育の本質的な論議は、京都の文学教育研究運動がつみあげてきた、「作品をどう読むか」という視点だけでなく、「子どもたちがどう読んでいるか」を大切にしていく実践を進めていくことが追求されてきたことが、「文学を文学として読む」ことであり、道徳教育や同和教育、生活指導のためにする指導から脱し、偏った教材分析や指導過程の固定化などによって、「教え込む文学指導」に堕すことなく、子どもたちが主体的に読む文学教育として、文学の教育力を活かし、愛国心注入教科として神話さえも文学指導として持ち込もうとする意図が露骨に見える現状を乗り越えるものとなることをめざし、教師と子どもたちがともに楽しめる文学教育実践がだれでもとりくめることを視点としての提起がされた。 その中で、だれでもとりくめる豊かな文学の授業の視点とは、 ① 作品のすべてのことば・表現を形象として読む。 ② 形象の読みの意味を考えることで、主題を読む。 ③ 自分の読みを持つこととともに、仲間の読みに学ぶことを大切にする。 ④ 文学の読みの力をつけ、自ら文学の教育力を享受する力をのばす。 にあると、子どもたちの感想や読み、授業の分析などをとおして提起した。 これは、子どもたちが主体的に読むことが、教材分析と称して教師が設定するものに無理やり近づけさせることばかりが強いられたり、授業豊かにすすめられないことが教材分析の弱さとして片づけられたり、さまざまなジャンルや文体、テーマをもつものが固定的な指導過程に無理やり押し込まれてしまうこととなったりすることが、これまでの論議を活かすことなく主張されることが多くなっている状況への批判でもある。 <討議> 論議の中では、部分的に提起された方法論に対する疑問が出されたりしたが、全体の問題意識が論議されたり、疑問に対しての具体的な方法論が示されるものとはならなかった。 しかし、大きく変わらされようとしている文学教育実践に対して、より実践的な文学教育理論や方法論が討議されることは、今、必要ではある。 とりわけ、国語教育の構造論として京都の国語教育県境運動のなかで創られた、「国語教育三分野説」のまとめとして出版された『国語教育―三分野説・その理論と実践―』(82年刊)に示された。
という実践的なつみあげのなかでまとめられた内容をおさえて、よりたしかなものとして論議をすすめていくものなる。 さらに今後のとりくみを 国語教育分科会での提起は、現在の京都の現状を乗り越えていくために重要な内容をもつものであった。 大切なことは、その論議を分散的なものとしてしまうことなく、現場の実践に対して意味のあるものとして、何が共通認識・共通理解され、何が論議のかだいとして残るのか、実践としてどう進めていくのかが明確になるような論議としていくことである。 実践の量的現象が際立ち、府下全体の状況が集約できにくくなっている教研国語分科会にも言えることだが、これまでの成果をどう生かすかという視点を明確にしつつ、現状に合わせた、現場教師が望む提起・主張をまとめ、「だれにでもできる国語教育実践」を構築していくことである。 今後の論議は、今不足しているこの視点を明確にしていくものとしたい。 また、今回も明らかとなった、「言語の学習」「説明文教育」「文学教育」「作文教育」の各分野での論議すべきことをさらに深めることと、それを全体として国語教育として構造と内容をしっかりとらえることで、見通しと自信をもっての実践がとりくまれていくことをめざしたい。 今後の国語部会のとりくみも、この具体的な活動をすすめたい。 |
||
|
| 事務局 | 2011年度年報もくじ |