| 事務局 | 2011年度年報もくじ |
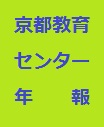 |
京都教育センター 第42回研究集会 第4分科会 「子どもにとってはすべてが育ちの場」 姫野 美佐子(子どもの発達と地域研究会) (*この報告は、京都教育センター事務局の責任で編集し、見出しは編集者がつけました。 |
|
1.基調報告:子ども受難の世の中でも元気でいられる子どもの姿を 姫野美佐子(子どもの発達と地域研事務局) 今年3月に東日本大震災と、東京電力福島第一原発事故が起こり、誰もが忘れられない年となりました。今、福島で子どもたちは、青空の下で思いっきり遊ぶ権利を奪われています。子どもに関わる大人として、本当に胸が痛みます。私たちが研究会の中で考え議論してきた「遊ぶ権利」「子どもの発達にとって本当に大切な、遊ぶということ」について、この分科会でも2つのレポートからより深くその意味を学べると思います。また山科からのレポートでは、学びや集団につまづいている子どもたちとの関わりについて知ることができます。「子どもにとってはすべてが育ちの場」-この言葉通り、暖かく見守り関わる大人たちの存在によって、また子ども自身が持つ力によって、子ども受難の世の中で、それでも子どもが元気でいられる姿を、話し合いたいと思います。 2.報告(1)「地域で展開する学習支援」 梅原美野(山科醍醐子どものひろば:のびのびラーニング) ①1980年に前身団体である「山科醍醐親と子の劇場」が誕生し、活動を続けてきた。その後1999年に「山科醍醐子どものひろば」となり、2000年にNPO法人認証となる。母親だけでなく間か物ボランティアを巻き込み誰でも参加できるNPO団体で、現在、約150名のボランティア(うち約50名の活動スタッフ)がいる。年間約30事業、約2万人(のべ人数)の子どもや子育て世帯に体験や支援活動を提供している。国や地方自治体から表彰を受けるなど、社会的評価も受けている。テレビの取材も受けた。(参加者で、その録画番組を鑑賞) ②新たに始まった「子どもの貧困対策事業」として「『楽習』サポートのびのび」がある。背景には、山科醍醐地域が抱える子どもの貧困問題がある。2009年統計では、全国生活保護率は26.5%だが、山科区では34.9%、伏見区では42.9%と高い。「『楽習』サポートのびのび」は、もともと「子どものひろば」の活動に参加していたお母さんからの声で始まった。京都市立の地域の小学校との連携もとっている。学校→銭湯→施設→学校という「お泊り」を実施していたときもある。(今はしていない)。他に支援としては、マンツーマンで学習支援をしたり、中3勉強会をしたり、ワンコイン勉強会、宿題お助け隊、昔遊びの会、書初め教室など、さまざまなことに取り組んでいる。 ③良い意味での変化の連鎖が見られる。活動にくるたびに、子どもがいろんな表情をみせてくれるようになる。→子どもが変わると、大学生サポーターにも変化が。→サポーター ④これから目指していくこととしては、「学校、商店街、青少年活動センター、寺院など地域との連携にもっと力を入れたい」「寄付で子どもを支えているが、参加費のハードルを低くして、社会に応援される活動を目指す」「この事業が、山科醍醐地域以外にも広がるように、モデルとなる事業づくりをしたい」などがある。 3.報告(2)「子ども会・少年団を育てる左京センターの活動から」 石田 隆(子ども会・少年団を育てる左京センター) ①そもそも「子ども会・少年団」って-歴史、活動、めざすもの-大人の願いがいっぱい 歴史―40年を超える歴史を持っている。1960年代の青年学生中心の運動から父母も専門家も入った大人の運動へと転換。1972年、少年少女組織を育てる全国センター結成。1976年、京都少年少女センター結成。1998年、京都少年少女センターより独立して左京センターを結成。2004年、全国センターから少年少女センター全国ネットワークへ移行。 やっていること-やっていることは地道だけどすごいこと。教育基本法、子どもの権利条約の後押し。 ②目指すものー目的、テーマ、提言など。 目的―(左京センター会則より)左京センターは、京都市左京区で活動する子ども会や小年団などの子ども組織に関わるか、または、関心を持っている人たちが参加します。子どもたちの自主的・自治的な活動を大切にし、子どもたちの豊かな成長と発達を目的に、活動交流、学習、行事など共同の取り組みをおこないます。 ③「第41回子どもの遊びと仲間を育てる全国集会」は京都で開催された。(11月5、6日)テーマは「子どもにとって大切なことって?」あそびと仲間・異年齢集団の関係づくりを大切にしている。集会の概要としては、これまでの小年団を中心とした取り組みから他団体も含め広がりのある集会を目指した。子育てネットの広がりや、DCI京都セクションの発足、3・11の年、10年ぶりの京都開催などの背景があった。記念講演は、DCIに本事務局長である世取山先生で「子どもの育ちと大人のかかわり」~子どもの権利条約から読み解く~として課題に迫った。 4.報告(3)「右京子どもまつりの取り組み」 後藤 米江(右京子育て・教育ネットワーク事務局) ②「子どもをまん中に地域の連携を深めよう」2009年6月「地域子育て教育ネットワーク京都」の発足。他の地域ネットワークとの交流の中で各種団体・個人が一つになって取り組める子どもまつり構想が生まれる。「右京子どもまつり」の柱は、子どもが主体となる、地域の団体・個人の交流、お金をかけないで楽しくの3つ。祭り成功に向け、児童館・保育所・幼稚園なども含め広く地域の団体・個人に呼びかけた。また、子ども達の要求に即した多彩なコーナーを実現しようと「もの作りのコーナー」「文化的な催」「活動的なコーナー」などを考えて実施した。会場さがしには苦労した。いくつかの条件をあげ、それぞれが分担して使用条件、費用などを検討。「安井公園芝生の広場」に決定。貸してもらえることになったが、取り組み終盤になって、会場管理団体から様々な申し入れを受けた。後日、まつりが終わってから京都市のまちづくり推進課に「会場使用にあたっては、主催者団体によって許可条件が異なることがないよう適切な対応をお願いいたします」と申し入れを行った。 ③「成果と今後の課題」降水確率が高く、開催にあたって迷いはあったが、第1回目をなんとか成功させたいという思いで開催。開会中3度の雨に見舞われながら、要員50名、参加者650名で成功。3本柱の観点から、ア:子どもが主体的に取り組めたかー各コーナー、特に手作りのコーナーでは担当者の助言を受けながら熱心に製作に取り組む多くの子どもの姿が見られた。また遊びのコーナーでも夢中になって遊んでいる子供の姿が印象的だった。読み聞かせのコーナーでは、そばで大音量のマイクが入ってるにも関わらず熱心に読み聞かせに聞き入る子どもがいて、読み手を感動させていた。ただ、企画段階でもっと子ども達に参加してもらう手立てはないのか。研究の余地あり。イ:地域の個人・団体の交流―この取り組みを通して協力が深まった。ないないづくしの取り組みの中で、それぞれの個人・団体の持ち味が生かされたものになった。今回つながれなかったところにも次回働きかけを強めていきたい。たくさんの保育園・幼稚園・児童館を訪問したが、今回積極的に参加していただいたのは児童館1、保育所1だった。1回目ということや実行委員会名での申し入れで主催者が不明瞭など、様子見がみられたのではないか。しかし、今後につながる活動として評価したい。多くの団体・個人が無報酬で参加応援していただき地域の底力を感じた。この交流を通じて他の問題でもお互いが積極的に提起すれば協力し合えるという確信が持てた。ウ:お金を使わないでー参加した子どもたちがお金を使わないで楽しく参加できるよう広告収入を得る取り組みやコーナー担当団体のボランティア精神を発揮していただいた。しかし宣伝費、原材料費、要員弁当の支給、備品だけでも90000万円近く費用を要した。今回の会場は1日1000円という低料金だったので助かった。こういう値段で借れる会場がもっとほしい。エ:コーナー担当者の感想からーメインステージのだしものは、バラエティに富んでいて良かった。参加している子どもたちが生き生きキラキラしているのを見るのが嬉しかったですが、コーナーを担当している大人の方が、とても楽しんでいました。いろんな知恵を集める楽しさ喜びを感じることができました。 5.〈討論の前に〉棚橋啓一先生(子どもの発達と地域研究会)から
|
||
|
| 事務局 | 2011年度年報もくじ |