| ������ | �Q�O�P�P�N�x�N������� |
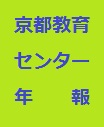 |
���s����Z���^�[�@��S�Q���W��@��R���ȉ� �u�w�͂̊�b�Ƌ���ے����l����v �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����@�p��i�w�́E����ے�������j �i�����́̕A���s����Z���^�[�����ǂ̐ӔC�ŕҏW���A���o���͕ҏW�҂����܂����B |
|
�P�D�͂��߂� �@2009�N�ȗ��A�w�K�w���v�̂̉����ɔ�������ے��Â���̌����̃e�[�}�Ƃ��āA�e���ȁE�Ȗڂ́u��b�I�Ȋw�͂Ƃ͉����v��ݒ肵�āA����������i�߂�Ƌ��ɖ{���ȉ�ł��̌����Ɗe�w�Z�Ŏ��g�܂�Ă�����H���������邱�Ƃ𑱂��Ă����B �@���N�x�́A�u��b�I�Ȋw�͂Ƃ͂Ȃɂ��v���������邽�߁A�L���[�o���A�����J�́u�����w���v�ɏے�������b�w�͂���Ă鍑�ƓI���ƂƂ��̈Ӌ`���A�L���[�o��K�₵�Ď��@���ꂽ��˕y�͐搶(�����s�s�����w�Z)�ɕ��Ă����������B����ɁA3.11�Őr��Ȕ�Q�����������{��k�ЂƂ���ɘA������������ꌴ�����̂Ƃ���ɔ����w�Z����ً̋}�̉ۑ�Ƃ��ċ���ے���̖��_���������邽�߂ɁA�s��͐l�搶(�{�������w�Z)�ƒҌ��i�搶(���s�s���w�Z)�̓�l�ɒ�ĂƎ��H����Ă����������B �@�{�N�x�́A14���̎Q���ŏ[�������������s�����Ƃ��ł����B �Q�D��@�����̋�����Ƃ��Ă̊�b�w�͂Ƃ͉����@�@����@�p��i���s����Z���^�[�j �@�����w�K�w���v�̂Ɋ�Â��w�Z���炪�n�܂�A���O���Ă����ʂ�A�������̉ۑ肪���炩�ɂȂ����B����́A�@�w�K���e�̑����ɂ��u�Ă��˂��Ȋw�K�v���ł��Ȃ��Ȃ������ƁA�A���ʊ������ԓx��`�ɂȂ�A���t�́u�w�����v����苭�߂�ꎩ�劈���Ƃ��Ă̎q�ǂ��̊w�K���錠�����q�ǂ��̌��������y�����邱�ƂƂ����킹�ĂȂ�������ɂ���邱�ƁA�B�����{�@�̉��������f���āA���ނ��Ȋw�I�ȍl�Êw����_�b�ɒu�������A���ނ̓������牻�ƐV�ێ��`�����`������ƍ��Z�̑S���Ȃŋ��v����Ă��邱�ƁA�C����]����V���R��`�̋��E���Ǘ��ŋ����̋��猠����������������Ă��邱�ƁA�D2009�N���{���q�͊w��̊w�K�w���v�̂Ƌ��ȏ��ɑ���O��I�ȍU���i�j�ƁA10���ɕ����Ȋw�Ȃ��o�����u���ː����ǖ{�v�́A���{�̍��������ʂ��鐶���̊�@�ł����镟���������̂��ǂ̂悤�ɗ������Ή����邩�Ƃ����傫�ȉۑ�ɑ��āA���{�̘_���Ŋw�Z������g���ĉ������������Ƃ��Ă��邱�Ƃł���B�E�����������̂Ɗw�Z����Ƃ̊W�ł́A�����ƌ������̂𗝉�����Ƃ����_�ŁA����30�N�Ԃ̊w�Z����Ŏq�ǂ������łȂ����l�̑����ɂ��A���R�Ȋw�ƎЉ�Ȋw�̊�b�w�͂��g�ɂ��Ă��Ȃ��Ƃ����ۑ肪���炩�ɂȂ����B �@����ł͌o�ςƐ����̏f���āA�q�ǂ������̐����Ɗw�K�̌�������邱�Ƃ���ł��Ȃ���Ԃɂ�����Ă���B���N��6�����_�ł́u�p�[�g�^�C���J���ґ������Ԓ����v�̌��ʁA�p�[�g�J���҂��]�ƈ��ɐ�߂銄���́A27���ɂȂ�A�K�J�����̊�����5�N��3.5����������34.4���ɂȂ������Ƃ\�����B����́A1990�N�ȍ~�ł͍ő�ŁA�e�̘J���������}���ɒቺ���A�q�ǂ������̉ƒ���Ɗw�K���̈������i��ł��邱�Ƃ������Ă���B�w�K�w���v�̂̉����ŁA�w�K���e�������A���Ǝ��Ԑ�������Ɍ������đ������Ă��Ȃ��ł́u�ƒ�w�K�v��u�m�E�\���Z�v�Ȃǂł̕⊮��O��Ƃ����`�����炪�s���Ă���B���̂悤�Ȓ��ŁA�����Ƃ��Ă̕K�v�Ȓm���◝���A����ɏ����̘J����ۏႷ�邽�߂́u��b�ƂȂ�m���E�����E�Z�p�v�̊l���́A���ׂĂ̎q�ǂ��ɕ����ɕۏႳ��Ă��Ȃ����Ԃ���R�Ƃ��邱�Ƃ���������K�v������B���Z�𒆑ނ��鐶�k���Ԃ��Ɍ�������ƁA�@��w�͂Ɗw�K�ӗ~�̌��@�A�A��{�I�Ȑ����K�����`������Ă��Ȃ��A�B�l�ԊW��z�����Ƃ��ł����A�Ǘ����Ă���A�C����(�g�сEmail)�E������(�C�k�E�l�R)�E���s���E�ւ̈ˑ��D�e�����DV�ENeglect)�E�n���w�̌Œ艻������)�Ȃǂ��ł���B �@�w�͂�g�ɂ���Ӗ��́A�@�l�ԂƂ��Ă̔��B��ۏႷ�邱�ƁA�A���܂���Ȃ��A�Ȋw�I�ȕ��̍l����g�ɂ��邱�ƁA�B�Љ�̒��Ől�ԊW�����сA�J���\�͂̊�b���͂����݁A�W�c�E���ԂƐ����Ă�����悤�ɂł��邱�Ƃł���B���A�w�K�w���v�̂̉����Ƃ��������w�͂��߂���ۑ肪�傫�ȊS���ɂȂ�Ȃ���A�w�Z���⋳�t�ԂŊw�͂̓�����w�͊ς��ǂ̂悤�ɑ����邩�A���̕]�����ǂ̂悤�ɂ��邩�A�܂��w�͕ۏ�̕��@�_�ɂ����Ă���v���Ď��g�ނ��Ƃ��ł�������������o���Ȃ��ł���B �@���̈���A�w�K�w���v�̂̉����Ƃ��̊w�͊ρA�w�K�ς̕ϓ]������A���ɂ́A������H�̉ۑ�Ƃ��đ��l�Ȋw�͊ς��q�ǂ������̊w�K��ۏႵ����Ă��Ȃ��_�ł���B����́A�@�w�͂��ǂ̂悤�Ȋw�K���e�ɂ��邩�A�A���̊w�͓��e�́A�q�ǂ��̗v��(�e�̊肢�A�Љ�̗v��)�ɍ����Ă��邩�A�B���ꂪ�w�K�ߒ�(�w���ߒ�)���o�ĕۏ�ł������ǂ����̕]�����ǂ����邩�A�C�w�͕ۏ�̗v�ɂȂ�w�K�E���Ƃ��ǂ̂悤�ɂ��邩�A�D�����I���t�Ǘ��ɑ��Ăǂ̂悤�ȓW�]�������A�Ȃǂł���B�������́A���݂̋���ۑ���������邽�߂ɁA�e���ȁE�ȖڂƓ��ʊ����Łu�����v(��{�I�Ȏw������)�A�u�ǂ��܂Łv(���B�ڕW)�A�u�ǂ̂悤�Ɂv(���ށA���Ɖߒ�)���W�c�I�E����I�Ȍ����ɂ���ċ�̉����邱�ƂŁA�����̎w�E�ɓ����邱�Ƃ��ł���B �P�@�u��A�����J�̎����w���ƃL���[�o�̋��玖��v�@�@�@��ˁ@�y�́i�����s�s�����w�Z�j (�P)�@ �L���[�o�́A1991�N����A�����̃\�A�̉������Ȃ��Ȃ�A�Ǝ��̍������i�߂Ă������B���̕����́A�����̕��Ƃ����Ă���z�Z�E�}���e�B�́u�����A���n������o�Ď���̗͂ł����Ƃ����Ɨ������A���҂ɂ͔����Ȃ�������邽�߂ɂ́A���ׂĂ̍����ɕ����ȋ���@���^���A�����ł��̂��l���邱�Ƃ��ł��鍑������ĂȂ���Ȃ�Ȃ��B�v�Ƃ������t�������悤�ɁA������d�������B���̌��ʁA�u�X�g���[�g�`���h���������Ȃ����v�A�u�q�ǂ��͎Љ�S�̂̕�ł�����Y������A�玙�͕�e��l�ɑ������̂ł͂Ȃ��݂�Ȃōs�����̂��B�v�Ƃ����l��������̒��S�ɂ���A���ꂪ���s����Ă���B���̂��߁A��҂̖ڂ͋P���A�q�ǂ��͖L���ɐ������Ă�����ɐe�ł���B (�Q)�@���琭��̈���u����������^���v�ŁA1960�N�ɍ��A�ŃJ�X�g���哝�̂����������u�ǂݏ������ł��Ȃ����̂́A�l�ނ̈�Y��D���Ă���B1�N�ŕ��ӂ����₷��v�����������g�݂ł������B����́A�u�����͌���ψ���v��g�D���A�e�̗����̌���10���l�̒��E���Z����2�T�Ԃ̌P�������āA2���̖{�ƃ����^���Ɩѕz�������Ĕ_�R���ɑ���A�u�m���Ă���Ȃ�����悤�B�m��Ȃ���Ίw�ڂ��B�v�������t�ɂ���1961�N�ɂ́A������38.3%����5.2%�ɂ����B�����J�X�g���́A�u450�N�ɂ킽�閳�m��j���v�Əq�ׂĂ����B�������Z���Ƃ��Ă��̉^���ɎQ�������l�́A�u�l���ōł��d�v�ȗB��̌o������ꂽ��A����͎����͌���^���ւ̎Q���ŁA���̐��ɑ��݂���Ƃ͎v��Ȃ������n���Ƃ��������ɐG�ꂽ�B�v�Ƃ����Ă����B �@�L���[�o�ł́A15�Έȏ�œǂݏ������ł��Ȃ�������1%���x�ł���B�������A����ƈ�Â͂��ׂĖ����ŁA����͍����̌����Ƃ��Ĉʒu�Â����Ă���A�n�悪�q�ǂ�����Ă邱�Ƃ͓O�ꂵ�Ă��āA�ƂA��Ɓu�w�K�̉Ɓv������A�w���҂����Ċw�Z�ŏK�������e�K���Ă���B�����Ďq�ǂ������Ȃ�����͂��Ȃ��B���̑��ɂ́A�ۈ牀���������Ă��āA�����̎Љ�i�o�������A�e���玙����ȏꍇ�́A���c���̊�h�ɂ�����A��Q�����q�ǂ��ɂ�����ɍ��킹���ۈ牀������B�A�w�O��1�N�Ԃ́A�w�Z���a�����Ă���B���w�Z��20�l�N���X�A���w�Z��15�l�N���X�ŁA�Љ�ɖ𗧂��߂̋���Ƃ��āu�s�I�l�[���w�K�v������B��Q��������������Ă���B (�R)�@�L���[�o�̎����͌��㋳��́A���e���A�����J�A�J���u�C(����12%)��T�n���ȓ�̔M�уA�t���J(����40%)�A��A�W�A(����45%)��28�J���ɍL�����Ă���B���̎�������v���O�����́A�u�W���E�V�E�v�G�h(�킽�������Ă��邳)�v���^�C�g���ɂ���20�y�[�W�̃e�L�X�g���g�������̂ŁA�@�N�ɂł��g�߂Ȑ��l�ƌ��t��g�ݍ��킹���ǂݏ����A�A�����̓A���t�@�x�b�g���ł͂Ȃ��A�ꉹ�Ǝg�p�p�x�ɉ����āB�͂��߂Ɋw�Ԍ��t�́A�ƁA�Ƒ��A�L�X�A���z�A���ł���B�B���k�̐l���o������ɂ��ċ��ނ��쐬���A�g�߂Ȃ��Ƃ��琢�E�I�ȈӖ��ցA�C�w�K���Ԃ́A1����30������A�T��5���ԁA3�����Ń}�X�^�[�A�D�e�n��̃A�C�f���e�B�e�B�A�K���A�@���A�����A�����A�N���X�l�X�̌��d����B �@15���ԃL���[�o�ɑ؍݂��āA�u�w�~���O�E�F�C�̈��������R���킩��C������B�n��������ǂ��L�т₩�ȃL���[�o�ł���B�v�u�ӂ邳�ƃA�t���J�̑�n�Ɏv������̂������o��x��ւ����������A�}���J�X�̊��������ƃR���K�̉�����������鑺�v�u�P�Z���Z���ƌ��V�݂Ȃ���n�o�i�̊X������v�Ƃ������z���������B �Q�@�u�������̂Ɗw�Z����|�����Ȋw�Ȃ̕��ǖ{���߂����āv�@�@�@�s��@�͐l�i�{�������w�Z�j (�P) �d�͉�Ђ�o�ώY�ƏȁE�����Ȋw�Ȃ́A����܂ō��������łȂ��w�Z����ɑ��������́u���S�_�b�v���q�ǂ��ɉ����t�����Ă��s���Ă����B����́A���ȏ��̋L�q�₳�܂��܂ȃp���t���b�g�⋳�ނȂǂł���B�Ƃ��낪�A3��11���̕����������̌��2011�N10���ɁA�����Ȋw�Ȃ͏��w�Z���獂�Z�܂Ŋw�Z��ʂ́u���ː����ǖ{�v���쐬���Ă���܂ł����O�ꂵ�āu���S�_�b�v���w�Z����Ƃ��ēO�ꂷ�邱�Ƃ��˂���Ă���B�����˂��Z��ʂɁu����ҋ��t�p�v�܂ō���čׂ������̓��e���w�����Ă���B �@���{�̌������i���͂́A�X���[�}�C�����������̂�`�F���m�u�C���������̂��N������ɂ��A���{�̌��������S���ƍ����Ɂu���S�_�b�v��U��܂��Ă����B���{���q�͕����U�����c�́A�u���_��}�j���A���v������A�u���̎����L��̍D�@�ƂƂ炦���p���ׂ����v�u���̎��̍L��́A���Y���̂ɂ��Ă����ł͂Ȃ��A���̎��ӂɊւ�����������B�K�v������S���̏��𗬂��B�v�Ƃ������̂ł���B��������ɏ]�������������œ��ɏd�������͎̂q�ǂ���W�I�ɂ�������ւ̉���ł���B (�Q)�@���̇@�ɁA���{���q�͊w��ɂ��u�V�w�K�w���v�̂ւ̒v������B����ɂ́A�u���w�Z���Ȃ̋��ȏ��ł́A���q�͂����d���ɒY�_�K�X��r�o���Ȃ����Ƃ��A���Љ�Ȃ̋��ȏ��ł̓G�l���M�[����������̉������̈�Ƃ��Č��q�͔��d�����łɍ����O�ōL�����p����Ă��邱�Ƃ���₷���Ă��˂��ɋ�����v�Ƃ��A�u���ː��ɑ���A�����M�[�ƂȂ�L�q�͉��߂�ׂ��v�u���q�͎{�݂̈��S���͍����A���ۂɂ̓K���⎩���Ԃ̎��̂Ȃǂ������X�N���\�����������Ƃ��E�E�E������ׂ��v�Ƃ܂ŏq�ׂĂ���B���̇A�Ƃ��āA���N�x����g�p����钆�w�Z�̋��ȏ��ɂ́A���R�Ђ̌������ȏ��ł́A�u���q�͔��d�ł͈��萫�̍����Z�p���m�������v�ƋL�q���Ă���B��Q�Ђ̋��ȏ��ł́A�����Ƃ��댯�ȍ������B�F���u��_���Y�f���قƂ�Ǐo�����A�����̃E�������J��Ԃ��g���闘�_������v�Ƃ܂Ŕ������Ă���B���Ђ̋��ȏ��ł��A�u�����͓�_���Y�f���o���Ȃ��̂Ŋ��ɂ悢�v�ƋL�q���Ă���B �@�����Ȋw�Ȃ�2009�N�ɍ쐬�������ǖ{��4�����z�z���A2010�N�ɂ́A���{���q�͕������c���R�O�Z�ł��̕��ǖ{�� �g���������̏o�O���Ƃ��s�����B�����������̌��2011�N�P�O���ɕ����Ȋw�Ȃ����������ǖ{�u���ː��v�ɂ́A����������S���������Ă���A�����̎d�g�݁A���ː��p�����̏����A�厖�̂̎��ԁA���̌����A�n�k�ƒÔg�̉e���͑S���L�q����Ă��Ȃ��B���ː������ɂ��Ă��S���G�ꂸ�A�����픘���������āA100�~���V�[�x���g�ȉ��̔픘�ɂ��Ắu���m�ȏ؋����Ȃ��v����픘���X�N���Ȃ��Ƃ��Ă���B���ǖ{�ɏ�����Ă��Ȃ������Ƃ����A�q�ǂ������ɂƂ��ĕK�v�Ȓm���ł���B (�R) 2011�N�̕��ǖ{�ɂ́A�u����ҋ��t�p�v������A�����ɂ́A���ː����u�|���Ȃ����́v�Ƃ��ċ����邱�Ƃ��������Ă���B�Ⴆ�A�u���R�E�ł͏�ɕ��ː����Ă��邱�Ɓv�A�u���ː����Љ�̒��ŗ��p����Ă��邱�Ɓv�A�u�K���Ȃǂ̕a�C�ɂ͂��낢��Ȍ���������B���ː��������ƍl������K�����S��������Ƃ������m�ȏ؋��͂Ȃ��v�A�u���ː������������Ă���{�݂ł́A�펞�A���ː����ւ��E�Ǘ����Ă��邱�Ƃ𗝉�������v�A�u���̌サ�炭���ƁA�E�E�E����܂ł̑���Ƃ�Ȃ��Ă��悢�v�A�����́A����܂ł̐��{��d�͉�Ђ̎咣���A������ς��������ł���A�V���ȁu���S�_�b�v�Ō����̈��S������������A���ː��������z�����ފ댯�������ăE�\�������肵�Ďq�ǂ��������댯�ɂ��炷�u�ƍߓI�ȕ����v��������Ă���B �@���̂ق��ɂ��A�ԈႢ����_����������A���̕��ǖ{���w�Z�Ŏg���邱�Ƃ͋ɂ߂Ċ댯�ł���B�������w�K������ʂ��Đ������m���������A�q�ǂ������ɋ����Ă������Ƃ��K�v�ł���A���̂��߂ɂ������w�Z��n��ł̊w�K����J�Â��A�������̂̑S�̂����ނɂ�������Ґ����]�܂�Ă���B �R�@�u�������̎��Ƃ��ǂ̂悤�ɂ����߂邩�v�@�@�ҁ@���i�i���s�s���o���u���w�Z�j �@������ꌴ���̎��̌�A���{�ɏ��߂Č���������ꂽ���C���̑��㑺���́A�u�����̖������̂������̓w�߁v�Ƃ��āu�E�����v��N���ɂ����B�ĉғ��⌴���A�o���˂炤���{�ɕ��𗧂ĂA���܂Ō����ɑ��āu���˔\���o�����Ǔ�_���Y�f�͏o���Ȃ��v���x�̂��Ƃ�������Ă��Ȃ������B����̑�S�������������Ɂu�����Ƃ������Ƃ����悤�v�Ǝv���āA���O�A���P�[�g(�f�f�I�]��)�����āAB4��8�y�[�W�̃��[�N�V�[�g���쐬����2�N����139����ΏۂɎЉ�Ȃ̎��ԂɎ��H�����B �@�������Ƃ̈�T�ԑO�Ɏ��{�������O�A���P�[�g�ł́A69%�������̎d�g�݂�m��Ȃ��A71%�����{�Ɍ�����50�������Ƃ͎v���Ă��Ȃ��A92%�����R�ƕ|���Ƃ����C���[�W�������Ă���A�w�K�O��87%�����������S�Ǝv���Ă��Ȃ��A57%�������Ŕ��d���Ȃ��Ɠd�͕s���ɂȂ�Ǝv���Ă���A�Ȃǂł������B (�Q)�@�n���̋��ȏ��ł́A�����ƃG�l���M�[�̐߂ŁA���q�͔��d��V�G�l���M�[�ɂ��Ă̋L�q�͂��邪�A�����ɂ́A�u���q�͔��d�́A�Ζ���ΒY���g�������d�̂悤�ɓ�_���Y�f���ʂɔr�o���邱�Ƃ͂���܂���B�v(���{�����o��)�Ƃ��u(������)��_���Y�f��r�o���邱�ƂȂ������I�ɔ��d�ł��܂����A���S���̌������ː��p�����̍ŏI���������ǂ��ɍ�邩�̉ۑ肪����B�v(�鍑���@)�Ȃǂ̋L�q������B (�R)�@�������̎��ƂÂ��� �@�Љ�Ȃł͐��_���傫�������������������Ƃ����邪�A���_�����A��{�I�Ȓm������������ŁA�u�N�����͓��l����H�v�Ɠ���������B�������A�����Ɋւ��ẮA�ŏ�����E�����őg�ݗ��āA�Љ�Ȃ̎��Ƃ����������̓���ɂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƍl����B �@���ƂÂ���̊�{�I�ϓ_�́A�@��b�I�Ȓm����������B�A�Ȃ������������Ă����̂��A���̔w�i��������B�B�Đ��\�G�l���M�[�Љ�������Ă������߂ɂ͂ǂ̂悤�Ɏd�g�݂�ς��Ă��������l���邽�߂̒m����������B�C���f�C�A�E���e���V�[�̊ϓ_����u�d�͕s���v�L�����y�[���ɂ��܂���Ȃ��͂ƁA�����̈ӌ������Ă�悤�ɂ���B �@���ƂÂ���̕��@�Ƃ��āA�E�����͂ǂ�Ȏd�|���Ŕ��d���邩�A�E���{�Ɛ��E�Ɍ������ǂꂾ�����邩�A�E�Ȃ������́A�C�ݕ���ߑa�n�ɂ��邩�A�E������ꌴ���łȂɂ��N���������A�E���˔\�͂ǂ�Ȕ�Q�������炷���A�E���̌��q�F�Ƃ͉����A�E�v���T�[�}���v��Ƃ͂Ȃɂ��A�E��������_���Y�f���o���Ȃ��͖̂{�����A�E�����͔��d�R�X�g�������͖̂{�����A�E�������Ȃ��Ɠd�C���s������͖̂{�����A�E�d�͐���̖��A�E���R�G�l���M�[�ɐ�ւ��邽�߂ɂ͂Ȃɂ��K�v���A�����ڂƂ��Ă����Ă���B �@���Ɖߒ��́A�P���ԖځuNHK�X�y�V�����E�`�F���m�u�C���̉f���A�����Ƃ́A�`���̌��q�F�v�A2���ԖځuNHK�h�L�������^���[�E�ъڑ��A�����̃S�~�`CO?���o���Ȃ����v�A�R���ԖځuNHK�h�L�������^���[�E�ъڑ��A�R�X�g�͈������`���R�G�l���M�[�v�A�S���Ԗځu���K�Ɩ���N�A���z���̍쐬�v �@���ƌ�̃A���P�[�g�ł́A�u���Ȃ�|���v��66%�ɑ����A�u������ꌴ���͒N�����������v�̐��������O�A���P�[�g��46%����85%�ɑ������B�u���������炷�v�́A89%�ɂȂ�A����̎��Ƃɂ��āA�u�ƂĂ��ǂ������v��70%�A�u�悩�����v��27%�ɒB���Ă����B���k�́A��������m�肽�����Ă���A�w�т������Ă��邱�Ƃ����������B����ɁA�u�Ȃ������������Ă������v�́A���j�̊w�K���s���ɂȂ�A�����𑝂₷�d�g�݂��t���̖��Ȃǐ����Ƃ���܂��邽�߂ɂ́A�n���̊w�K���������ň������ق����j�S�ɔ��邱�Ƃ��ł���B�u�E�����v�Ɍ����āA���w�Z�Љ�ȂƂ��Č���ꂽ���Ԃłǂ̂悤�Ȓm���E�ᔻ�́E�v�l�͂�����̂��A�v�����̍쐬���K�v�ł���B�n���ł̓G�l���M�[���̊�b�I�Ȓm���⌴���̊댯���A���R�G�l���M�[�̊w�K�A���j�ł́A�픚���Ƃ��ĒN�����̂��߂Ɍ�������������̐��j�w�K�A�����ł͓d�͐���E�ŋ��̎g�����E���R�G�l���M�[�ւ̓W�]��g�ݍ��킹�����B �@���̎��H���u�Ȃ������܂Ō����������Ă������v�A�u�ǂ�������Đ��\�G�l���M�[�ɓ]�����Ă����邩�v���l��������Ƃɔ��W���������Ƃ����̂���(��)�̂˂炢�ł��B ���ȉ�_���� �E�@���w�Z�̍r�ꂪ�Ăіڗ��悤�ɂȂ����B���t�\�͂��p������A�����߂��N����Ȃǐ[���ł���B����́A��b�w�͂������Ă��Ȃ����Ƃ�͍��Z���w���ł��Ȃ��Ȃǐ�����W�]�����ĂȂ����k�������Ă��邱�Ƃ̔��f�ł���B��{�I�Ȃ��Ƃ͋������܂Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����B �E�@�����̊w�K�ɂ́A�Ȋw�̊�b�I�Ȓm�����K�v�ŁA���̂��߂ɂ͌��q�A���q�A�j�A�d�q�Ȃǂ̕����̊�{�������邱�Ƃ��K�v�ł���B��b�I�Ȍ�b��g�ɂ��Ă��Ȃ��ƁA�����͐i�܂Ȃ��B �E�@���d�͓͂Ɛ��ƂŐ�`���K�v�Ȃ��̂Ƀ}�X�R�~�ɔN��2700���~���g���Đ�`���Ă���B����́A�d�͉�Ђ��}�X�R�~���R���g���[�����邽�߂̑���p�ł���A���̋�������Ă���V����e���r�͖{���̂��Ƃ������Ȃ��Ȃ��Ă���B���̂悤�ȃ}�X�R�~���炵�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B �E �����̂��Ƃ�m��Ȃ�������A��b�w�͂̒��Ɍ����𗝉����邱�Ƃ�����Ȃ������肷��̂́A�����Ȋw�Ȃ̊w�K�w���v�̂ɂ�邪�A�����{���̉ۑ�ł�����B�����̊w�K���g�D���邱�Ƃ�����B������TPP�Ȃǎq�ǂ����m�肽���Ƃ����v���͑傫���B�q�ǂ������ɂ������Ƌ�����K�v������B �E�@�Ҏ��H�́A�����I�F�����痝���I�F���ւƂ���ɁA����ɁA����ɂ��i���A�s������܂Ŕ��W�����Ă���B������₷���p���t���b�g�����ȂǁA�Ӑ}�I�v��I�Ɍ����ɂ��Ă̑��l�Ȉӌ������肷��������K�v������̂ł͂Ȃ����B�����鋳�t�́A�S�̑��𑨂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �E�@��́A�����̊w�͖���I�m�ɐ�������ĕ�����₷���Ă悩�����B��b�w�͂�S�Ă̎q�ǂ��ɕۏႵ�Ă������Ƃ̈Ӗ��Ɖۑ�̍l�����́A�܂��Ɍ����I�Ȃ��̂ł���B�u�L���[�o�v�́A��������Đl�Ԃ̐������A�Љ�̂�����܂ōl��������ꂽ�B�����̒��w�ł̎��H�́A���ȏ��������z���A������H�̎��R�Ƃ͉����Ƃ�����{���N������̂ł���A���������B �E ���̓���ԁu�E�����v���l����@��ɂȂ荡�N����ߊ���̂ɑ��������W��ƂȂ����B |
||
|
| ������ | �Q�O�P�P�N�x�N������� |