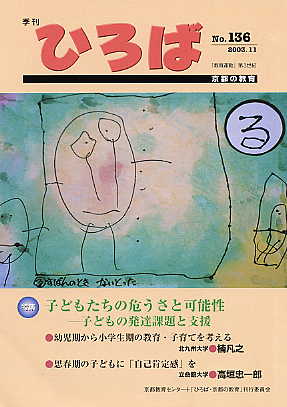 |
思春期の子どもに「自己肯定感」を
高垣忠一郎(立命館大学) |
|
「第二の誕生の時」としての思春期
思春期は第二の誕生のときといわれます。それは大人になるための産みの苦しみが始まるときです。
大人になるとは、「これこそ私の人生だ」と自分の人生を引き受け、責任を持てるようになることだと思います。 私たちの多くは二〇世紀に、日本の社会に、生まれてきました。しかしそのことを自分の意志で選んだ人はいないでしょう。みんな偶然、二〇世紀に、日本の社会に生を与えられたのです。受け身に生を与えられたのです。 吉野弘さんの詩「I was born」にあるように、「生まれる」ということは「受け身」なのです。その受け身に与えられた生を、「これこそ私の人生だ」と言えるように選び直していく産みの苦しみが始まるのが、思春期なのです。だから思春期のことを「第二の誕生の時」と言うのでしょう。 私たちの祖父母、そのまた祖父母のころにも子どもが思春期になれば、第二次性徴が発現し、性に目覚める点では今の子どもたちと変わりなかったであろうと思います。しかし、その頃の子どもの多くが「第二の誕生の時」と呼ぶにふさわしいような思春期を経験できたかというと、そうではなかっただろうと思います。 昔は、どのように生きるのかを生まれや血筋、家柄によって決められていました。またどのように生きるのかを考える余地もないほどに貧しさに追われていました。ところが今日では、多くの子どもたちが、そういう縛りから解放され、曲がりなりにも自分の人生を選んでいける自由と可能性を与えられています。 だからこそ、今日の子どもたちは自分の人生をどう生きるのかをめぐつて、迷ったり、葛藤したりする産みの苦しみを経験できるのです。親も子どもたちに「自分らしい人生を生きてほしい」と願うことができるようになっています。「自分らしさ」とか「自分探し」などという言葉が出てきたのは、まだ最近のことではないでしょうか。私が子どもの頃には「男らしい」とか「女らしい」という言葉は使われても、「自分らしさ」などという言葉は使わなかったように思います。今の子どもたちは「自分らしさ」ということをめぐつて迷ったり、葛藤したりすることもできるようになつているのです。 ところが今日の社会は「第二の誕生」を難産にする困難を他方で子どもたちに与えています。それが今日の社会を支配している「競争原理」です。思春期は受験競争のまっただ中です。「競争原理」という狭い狭い「産道」をくぐり抜けて、第二の誕生を遂げなければなりません。だから難産になるのです。その難産の苦しみが、今日の思春期の子どものさまざまな問題となって噴出してきているのです。 「自己肯定感」と今日の子育て・教育 (1)第二の誕生を支える「自己肯定感」 自分で自分の人生を選んでいくためには、それを支える心が育っていなければなりません。自分の頭で考え、自分の心で感じたことに依拠して、自分の人生を選んでいくことができるためには、「自分が自分であって大丈夫」という自己肯定感が膨らんでなければなりません。自己肯定感が膨らんでない人は、自分が他人からどう評価されるか、どう思われるかということがとても気になって、自分の考えや自分の気持ちに従って、自分の行動や人生を選ぶことが困難になります。 とりわけ、自分の人生の主人公として「第二の誕生」を遂げていかないといけない思春期の子どもたちには、「自分が自分であって大丈夫」という自己肯定感がとても必要なのです。ゆえに思春期の子どもに対する援助に際しては、いかに自己肯定感を育てるかということが今日において特に重要な課題になってきているように思います。 ところが今日の子育てや教育は子どもたちのなかに「自己肯定感」を育てることに必ずしも成功していません。いやむしろ自己肯定感を奪っていることが少なくないように思います。 (2)「脅し」の子育て・教育 人間を動かす、動かし方に少なくとも三つの方法があるように思います。一つは「脅し」で動かす。二つ目に「利益誘導」で動かす。三つ目に「共感」で動かす。残念ながら今日の子育てや教育のなかに、「脅し」や「利益誘導」で子どもを動かす行き方がはびこつているように思えます。 今から十数年前に東京で大変悲惨な事件がありました。中学生の男子が祖母と両親を刺し殺した事件でした。そのときに新聞に「子どもの成績が下がれば小遣いを減らすというような、親の側にも行きすぎた対応があったようだ」という記事が載りました。それは文字通り「小遣い」で操って子どもを自分たちの思うとおりに動かそうとする子育てです。そこまで露骨ではなくても、今私たちの子育てや教育が大人の期待通りの「いい子」でなければ愛情を減らすというような、条件付きの愛情提供によって子どもを動かす子育てや教育に陥っていないかどうか気になります。 もし、そういう子育てや教育に陥っているとすれば、それは「『いい子』でないと見捨てるぞ!」と脅しをかけて子どもを追い立てる子育てや教育だと言っていいでしょう。 そういう子育てや教育の中で育つ子どもたちのなかに、「自分が自分であって大丈夫」という自己肯定感は育たないでしょう。むしろそういう子どもたちのなかには「見捨てられる不安」が膨らみます。 (3)比べる子育て 競争原理で支配された社会のなかで、子育てや教育も子どもたちを比べて順位をつけるものになりがちです。 「太郎ちゃんを見てごらん、あんなによく勉強しているよ」「次郎ちゃんを見てごらん、あんなにいい学校に行ったよ」「花子ちゃんを見てごらん、あんなに元気でお外で遊んでいるよ」こんな風に常に他人と比べて追い立てるメッセージを受け続けて育つ子どもたちは、そのメッセージをどのように受け取るでしょうか。 それは「あなたがあなたであって大丈夫」というメッセージではなく、「あなたがあなたであってはダメなのだ、太郎や次郎や花子でなければならない」という風に受け取られます。そういう子どもたちのなかに「自分が自分であって大丈夫」という自己肯定感は育ちません。 また競争原理に支配された目で子どもを見ていると、比較できる部分しか目に入らなくなります。なぜならば比較して、順位をつけることができるのは、身長や体重、学校の成績など部分的な特性でしかありません。丸ごとの一人ひとりの子どもを比較して、順位をつけることはできません。 ゆえに、比較して順位をつける癖のついた目で子どもを見ていると、丸ごとの子どもを見落としてしまうのです。そして「おとなしいダメな子ども」「成績の悪いダメな子ども」というように部分的な特性でもって「ダメな子ども」と丸ごと否定する怖い「評価の目」で子どもを追い立てることになります。 そういう「評価の目」をシャワーのように浴びながら育った子どもたちのなかにはある種の「傷つきやすさ」が巣くいます。つまり、ちょつとある部分を批判されたり、注意されただけで、丸ごと自分が否定されたように感じて傷つき、落ち込んだり、パニックを起こしたりするのです。そういう子どもたちの姿を学校の教師から開かされることが少なくありません。 さらにいえば、他人と比較する習慣は、恐怖をもたらすように思います。すなわち、他人と比較することで、「自分にはこれが足りない、あれが足りない」と自分のなかの不足、満たされなさを常に意識させられます。その不足や満たされなさ、内面の「空虚感」を満たすために、何かに依存することになります。それはお金かもしれません。地位や名誉、酒や異性かもしれません。何かにすがりついて、自分の「空虚感」を満たそうとするのです。すがりつき、依存するものができますと、それを失うことをとても恐れるようになります。そういう「依存症者」を生み出すのです。 「第二の誕生」の産みの苦しみへの「共感」を (1)「揺れる」間を与える見守り
以上のように、「脅し」や「比較」で子どもを駆り立てる子育てや教育は、子どものなかに「見捨てられる不安」や「傷つきやすさ」あるいは「恐怖」をもたらすことはあっても、「自己肯定感」を育て、膨らませることができません。ゆえにまず私たちは、「脅し」で子どもを動かしたり、比べて子どもを駆り立てるような行き方から、子育てや教育を解放しなければならないでしょう。 そして、思春期の子どもたちの「第二の誕生」の産みの苦しみに共感しながら、子どもと向き合うような援助や指導をつくりだしていかなければなりません。子どもたち、とりわけ思春期の子どもたちは「余計なお節介は焼かれたくない、でも放ったらかしにもされたくない」という欲求を持っています。一歳の子どもが自分の脚で立ち上がるように、思春期の子どもは自分の頭と心で立ち上がろうとします。自分の頭で考え、自分の心で感じたことに依拠しながら、自分の行動や人生を決めていこうとします。だからこそ、考えに迷い、心のなかに葛藤が生じたりして「揺れる」のです。そして「揺れる」ことを通じて人生の主人公として自立していくのです。 だとすれば、私たちはその子どもたちに「揺れる」間を与えてやらなければなりません。 「早くしろ」「ああしろ、こうしろ」と口出しをし、余計なお節介を焼かずに、見守ってやらなければなりません。見守るとは、放ったらかしにすることではありません。自分が守られているという安心感を与えることですJ自分が見捨てられていないという手応えを与えることです。 (2)揺れる心を共感的に受け止めること 今の子どもたちは、余計なお節介を焼かれるか、放ったらかしにされているか、どちらかの子どもが多いのではないかと思います。なかには余計なお節介を焼かれながら、放ったらかしにされている子どももいるようです。 とりわけ、今日の子どものなかには、自分の気持ちを誰からも受け止めてもらえず、情緒的に見捨てられ、放ったらかしにされている子どもが少なくありません。心理臨床の世界では親の機能を「鏡」になぞらえることがあります。つまり子どもの気持ちを鏡のように映し返してやるのです。 例えば一生懸命頑張って勉強したのに、成績がよくな、かった、そのことを訴える子どもの気持ちを「それはがっかりしたね」と映し返してやるのです。そうすると、子どもは自分の気持ちをしっかり受け止めてもらえた安心感をもち、自分が見守られているという手応えを感じることができます。同時に自分の気持ちをしっかりと自覚することができるのです。 ところが、その気持ちを受け止められずに、逆に責められたり、安易な気休めを言って、はぐらかされたりすれば、「わかってもらえない」という見捨てられ感をもちます。そういう子どもたちは、自分の気持ち、とりわけ「しんどい」「つらい」「寂しい」などといった否定的な暗い気持ちを表現できずに、心の中にため込んでしまい、自分でもわけのわからない気持ちを腹痛や頭痛などの身体症状として出したり、「荒れ」や非行という形で行動化することが少なくありません。 今日の人間関係が「明るい」=○、暗い=×という価値観に支配され、人前に暗い感情を出しにくくなっているなかで、「しんどい」「つらい」「寂しい」といった暗い感情を小出しにできる人間関係をつくり、自分が自分の気持ちをともに見捨てられ、置き去りにされているのではなく、見守られているという安心感を与えることがとても大切になっているように思います。 また、最後に付け加えるならば、自分自身が競争原理の洗礼を受け、「いい子」でないと見捨てられるという「脅し」を受けて育ってきた親は、「いい親」でなければならない、「いい親」であるためには「いい子」を育てなければならないという強迫観念にとらわれ、子どもと向き合うことになりがちです。そういう自分を抑圧する自分の内なる「いい子」性と向き合い、それからの解放を援助しあえるような大人同士の人間関係も、とても重要になつているように思います。 |